-
1位
 名護東道路延伸計画、地域住民の長期的な渋滞負担に懸念 (島尻安伊子)
名護東道路延伸計画、地域住民の長期的な渋滞負担に懸念 (島尻安伊子)
-
2位
 さとうさおり氏、減税党DOGEチーム作成の補助金ランキング公開 (佐藤沙織里)
さとうさおり氏、減税党DOGEチーム作成の補助金ランキング公開 (佐藤沙織里)
-
3位
 天皇の男性限定継承に反対 女性天皇の認可を主張 (塩川鉄也)
天皇の男性限定継承に反対 女性天皇の認可を主張 (塩川鉄也)
-
4位
 減税主張に警鐘 持続可能な経済成長に向けた政策の必要性を強調 (米山隆一)
減税主張に警鐘 持続可能な経済成長に向けた政策の必要性を強調 (米山隆一)
-
5位
 「海の家のトイレじゃん」 大阪万博の2億円デザイナーズトイレに批判続出 (吉村洋文)
「海の家のトイレじゃん」 大阪万博の2億円デザイナーズトイレに批判続出 (吉村洋文)
-
6位
 神谷宗幣議員、国民負担率に35%上限設定を提案—消費税減税と税制改革で経済活性化を目指す (神谷宗幣)
神谷宗幣議員、国民負担率に35%上限設定を提案—消費税減税と税制改革で経済活性化を目指す (神谷宗幣)
-
7位
 ガソリン税軽減の「トリガー条項」発動を否定 (石破茂)
ガソリン税軽減の「トリガー条項」発動を否定 (石破茂)
-
8位
 国民民主・榛葉幹事長、外国人土地購入規制強化を訴える (榛葉賀津也)
国民民主・榛葉幹事長、外国人土地購入規制強化を訴える (榛葉賀津也)
-
9位
 石破首相、物価高騰対策を強力に打ち出し参院選へ (石破茂)
石破首相、物価高騰対策を強力に打ち出し参院選へ (石破茂)
-
10位
 島田洋一氏、前原維新を自民増税派の補完勢力と批判 (島田洋一)
島田洋一氏、前原維新を自民増税派の補完勢力と批判 (島田洋一)
企業献金の禁止を巡る議論、政治改革の抜け道と歴史的逆行
2025-03-17
企業献金の禁止を巡る議論、政治改革の抜け道と歴史的逆行
衆議院の政治改革特別委員会は17日、企業・団体献金に関する参考人質疑を行い、日本共産党の塩川鉄也議員が質問に立ちました。慶応大学名誉教授の小林節氏は、企業献金について「本質的に買収行為であり、公共の福祉に反するため禁止すべきだ」と述べました。また、塩川議員は企業・団体献金が国民の参政権を侵害している可能性があると指摘し、企業の資金力が政治に影響を与える現状に警鐘を鳴らしました。
■要点
- 企業献金の禁止:
小林節教授は、企業献金が政治的影響力を不正に行使する手段として機能しているとし、禁止するべきだと主張。
- 参政権の侵害:
塩川鉄也議員は、企業献金が国民の平等な参政権を侵害しているとの懸念を表明。
- 歴史的な逆行:
小林教授は、企業献金が1人1票の原則に反し、制限選挙時代に逆行していると指摘。
- 1990年代の政治改革の抜け道:
1990年代の政治改革で、個人への企業・団体献金は禁止されたが、政党支部やパーティー券の購入という抜け道があったことが改めて確認された。
■企業献金の歴史的な背景と問題
企業献金は、戦前の日本で企業や富裕層が政治家に献金し、政治的な影響力を行使していた時代から続いています。
戦後、民主主義の確立とともに政治資金規正法が作られ、個人献金が主流となりましたが、それでも企業・団体からの資金提供を完全に排除することはできていません。
特に、1990年代の政治改革以降も、企業や団体が間接的に政治家に資金を提供する手段として、政党支部やパーティー券購入という抜け道が利用され続けてきました。この現状は、政治資金の透明性や公平性に対する疑問を呼び起こしています。
■1990年代の政治改革とその限界
1990年代の政治改革では、企業・団体献金を禁止する方向に進みました。しかし、政治家個人への献金を制限しながらも、政党支部やパーティー券の購入を通じて企業・団体からの資金提供は続き、結果的に企業の影響力を排除することはできませんでした。
この点について、当時細川護熙首相の秘書官を務めていた成田憲彦・駿河台大学名誉教授も、「当時からこの問題は予見されていた」と振り返り、懸念されていた問題が実際に起きたことを指摘しました。
コメント: 0件
2025-03-19 13:28:45(先生の通信簿)
コメントを投稿することができます。管理者の確認後公開されます。誹謗中傷・公序良俗に反する投稿は削除されます。
人気のある活動報告
-
1位
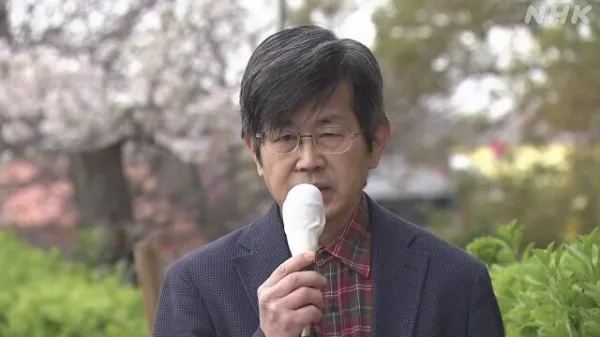 岸和田市長選挙:上妻敬二氏「未来を見据えた資産形成」提案 (上妻敬二)
岸和田市長選挙:上妻敬二氏「未来を見据えた資産形成」提案 (上妻敬二)
-
2位
 空襲被害者への給付金と謝罪求める大椿議員の質疑 (大椿ゆうこ)
空襲被害者への給付金と謝罪求める大椿議員の質疑 (大椿ゆうこ)
-
3位
 岸田首相、牡蠣養殖議員連盟の立ち上げを発表 産業発展に向けて積極的な取り組みを宣言 (岸田文雄)
岸田首相、牡蠣養殖議員連盟の立ち上げを発表 産業発展に向けて積極的な取り組みを宣言 (岸田文雄)
-
4位
 金沢市に尹奉吉テロリスト記念館開設計画 反対運動激化で地域社会に混乱 (村山卓)
金沢市に尹奉吉テロリスト記念館開設計画 反対運動激化で地域社会に混乱 (村山卓)
-
5位
 道路法改正案可決、太陽光パネル設置促進に反対する保守党の警鐘 (島田洋一)
道路法改正案可決、太陽光パネル設置促進に反対する保守党の警鐘 (島田洋一)
-
6位
 「切らんでええカードを切り過ぎた」―高市早苗氏、石破首相の対米交渉に疑問視 (高市早苗)
「切らんでええカードを切り過ぎた」―高市早苗氏、石破首相の対米交渉に疑問視 (高市早苗)
-
7位
 維新、神奈川4区支部長辞退 加藤千華氏「一身上の都合」 (加藤千華)
維新、神奈川4区支部長辞退 加藤千華氏「一身上の都合」 (加藤千華)
-
8位
 伊藤辰夫氏、自民党離党し国民民主党から参院選出馬へ (伊藤辰夫)
伊藤辰夫氏、自民党離党し国民民主党から参院選出馬へ (伊藤辰夫)
-
9位
 【岸和田市長選】花野眞典氏が無所属で立候補表明、「新しい風を吹かせる」 (花野眞典)
【岸和田市長選】花野眞典氏が無所属で立候補表明、「新しい風を吹かせる」 (花野眞典)
-
10位
 【大阪万博開幕直前の混乱】 パビリオン未完成、空飛ぶクルマ展示断念、チケット販売低迷で不安募る (吉村洋文)
【大阪万博開幕直前の混乱】 パビリオン未完成、空飛ぶクルマ展示断念、チケット販売低迷で不安募る (吉村洋文)
オススメ書籍
塩川鉄也
新着記事
- 2025-04-03
- 2025-04-02
- 2025-04-02
- 2025-04-02
- 2025-04-01
- 2025-04-01
- 2025-04-01
- 2025-03-31
- 2025-03-31
- 2025-03-31
「先生の通信簿」は、議員や首長など政治家の公約・政策を「みんなで」まとめるサイトです。また、公約・政策に対しては、進捗度・達成度などを含めたご意見・評価を投稿することができます。
政治家や議員の方は、公約・政策を登録し有権者にアピールすることができます。また、日頃の活動報告も登録することができます。
選挙の際に各政治家の公約達成度や実行力など参考になれば幸いです。
※この情報は当サイトのユーザーによって書き込まれた内容になります。正確で詳しい情報は各政治家・政党のサイトなどでご確認ください。



