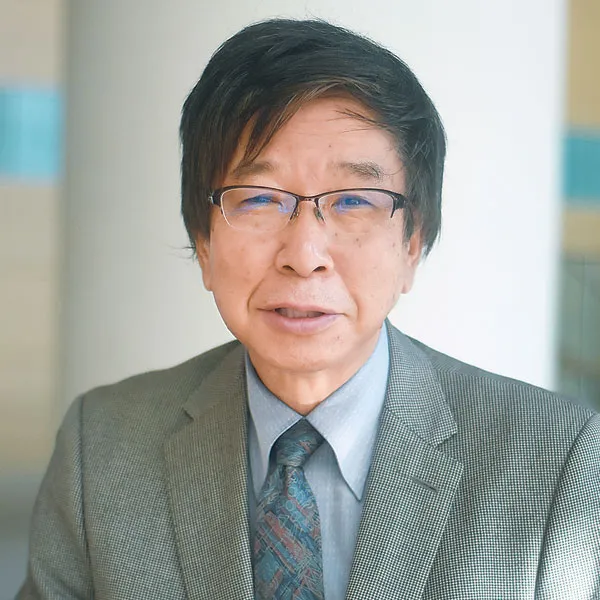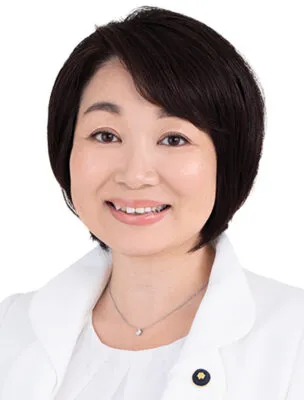2025-08-06 コメント: 2件 ▼
公約実質賃金6カ月連続マイナス 夏のボーナスでも物価高に勝てず「実感なき賃上げ」続く
昨年は6月にボーナスの支給効果で一時的に実質賃金がプラスへ転じていたが、今年は物価高に押しつぶされ、支給月にもかかわらずマイナスとなった。 しかしながら、「収入が増えても出ていく金のほうが多い」「物価が上がりすぎて、ボーナスのありがたみがない」といった声が現実を物語っている。
実質賃金は6カ月連続のマイナス 今年の夏も生活にゆとりなし
厚生労働省が8月6日に公表した毎月勤労統計調査(6月分速報値)によれば、物価の変動を反映した実質賃金は前年同月比で1.3%の減少となった。減少は今年1月から6カ月連続。昨年は6月にボーナスの支給効果で一時的に実質賃金がプラスへ転じていたが、今年は物価高に押しつぶされ、支給月にもかかわらずマイナスとなった。
6月は例年、夏のボーナスが支給される企業が多く、賃金の増加が期待される時期だ。しかしながら、「収入が増えても出ていく金のほうが多い」「物価が上がりすぎて、ボーナスのありがたみがない」といった声が現実を物語っている。
現金給与総額は増加でも、物価上昇がそれを帳消し
名目ベースの現金給与総額は51万1210円と前年同月比で2.5%増加。これで42カ月連続のプラスとなった。賃上げの動きが進んでいる企業もあり、ボーナス額そのものは増加している。
しかし同時に、生活を直撃する消費者物価指数(CPI)は3.8%の上昇。食品や日用品、光熱費など、日々の暮らしに欠かせない項目の多くが値上がりしており、賃上げ以上に家計への圧力が強まっている。結果、物価上昇に実質賃金が追いつかず、家計の購買力は低下したままだ。
ネットでは「これで実質賃金が上がっているとか言わないでほしい」「数字だけ上がっても生活は苦しいまま」「名目だけの“見せかけ”賃上げ」と、現場感覚と政府発表のギャップに不信感を抱く声が相次いでいる。
昨年との違い ボーナス効果が物価に負ける
昨年2024年6月は、ボーナス支給額の伸びが4.5%に達し、物価上昇率(3.3%)を上回ったことで、実質賃金は1.1%のプラスとなった。年末の冬のボーナス時期でも同様の傾向がみられ、一時的とはいえ、物価高をカバーする成果が出ていた。
だが、2025年は状況が異なる。物価上昇が持続し、エネルギー価格や食料品価格の高止まりに加え、輸入品への円安影響も強く出ている。一方で、賃上げ率は鈍化しはじめており、従業員5人以上の事業所のボーナス水準が生活費の膨張に追いつかない。
「夏のボーナスが出ても、結局それで生活費がギリギリ」「去年は少しゆとりができたけど、今年は無理」といった声が現場からは聞こえてくる。
“実感なき賃上げ”が続く構造的要因
この「実感なき賃上げ」の背景には、構造的な問題がある。物価が継続的に上昇しているのはエネルギーや食料品、物流費などのコストが上がっているためで、企業の収益を圧迫する。その結果、賃上げ余力が乏しい中小企業は昇給に慎重にならざるを得ない。
また、定期昇給やベースアップを実施した企業でも、昇給分がそのまま物価上昇に吸収されてしまう現状では、手取りの実質価値はほとんど変わらない。加えて、インボイス制度や社会保険料の負担増など、家計の支出をじわじわと圧迫する要素も無視できない。
「賃上げしたって、税や保険料で差し引かれたら手取りは変わらない」「インボイス廃止してくれたほうがよほど実感ある」といった指摘も多い。
「経済対策」は給付金ではなく、抜本的な減税を
この実質賃金の低下傾向を受けて、政府の経済対策に対する批判も強まっている。石破政権は、一定の物価高対策としてエネルギー補助や給付金を打ち出しているが、それが生活者の安心に直結しているかといえば疑問符がつく。
「減税をやってくれた方がよほど助かる」「給付金って結局一時しのぎ。長期的には意味がない」との声が多数。国民の不満が根強いのは、負担感の継続に加えて、政策の“その場しのぎ感”にある。
特に注目されているのは消費税減税や所得税の減税措置だが、現時点では抜本的な税制改革には至っていない。消費税が家計に与える影響の大きさを考えれば、構造的な対応が求められているのは明らかだ。
この投稿は石破茂の公約「物価上昇を上回る賃金の増加を実現」に関連する活動情報です。この公約は50点の得点で、公約偏差値55.3、達成率は0%と評価されています。
この投稿の石破茂の活動は、0点・活動偏差値42と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。