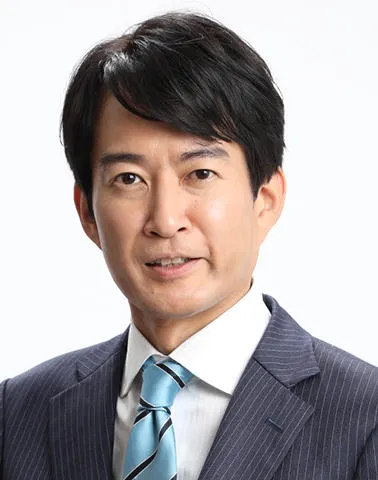2025-07-03 コメント投稿する ▼
石破政権の「プロミネンス・ルール」に潜む危険 NHK優遇と情報統制の可能性
石破政権下で進む放送制度改革 「プロミネンス・ルール」に潜む危うさ
石破茂首相のもと、自民党政権は放送分野における制度改革を進めている。その中心にあるのが「プロミネンス・ルール」の議論だ。一見、公共放送を目立たせるという公益性の高い制度に見えるが、その裏には政府の思惑と、情報統制の懸念が潜んでいる。
NHK優遇?「プロミネンス・ルール」の本質
自民党政権が設置した「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」は、これまで33回にわたり開催され、7月9日には第34回目を迎える予定だ。今回の議題は、「ヒアリング(産業としての放送)」と「プロミネンス制度に関する調査研究報告」だ。
このプロミネンス制度とは、欧州を参考に、公共放送など“公共の利益がある”とされる放送に優先的な表示やアクセスを保証するという仕組み。イギリスのBBCのように、ニュースの公正性や外部制作などが評価され、視聴者がまず接触しやすい位置に配置される。
一方で、日本での議論では、NHKのような放送事業者が優遇される可能性が高く、「政府の広報機関としての側面を強める危険性がある」との懸念も出ている。関西大学の准教授は「これはプロパガンダの温床になりかねない」と明確に警鐘を鳴らしている。
「プロミネンスという言葉の響きはきれいだが、中身は放送支配の装置にしか見えない」
「石破政権のメディア戦略、見えてきたのは情報統制の匂い」
「NHKがますます政府寄りになるのでは?本当に中立と言えるのか」
「公共性と政府の都合は別物。政治に都合のいい放送だけが目立つ時代が来るのか」
「若者はテレビを見ない。だから見せたい番組を前に押し出すって…戦時中みたいで怖い」
ソーシャルメディア批判も浮上 若者世代との断絶
会合では「不満や不信をあおるソーシャルメディアの側が変わるべき」との声も上がった。確かに誤情報や扇動的投稿は無視できない課題だ。しかし、これは放送側の正当化にも聞こえる。
特に、「放送事業者の役割は、若者が親しむSNSではなく、正確な情報源として放送コンテンツに導くべきだ」とする主張には、既存メディアによる“情報の選別”という姿勢が色濃く滲む。問題の本質は、テレビ離れそのものではなく、既存メディアへの信頼が崩れていることにある。
市民のメディアリテラシーが向上している今、視聴者は情報を見抜く力をつけている。にもかかわらず、視聴者の「疑う目」に対し“導く側”としての放送局が「正しい」とする姿勢は、時代錯誤と言わざるを得ない。
なぜ今、メディア改革なのか?
そもそも、なぜ石破政権はこのタイミングで放送制度改革を加速しているのか。そこには、政権運営におけるメディア活用の意図が透けて見える。物価高や減税論争、安全保障政策などで批判を浴びる中、メディアにおける「支持の下地づくり」が急務と考えているのではないか。
現実として、政権批判や異論がネットで多く見られるなか、既存放送局を優遇し、情報の出口を一定方向に絞る動きが始まれば、健全な民主主義に深刻な影を落とす。特定のコンテンツや報道が“公共性”という名目で優遇され、異論が「ノイズ」とされれば、それはまさに“統制メディア”への第一歩だ。
私たちは何を求めるべきか
メディアの自由は民主主義の根幹である。放送の役割は権力の監視であり、政府の味方になることではない。公共性の名の下で中立性を失えば、視聴者の信頼もまた失われるだろう。
石破政権には、放送制度の再構築を進めるにあたり、「視聴者のための公共性とは何か」「情報の多様性とは何か」を正面から議論し、開かれた制度設計を求めたい。