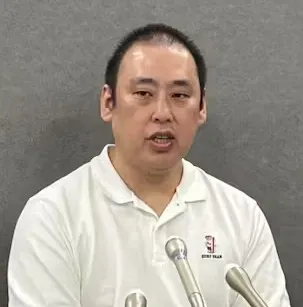2025-08-25 コメント投稿する ▼
公約最高裁「生活保護基準引き下げは違法」 自民党の公約が国民生活を貧しくした実態
最高裁が違法判断 自民党の「生活保護基準引き下げ」公約の罪
政府が実施した生活保護基準の1割引き下げが最高裁で「違法」と判断された。判断の焦点は行政手続きの不備に置かれ、基準の高低そのものについての判断ではなかったが、政策決定の背景にあった政治的思惑が改めて問われている。2012年衆院選で自民党が掲げた「生活保護基準の1割引き下げ」公約に沿う形で厚生労働省が調整を行った結果、国民生活に重大な影響を及ぼしたとみられている。
立教大学コミュニティ福祉学部の木下武徳教授は「なぜ引き下げ幅が10%だったのか。5%でも15%でもなく、まさに自民党の公約に合わせたとしか思えない」と語り、行政判断ではなく政治的な誘導があったと批判した。
「生活保護費を削っても財政は全く改善しない」
「結局はバッシングに便乗しただけだろう」
「国民の生活を豊かにするどころか、貧しくする公約だった」
「最低賃金の引き上げまで抑制する結果になりかねない」
「大企業の内部留保は600兆円もあるのに、困窮者を叩くのは筋違い」
ネット上ではこうした批判的な声が広がっている。
生活保護基準引き下げの波及効果
生活保護の基準は受給者だけに影響するわけではない。最低賃金や就学援助など、幅広い制度の基準点として利用されている。基準が引き下げられれば、最低賃金の上昇幅が抑えられ、社会全体の生活水準が低下する可能性がある。
木下教授は「国民の生活を守るための最低限度の基準が切り下げられれば、困っていない人にも影響が及ぶ。結果的に社会全体が貧しくなる」と指摘した。憲法25条2項が「国は国民生活の向上および増進に努めなければならない」と定めていることからすれば、今回の政策は明らかに逆行していたといえる。
生活保護バッシングと政治利用
2012年前後には「生活保護バッシング」が社会問題化していた。自民党はこれに便乗する形で「1割削減」を打ち出したが、木下教授は「財政改善のためではなく、国民の不満を生活保護利用者に向けるためだった」と指摘する。
実際、生活保護費の総額は社会保障費全体に占める割合から見てもごくわずかで、削減しても財政への影響は限定的だ。にもかかわらず削減が推し進められたのは、国民の不満をそらす政治的意図があったからに他ならない。
「生活保護を受ける人を悪者に仕立てるのは、いじめと同じ構図だ」
「国民同士を対立させて政治批判を逸らす思うつぼ」
「真に負担すべきは大企業や富裕層なのに、弱者に矛先を向けるのは卑怯」
こうした批判は、今回の最高裁判決を受けて一層強まっている。
自民党の政治姿勢と国民生活
企業の内部留保は600兆円を超えている一方、生活保護費の削減は財政改善にほとんど寄与しない。木下教授は「生活保護は一種の保険制度であり、困窮した時に誰もが利用できるセーフティーネットだ」と指摘し、政治がその価値を忘れていると警鐘を鳴らす。
生活保護利用者を「甘えている存在」と攻撃することで一時的に国民の不満を吸収し、政治への批判を避ける。この構図こそが自民党の「思うつぼ」だという。だが、それは結局、国民の生活水準全体を切り下げることにつながる。
最高裁が違法と断じた生活保護基準引き下げは、単なる行政手続きの瑕疵にとどまらず、政治が「国民の生活を豊かにする」という憲法の理念を忘れ、弱者を利用してきた実態を浮き彫りにした。生活保護は誰にとっても必要となり得る「社会の保険」であり、政治が本来向き合うべきは困窮者を攻撃することではなく、生活基盤の強化にある。今回の判決は、国民の暮らしを守る政治の責任を改めて問い直す契機といえる。
この投稿は石破茂の公約「生活保護や貧困対策は衣食住の現物支給」に関連する活動情報です。この公約は76点の得点で、公約偏差値67.7、達成率は0%と評価されています。