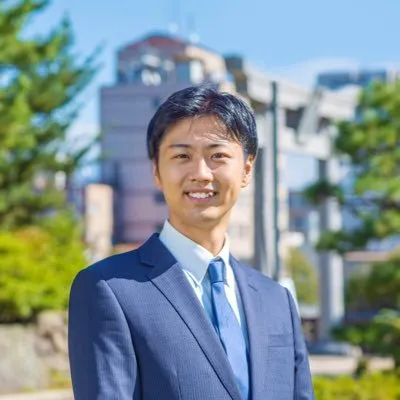2025-11-19 コメント投稿する ▼
中国が牛肉輸出協議を一方的中止、外交カードとしての経済制裁に日本は脱中国依存の検討急務
この協議中止は、中国が日本産水産物の輸入を事実上再停止したのと同じタイミングで発表されており、高市早苗首相氏の台湾有事に関する答弁への反発が背景にあるとみられています。
中国側意向で牛肉輸出協議が突如中止
日本産牛肉の対中輸出再開を巡る政府間協議が中国側の意向で中止となっていたことが2025年11月19日、明らかになりました。複数の政府関係者が報道機関に対して明かしたもので、24年ぶりの対中牛肉輸出再開への期待が高まる中での突然の方針転換となりました。
この協議中止は、中国が日本産水産物の輸入を事実上再停止したのと同じタイミングで発表されており、高市早苗首相氏の台湾有事に関する答弁への反発が背景にあるとみられています。日本産牛肉は2001年のBSE発生以来、中国による輸入禁止措置が続いており、2019年に禁止解除が発表されたものの、実際の輸出再開には至っていませんでした。
「また中国が勝手に協議をやめるのか。振り回されるのはもううんざりだ」
「日本の農業が中国の機嫌次第で左右されるなんておかしい」
「外交カードとして使われる農産物。中国頼みは危険すぎる」
「ちゃぶ台返しのような国とまともな取引ができるわけがない」
「中国依存からの脱却を真剣に考える時期に来ている」
中国による外交カードとしての経済制裁
今回の協議中止は、中国が農産物や水産物を外交カードとして活用する典型的な事例です。中国は2010年以降だけでも、日本、韓国、オーストラリア、カナダなど10カ国以上に対して経済制裁や制限措置を発動しており、その手段は貿易制限、観光制限、投資規制など多岐にわたります。
中国の経済制裁は政治的目的を達成するための戦略的手段として位置づけられており、2017年の韓国に対するTHAAD配備を理由とした観光制裁、2020年のオーストラリアに対する新型コロナ調査要求への報復として大麦や石炭の輸入制限などが代表例です。これらの制裁は経済合理性ではなく、政治的な圧力をかける目的で実施されています。
日本も2010年の尖閣諸島問題を巡ってレアアース禁輸措置を受けた経験があります。今回の牛肉協議中止や水産物輸入再停止も、高市首相氏の発言に対する政治的圧力の一環とみられ、中国が経済関係を政治的交渉の道具として利用する姿勢は一貫しています。
予測困難な中国の一方的政策変更
中国の経済制裁や政策変更の最大の問題は、その予測困難性にあります。協議が進行中であっても、政治的な思惑により一方的に中止される可能性が常に存在します。これは通常の外交関係や商取引では考えられない不安定さです。
気に入らないことがあるたびにちゃぶ台をひっくり返すような行動パターンでは、長期的な信頼関係の構築は不可能です。日本の畜産業界にとって、中国市場への期待は大きいものの、このような政治的リスクを常に抱えながらのビジネス展開は極めて困難と言わざるを得ません。
中国の政策決定プロセスは透明性を欠き、法の支配よりも政治的判断が優先される傾向があります。このため日本企業や生産者は、投資や設備拡張の判断を下すことが困難になり、結果として経済活動全体の効率性が損なわれることになります。
中国依存からの脱却が急務
このような中国の一方的な態度を踏まえると、日本は中国依存の貿易・生活構造を根本的に見直すべき時期に来ています。サプライチェーンの脱中国化は既に世界的潮流となっており、日本企業も生産拠点の多元化や調達先の分散を進める必要があります。
農産物や水産物の輸出についても、中国一辺倒ではなく東南アジア、北米、欧州など複数市場への分散を図るべきです。特にベトナム、インド、タイなど成長市場への参入強化により、中国の政治的圧力に左右されない安定した輸出基盤の構築が重要になります。
移民・難民・外国人労働者についても法文化順守を徹底し、適切な法整備が必要です。法を犯して海外に逃げられる恐れがあり、それを排他主義と批判することは間違っています。日本の国益を守るため、毅然とした対応が求められています。