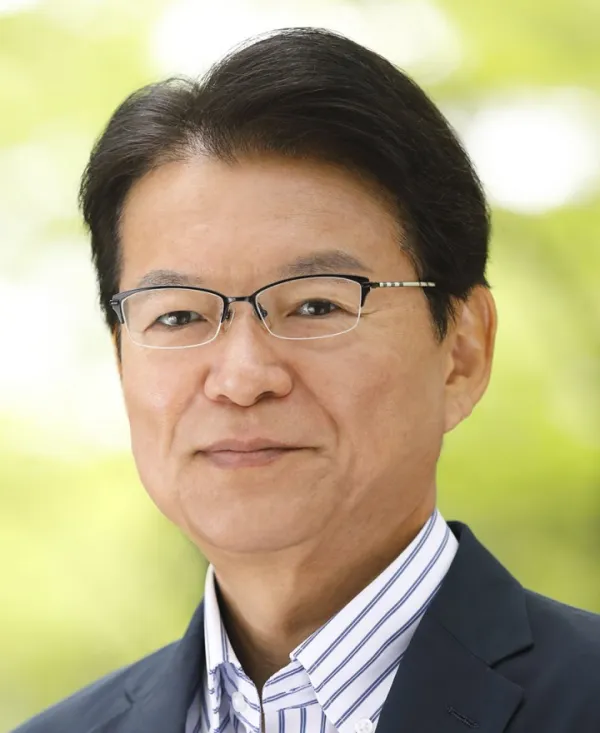2025-07-03 コメント投稿する ▼
神戸市が永久保存を決断 災害公文書の行方と他自治体との格差
阪神・淡路大震災から30年という節目を迎える神戸市では、震災関連の公文書を「永久保存」するための本格的な作業が進んでいる。 神戸市が震災記録を丁寧に保存している一方で、他の被災自治体では対応が分かれている。 仙台市では、震災から10年が経過した令和3年にガイドラインを策定し、がれき処理、遺体安置、復旧復興に関する文書を歴史的公文書として永久保存する方針を打ち出した。
神戸市が示す「震災公文書永久保存」の覚悟と他自治体の温度差
阪神・淡路大震災から30年、神戸市が記録を守る決断
阪神・淡路大震災から30年という節目を迎える神戸市では、震災関連の公文書を「永久保存」するための本格的な作業が進んでいる。避難所の報告や仮設住宅の記録など、市民と行政の格闘の跡が刻まれた膨大な文書が、市立小学校の空き教室などに分散して保管されてきた。
須磨区にある市立松尾小学校では、段ボールに詰められた1万3千点以上の資料が約1300箱分、5つの教室に積み上がっている。手書きの避難所日誌には《1月31日10時30分現在、避難場所で宿泊している人数はおよそ250名》《仮設トイレのくみ取りに来てほしい。全部満杯》など、当時の厳しい現場の声がそのまま残されている。
現在は簡易的な遮光や湿気対策が施されているが、空調もなく、資料にとっては決して万全とは言えない環境だ。このため神戸市は、来年6月に兵庫区に開館予定の市歴史公文書館に資料を移し、保存体制を抜本的に強化する。
同館では、公文書管理の専門職「アーキビスト」の資格を持つ職員が適切な温湿度環境のもとで管理を行い、これまで情報開示請求が必要だった資料も審査済みのものは即日閲覧が可能になる見通しだ。
市文書館の野口千晶館長は「震災の行政対応を知るための資料は、今の市民だけでなく将来世代にとっても重要。記録は過去を振り返るものではなく、未来への備えそのもの」と語る。平成11年、神戸市は震災関連資料の延長保存方針を打ち出し、平成22年には当時の市長が「永久保存」を明言。8年かけて3,700箱にまで選別・整理された記録群は、市の強い意思の表れだ。
「神戸の本気度に感動。これが行政の責任の取り方」
「あのとき何が起きたのか、次の世代に必ず伝えてほしい」
「保存場所が学校って……今までよく耐えてくれた」
「未来の被災地の命を救う記録になるかもしれない」
「こういう地味だけど重要な仕事にもっと注目を」
対照的な他自治体の対応と、広がる“保存格差”
神戸市が震災記録を丁寧に保存している一方で、他の被災自治体では対応が分かれている。とりわけ、未曽有の被害をもたらした東日本大震災に関する文書管理では、そのばらつきが顕著だ。
仙台市では、震災から10年が経過した令和3年にガイドラインを策定し、がれき処理、遺体安置、復旧復興に関する文書を歴史的公文書として永久保存する方針を打ち出した。令和5年に開館した市公文書館で資料の収集・保管が進められている。
福島県大熊町ではさらに踏み込んだ対応が取られた。震災の前後2年間(平成22〜23年度)の行政文書すべてを、震災に関係するか否かを問わず永久保存することを決定。原発事故という特殊な事情を背景に「すべてが記録」との考え方を徹底した。
だが、すべての自治体が同じような対応をしているわけではない。岩手県大槌町では、震災発生時の初動を検証するために職員から集められた聞き取りメモが、明確な定義のないまま廃棄されていたことが平成30年に判明。町はその後、公文書管理条例を制定し、再発防止に取り組んでいるが、失われた記録は戻らない。
「震災記録は全国の教訓」でも統一ルールなし
平成30年、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会が東日本大震災の被災自治体に実施したアンケートでは、173自治体のうち57%が「保存年限を特に意識していない」と回答。「廃棄する」とした自治体も33%に上っていた。災害という非常時に生まれた記録が、その重要性に見合う扱いを受けていない現状が浮かび上がる。
筑波大学の白井哲哉教授は「公文書管理の意識は高まりつつあるが、隣同士の自治体で対応が全く違うという事態も珍しくない」と指摘する。「被災時の記録は、その地域のものだけでなく、将来の他地域にとっても貴重な教材になる。保存するかどうかは、被害を繰り返すかどうかの分かれ目」と語る。
「全国で保存基準を統一してほしい」
「自治体に任せきりだと、また記録が失われる」
「大災害が来るたびにゼロから始めるの?」
「命に関わる記録が紙切れ扱いされてる現実」
「国が責任持つべきでは?」
“記録”を軽視する国でいいのか
震災後、真っ先に交付されるのは支援金や補助金だが、それらがどこに、どのように使われたかを検証するには、公文書の存在が不可欠だ。記録を残すことは、過去の過ちや成功を正しく把握し、次の災害で生かすための最低限の備えである。
「給付金は一時しのぎに過ぎない」「制度の効果があったのかは記録を見なければ分からない」。こうした声が震災のたびに繰り返されてきた。だが、その“記録”が失われていれば、いかなる反省も意味をなさない。
本来、公文書の保存は国が関与してもよい重要事項だ。スパイ防止法の議論と同じく、公的情報の管理には国家的な意識が求められる。災害はいつか、どこかで必ず起きる。だからこそ、行政の動きを残す仕組みが全国的に必要だ。
神戸市の取り組みは、「公文書は過去ではなく未来への希望」であることを証明している。他の自治体、そして政府も、この姿勢に学ぶべき時だ。