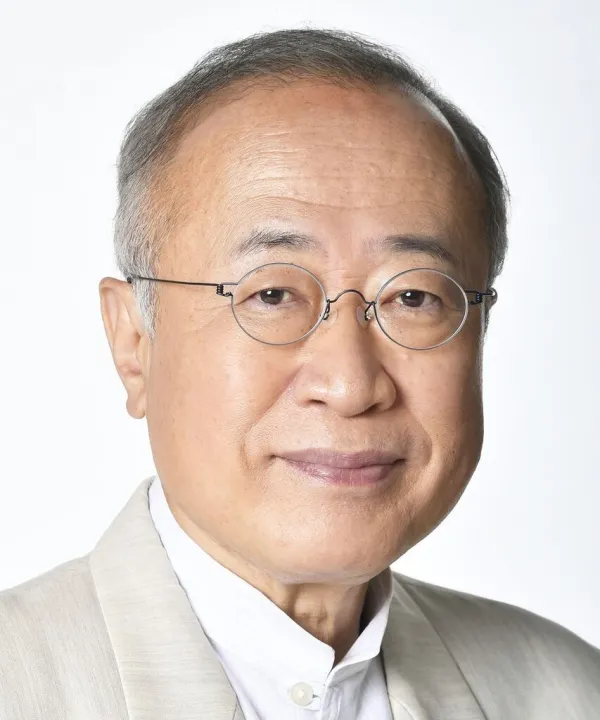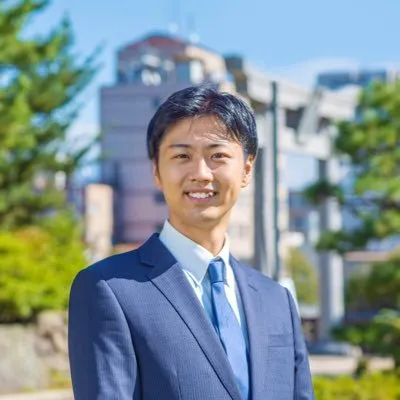2025-03-13 コメント投稿する ▼
佐原若子議員、修学支援法の課題を指摘—中間層・多子世帯への支援拡充を求める
この点について、文部科学省は家計全体で負担軽減を図るためという理由で、支援対象を3人以上の子どもを持つ世帯に絞ったと説明していますが、佐原議員は、このような措置が教育費や子育て費用で理想的な子供の数を断念させる原因になっているのではないかと疑問を呈しました。
議員はまた、多子世帯に対する支援に関しても懸念を示しています。具体的には、1人目の子どもが就職すると、残りの子どもが支援対象外になる可能性があり、これが不公平だと問題提起しています。この点について、文部科学省は家計全体で負担軽減を図るためという理由で、支援対象を3人以上の子どもを持つ世帯に絞ったと説明していますが、佐原議員は、このような措置が教育費や子育て費用で理想的な子供の数を断念させる原因になっているのではないかと疑問を呈しました。
さらに、佐原議員は、文部科学省が支援対象を細かく区切る背景に、財務省の緊縮財政主義が影響しているのではないかと指摘し、大学無償化を実現するための最大の障害は財務省だと問いかけました。
日本の高等教育の公的支援について
議員は、日本の高等教育に対する公的支援がOECD平均に比べて低いことを問題視しており、これが家計の負担を増大させている原因だとしています。特に、貸与型奨学金の債務免除が、実質的に大学無償化に近い効果を持つとして、異常な取り立てはすぐに止めるべきだと訴えました。
また、佐原議員は、教育分野に対して積極的な財政支援が必要であり、その財源として国による通貨発行や国債発行を挙げています。この点について、財務省の姿勢に疑問を持っているようです。
政府の対応と今後の課題
これに対して、文部科学大臣安倍俊子氏は、高等教育の修学支援新制度の対象として、令和7年度予算案で約84万人を見込んでおり、支援対象は高等教育機関の在籍者の約22%に相当すると説明しました。また、多子世帯への支援対象を3人以上に絞った理由については、教育費や子育て費用のために理想の子供数を断念する家庭が多いためとしています。
一方、財務大臣加藤克信氏は、教育の重要性を認めつつも、教育費の財源を国債発行でまかなうことについては慎重に検討する必要があるとの立場を示しました。
佐原議員の主張は、修学支援法が低所得者層には恩恵をもたらしている一方で、中間層や多子世帯には不十分な支援が提供されている現状を浮き彫りにしています。今後、支援の対象をどう広げ、どう財源を確保していくかが大きな課題となるでしょう。