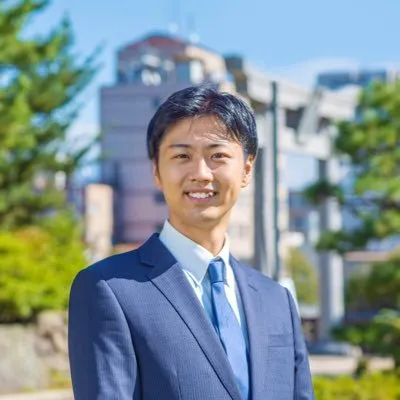2025-08-27 コメント投稿する ▼
政府、使用済み太陽光パネル再利用義務化を断念 費用負担決まらず不法投棄懸念
政府が検討してきた使用済み太陽光パネルのリサイクル義務化は、最終的に見送られる方向となった。 背景には「リサイクル費用を誰が負担するのか」という根本的な整理がつかなかったことがある。 欧州では拡大生産者責任(EPR)の考え方に基づき、製造業者にリサイクル費用の負担を義務付ける仕組みが既に導入されている。
政府、使用済み太陽光パネル再利用義務化を断念
政府が検討してきた使用済み太陽光パネルのリサイクル義務化は、最終的に見送られる方向となった。背景には「リサイクル費用を誰が負担するのか」という根本的な整理がつかなかったことがある。当初は製造業者や輸入業者に負担を求める法案の準備が進められていたが、関係業界からの反発もあり、合意形成に至らなかった。
代替策は「報告義務化」
政府は代替策として、大規模発電事業者(メガソーラー事業者など)にリサイクルの実施状況を報告させる新制度を検討している。専門家会議で詳細を詰め、来年の通常国会に関連法案を提出する見通しだ。しかし、単なる報告義務では実効性に欠け、リサイクル率の向上につながるかは不透明との指摘も出ている。
大量廃棄の懸念と不法投棄リスク
太陽光パネルの寿命は20~30年とされ、廃棄量は2030年代後半から急増、2040年代前半には年間最大50万トンに達すると見込まれている。処分場の逼迫や不法投棄のリスクは高く、環境負荷が深刻化する恐れがある。
「再エネ推進の裏で廃棄物問題を置き去りにしている」
「泥舟連立政権の環境政策は場当たり的だ」
「義務化を断念ではなく、費用負担の仕組みを急ぐべき」
「不法投棄が増えれば結局税金で処理することになる」
「国民に負担を押し付けるのではなく、メーカー責任を明確化すべきだ」
SNS上ではこうした厳しい声が相次ぎ、政策の後退を懸念する意見が目立つ。
国際的な動向と日本の課題
欧州では拡大生産者責任(EPR)の考え方に基づき、製造業者にリサイクル費用の負担を義務付ける仕組みが既に導入されている。再生可能エネルギーを推進する一方で、そのライフサイクル全体に責任を持たせる仕組みを強化しているのだ。日本が今回、義務化を見送ったことは、国際的な取り組みとの格差を広げる懸念がある。
太陽光パネル廃棄問題と制度設計の行方
政府の方針転換は、再エネ推進の信頼性そのものを揺るがしかねない。コスト負担の在り方を先送りにすれば、廃棄の山が押し寄せる30年代後半以降に大きな社会問題化する恐れがある。必要なのは、費用負担の透明なルールと、不法投棄を防ぐための強制力ある制度だ。報告義務だけではなく、メーカー責任と国の監視体制を組み合わせた仕組みづくりが急務である。
この投稿の石破茂の活動は、0点・活動偏差値42と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。