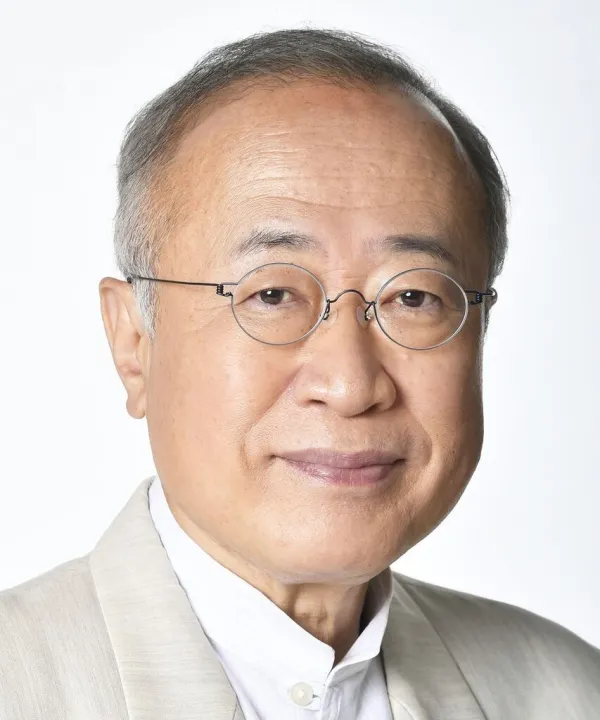2025-08-20 コメント投稿する ▼
公約南海トラフ巨大地震「警戒」で52万人事前避難対象、高齢者中心に課題山積
対象者の半数以上は高齢者や障害者など要配慮者であり、避難の実効性が課題となっている。 南海トラフ地震は、発生からわずか数分で津波が到達する地域もあるため、国は市町村に対し「事前避難対象地域」を指定するよう求めてきた。 特に標高が海面より低い「海抜ゼロメートル地帯」を指定する自治体が増えており、住民にとって避難は喫緊の課題となっている。
南海トラフ巨大地震、「警戒」発令時の事前避難対象52万人超
国の初調査によると、南海トラフ地震臨時情報のうち最も切迫性が高い「巨大地震警戒」が発表された場合、全国で約52万人超が事前避難の対象になることが明らかになった。対象者の半数以上は高齢者や障害者など要配慮者であり、避難の実効性が課題となっている。
南海トラフ地震は、発生からわずか数分で津波が到達する地域もあるため、国は市町村に対し「事前避難対象地域」を指定するよう求めてきた。今回の調査で、千葉から鹿児島にかけての16都県130市町村がすでに指定を行っており、対象は全住民約24万5600人、要配慮者約27万4800人に上ることがわかった。
「わずか1週間前に避難を求められても現実的に動けるのか不安だ」
「高齢者や障害者の移動は行政の支援なしでは難しい」
「海抜ゼロメートル地帯の住民が対象になるのは当然だと思う」
「避難所不足が深刻、受け入れ態勢を国が整えるべき」
「人数を数えて終わりでなく、避難の費用を国が補助するべきだ」
調査の背景と地域別状況
昨年8月に宮崎県沖の日向灘地震を受けて「巨大地震注意」が初めて発表されたことを契機に、政府は今年6~8月に29都府県707市町村を対象に事前避難の指定状況を調査した。その結果、高知県が9万2100人で最も多く、宮崎県7万9900人、静岡県7万200人と続いた。
一部自治体では、津波被害に直結する海岸部だけでなく、土砂災害警戒区域や耐震性が不足する住宅地も指定している。特に標高が海面より低い「海抜ゼロメートル地帯」を指定する自治体が増えており、住民にとって避難は喫緊の課題となっている。
避難の課題と国の対応
自治体からは「避難所不足」「高齢者ら要配慮者の移動の困難さ」などの課題が指摘されている。これを受け、国は今年7月に改定した防災対策推進基本計画で、事前避難の方法を各自治体の推進計画に明示するよう求めた。また8月にはガイドラインを改定し、海抜ゼロメートル地帯を新たに事前避難の検討対象に追加した。
京都大学防災研究所の矢守克也教授は「国は単に人数を把握するだけでなく、事前避難にかかる費用補助など支援体制の強化が不可欠」と指摘する。行政の枠組みだけでは実効性に限界があり、地域住民や企業、ボランティアを含めた広域的な避難体制の構築が求められる。
今後の展望
今後、事前避難の対象地域や住民数はさらに増加する見込みであり、国や自治体は避難計画の実効性を高めるために財政支援や人員配置を強化する必要がある。南海トラフ巨大地震は「いつ発生してもおかしくない」とされるだけに、事前避難体制を整備し、特に高齢者や障害者を安全に移動させる仕組みづくりが急務だ。
日本社会にとって、南海トラフ地震への備えは単なる防災政策ではなく、国民の命を守る最優先課題である。国が率先して避難所の整備や支援体制の構築を進め、地域と共に現実的な避難の在り方を模索していく必要がある。
この投稿は石破茂の公約「来るべき巨大自然災害や風水害への対処を万全なものとします」に関連する活動情報です。この公約は29点の得点で、公約偏差値44.8、達成率は10%と評価されています。