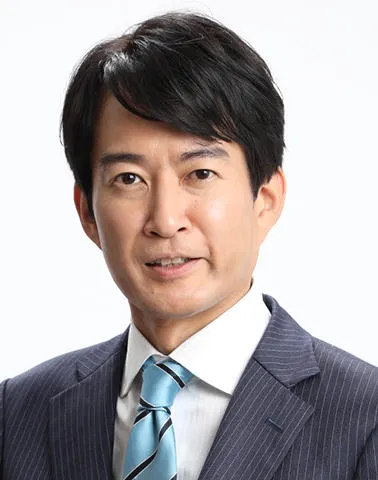2025-07-01 コメント: 1件 ▼
石破首相が米政策を大転換 「令和7年産から増産」表明も、田植えはすでに終了―現場の声は冷ややか
米価の安定化へ向けた「新たな米政策」始動
石破茂首相は1日、政府の「米の安定供給等実現関係閣僚会議」で、米の価格高騰を抑えるため、令和7年産(2025年秋収穫)からの増産に踏み切ると表明した。「不安なく増産に取り組める新たなコメ政策に転換する」との方針を打ち出し、これまでの抑制策からの方向転換に踏み込んだ。
首相は、「随意契約の導入や小売への直接売渡しを進めた結果、平均価格は3801円となり、3000円台に抑える成果が出ている」と成果を強調した上で、「小泉農水相には引き続き、米価の安定に全力で対応してほしい」と訴えた。
だが、こうした発言の裏で、現場の農家からは早くも「期待よりも疑念」の声が上がっている。
田植えはすでに終了、「増産」と言われても現場は動けない
首相が「今年産からの増産」と明言したにもかかわらず、すでに全国の田植えは6月時点でほぼ終了している。現実的に「今から増産に転じる」というのは不可能に近く、農家の中には「言葉だけが先行している」と困惑する声もある。
「田植えが終わってるのに今年増産って、どうやって?何の説明もない」
「現場のスケジュール感を全く理解してない政治判断にしか見えない」
「今さら増産と言われても肥料も資材も高騰してて、動ける余裕はない」
「結局、数字だけいじって“やってます感”を演出してるだけじゃないの?」
「来年の話ならまだ分かる。今年のことなら、もう手遅れです」
田植えは春から初夏にかけて一気に行われ、7月には生育期に入る。いくら「増産」と言われても、今から面積を増やすことは現実的ではない。政策と現場の時間軸がずれていることに、多くの関係者が戸惑っている。
農業関係者からは「今年産に関しては、増産という言葉より、実際の収量をどう最大化するか、収穫後の買い取りや価格調整策を具体的に示すべきだった」という声も出ている。
構造の見直しと統計の修正へ
一方で、石破首相は価格高騰の背景を「構造的課題」としても指摘。流通経路の偏り、作況指数の制度疲労など、過去の統計と実態のズレを認め、「作況指数の廃止」「収穫量の把握方法の見直し」「流通の可視化」など、農政の根本的な制度改革にも着手する構えを見せた。
これまでの統計が「需要減・過剰供給」といった旧来の前提に引きずられていた可能性もあり、それが意図せず価格操作や不公平な市場形成につながっていたとの見方もある。
「数字いじってコントロールする時代はもう終わりにしてほしい」
「農業は生活の根幹、株式みたいに“操作”していい分野じゃない」
価格統制の陰で損をしたのは消費者だけではなく、誠実に生産を続けてきた農家も同様だった。
増産政策の行方と問われる政権の真意
今回の表明を受けて、政権は「新たな米政策」へ本格的に舵を切るとするが、現場の不信感は根強い。米の消費量が年々減少している中、単純な増産が果たして正解なのか、それとも新たな過剰在庫を生むのかという議論も始まっている。
さらに、農政全体に広がる問題として「実需との乖離」もある。消費の多様化やパン・麺類などの台頭により、コメの需要は毎年1%程度減っている。増産が単なる数量の上乗せでしかない場合、それはまた新たな価格崩壊を呼ぶ“負のループ”を生む危険すらある。
石破政権が目指すのは、あくまで「適正な備蓄」「安定価格」「農家所得の確保」の三本柱による安定政策。だが、その実現には、場当たり的な表明ではなく、現場との連携、制度の持続性、そして市場への信頼回復が不可欠だ。
米価政策の信頼回復なるか
コメは単なる農産物ではない。国民の主食であり、日本の文化であり、食卓の中心にある存在だ。その米が「高くて買えない」「作っても儲からない」と言われるようでは、国の食料安全保障など絵に描いた餅にすぎない。
今回の政策転換が、過去の農政失策を乗り越える一歩になるのか、それともまたしても机上の空論で終わるのか。石破政権の“本気度”が問われている。