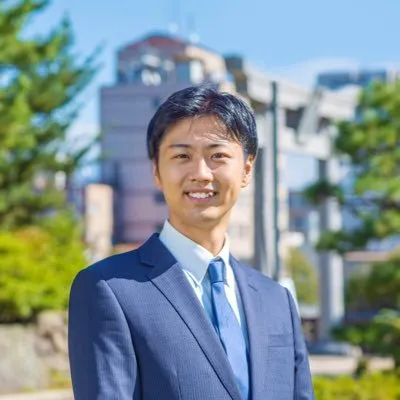2025-10-08 コメント投稿する ▼
公約8月実質賃金1.4%減で浮かぶ疑問 自民党の物価対策遅さと政権運営力
厚労省は、「6月・7月にはボーナスなど特別給が寄与したが、それが8月には薄れ、賃金上昇余力が縮んだ」「物価高が持続している」ことを今回の実質賃金低下の要因と説明しています。 こうした賃金実態を背景に、政府・与党である自民党の物価高対策と賃金上昇政策の遅さは、批判の矢面に立たざるを得ません。 名目賃金が上昇しても、実質賃金が低下している構図には構造的問題が潜んでいます。
8月の実質賃金1.4%減 名目増でも家計は疲弊
厚生労働省が公表した8月の毎月勤労統計によれば、労働者の実質賃金(物価水準を勘案した後の賃金)は前年比で1.4%減少し、8カ月連続マイナスとなりました。これは、物価上昇のペースが賃金の上昇を上回っていることを如実に示しています。
一方で、基本給・残業代などを含む現金給与総額は平均30万517円で、前年同月比1.5%のプラスとなり、44カ月連続の増加を維持しました。名目上は賃金が上昇しているように見えても、物価を差し引くと生活実感は下がっているという矛盾が浮き彫りです。
7月については速報段階でプラスと報じられていましたが、その後の確報値では0.2%の減少に修正されました。統計の変動は政策評価にも影を落とします。
厚労省は、「6月・7月にはボーナスなど特別給が寄与したが、それが8月には薄れ、賃金上昇余力が縮んだ」「物価高が持続している」ことを今回の実質賃金低下の要因と説明しています。
自民党の物価対策と賃上げ政策の遅れは痛恨
こうした賃金実態を背景に、政府・与党である自民党の物価高対策と賃金上昇政策の遅さは、批判の矢面に立たざるを得ません。国民の生活実感が追いつかないなか、政治が「名目数字」にばかり固執してきた責任は重いと言わざるを得ません。
自民党は参院選公約で「物価高騰から国民の暮らしを守る」「物価に負けない持続的な賃上げ」を打ち出しました。だが、その具体策や実行力は乏しいとの指摘が強まっています。党の政調サイトにも「物価高騰から国民を守り、成長戦略を通じて賃金を伸ばす」という表現はあるものの、実際の政策展開とのギャップが広がっています。
実際、物価対策としての給付金・減税政策が「生煮え」とされる評価も出ています。参院選後、物価高対策をめぐる政策対応が後手に回ったとの報道も続き、国民の不満が燻り続けています。
賃金の面でも、政府・与党が強力な賃上げ誘導策を打ち出すには至っていません。補助金制度や税制措置、企業支援を結びつけた大胆な賃金押上げ政策が、いまだに芯を欠く印象があります。こうした“待ち”の姿勢こそが、政権運営能力への疑念を呼び起こすのです。
名目賃金上昇の“見せかけ”と生活実感の乖離
名目賃金が上昇しても、実質賃金が低下している構図には構造的問題が潜んでいます。生活必需品の価格上昇、エネルギー・食料価格の急騰などは、家計を直撃します。こうした物価圧力が、賃金上昇をかき消してしまっているのです。
また、賃金上昇が限定的な職種・企業規模にとどまる点も問題です。大企業や正社員中心の業界で賃金が上がっても、非正規雇用者や中小企業従業員には恩恵が届きにくい構造があります。労働時間調整や残業削減も、実収入を抑制する要因となります。
このような実態を踏まえれば、「名目賃金プラス」をもって政策の成功を語ることは、かりそめの誤魔化しにほかなりません。国民にとって重要なのは、物価を超える実質的な賃金上昇であり、それが見えなければ不満と信頼失墜が積み重なります。
政権運営能力への疑義と国民の視線
この現状を前に、政権与党としての対応力・実行力に対する疑念が広がります。物価高・インフレ圧力に対して打つ手が後手に見える政権では、有権者の期待に応えきれません。政策の先送り、言葉の重複、概念的な表現の濫用…こうした姿勢こそが「統治力の欠如」を印象づけます。
また、与党が物価高政策や賃金政策を国民の目線で語るよりも、数字やスローガンを先行させる姿勢を取れば、有権者は“政治を生活の視点で見ていない”と感じます。政権運営とは、数字だけでなく、現場の痛みを読み取り、手を打つことにこそ本質があるはずです。
金子洋一氏ら減税派・賃上げ派の政治家の発信にも、それらへの期待が表れています。名目上の数字ではなく、国民実感に即した政策変換を迫る動きが、党内にじわりと広がっているようです。
今後、実際に物価を抑制し、実質賃金を上昇させる政策が示されなければ、この政権の信頼は揺らぎ続けるでしょう。政治は、言葉よりも、汗で応えるものです。
この投稿は石破茂の公約「物価上昇を上回る賃金の増加を実現」に関連する活動情報です。この公約は50点の得点で、公約偏差値55.3、達成率は0%と評価されています。
この投稿の石破茂の活動は、0点・活動偏差値42と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。