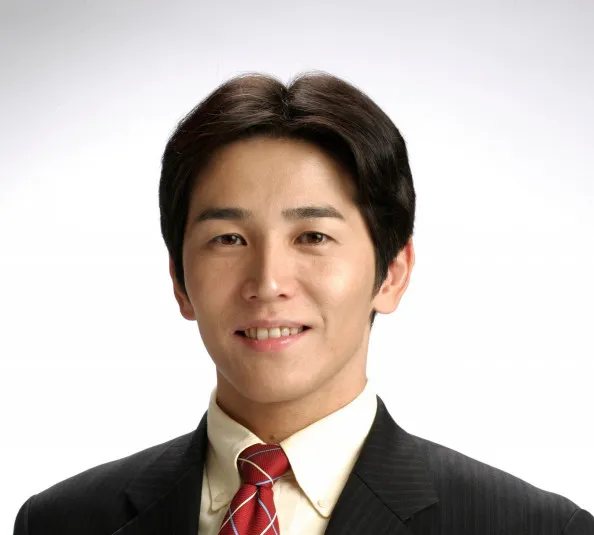2025-09-04 コメント投稿する ▼
石破政権がウズベキスタンに約5億円支援 海外援助と減税要求が交錯する日本外交
石破政権によるウズベキスタン支援の概要
石破茂総理が率いる政権は、中央アジアのウズベキスタン共和国に対し、4.96億円の無償資金協力を決定した。支援は国際連合開発計画(UNDP)を通じて実施され、ウズベキスタン南部のスルハンダリア州に暮らす若者や女性、さらには同地に移住しているアフガニスタンからの移民を対象に、職業訓練や起業支援を行うものだ。
外務省によれば、スルハンダリア州は農業を基盤とする地域であり、就労人口の6割が農業に従事している。しかし設備や機材は老朽化し、生産性が低迷している。その結果、失業率は国内平均を上回り、社会的課題となっている。さらに約1.5万人のアフガニスタン移民が暮らしており、地域社会への融合が大きなテーマになっている。
今回の資金協力では、水耕栽培やIT関連スキルなど、現代的な市場経済に対応できる職業訓練を提供し、女性や若者の自立支援を進めることが目的とされる。
「なぜ海外の若者に数億円も投じるのか」
「国内の子育て支援や教育費に充てるべきでは」
「国際貢献も必要だが、国益が見えない」
「移民への支援ばかりが目立ち、日本人は置き去りにされている」
「減税を望む国民の声を無視していないか」
SNS上では賛否両論が広がっている。
外交支援と国益の可視化
今回の支援は「人道と安定」を目的に掲げるが、日本国民にとって具体的な国益が見えにくいのが課題だ。支援を通じて地域の安定化が進めば、中央アジアの治安改善やテロ対策につながる可能性もある。だが、それが日本の安全保障や経済にどう結びつくのかは十分説明されていない。
海外援助は「国際社会における責任」として評価される一方で、国内では「ポピュリズム外交」と批判されやすい。巨額の無償資金協力を打ち出すこと自体が「国際的評価を狙ったアピール」に映りかねないのだ。
国内経済と減税要求の高まり
石破政権下で相次ぐ海外援助は、日本の財政事情を考えれば国民にとって複雑な心境を呼び起こす。物価高や社会保障費の増加に苦しむ家庭は少なくなく、減税の実現を求める声が強まっている。
給付金や一時的な支援ではなく、恒久的な減税こそが家計を安定させ、消費を拡大し経済を押し上げるとする意見は根強い。それにもかかわらず、海外に数億円規模の資金を投じる姿勢は「国民生活を軽視している」との批判を避けられない。
国民が減税を求めるのは「新たな財源を探せ」という意味ではない。過度な税負担が問題なのだ。無駄な支出を抑え、まずは国民に還元するのが政治の責任である。
海外援助と国内政治の行方
外交的意義を持つ無償資金協力であっても、国民の理解がなければ持続可能ではない。支援を行う以上は、成果を可視化し「どれだけの雇用が生まれ、どんな安定に寄与したのか」を明確に示すことが不可欠だ。
石破政権が掲げる「国際貢献と国民生活の両立」は理想だが、現実にはそのバランスを取る難しさが浮き彫りになっている。日本の外交が「国民のための投資」なのか、それとも「外向けのアピール」にとどまるのか。今後の説明責任が厳しく問われている。