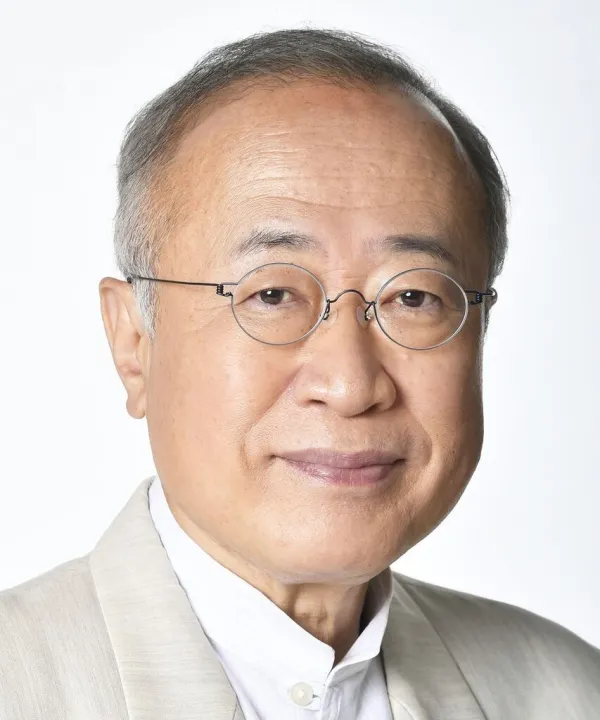2025-10-15 コメント投稿する ▼
長射程ミサイル用弾薬庫、全国62棟予算化も完成ゼロ、保安距離確保が課題
政府が進める長射程ミサイル配備に伴う弾薬庫建設計画で、2025年10月時点で全国62棟分の予算が計上されていることが防衛省への取材で分かりました。 防衛省は2027年度までに70棟を措置し、2032年度までに60棟を整備する方針ですが、火薬類取締法による保安距離の確保など、建設には多くの課題が残されています。
着工は14棟のみ、完成ゼロの現状
防衛省への取材によると、2025年10月時点で調査・設計を含む予算措置がとられているのは8道府県で計62棟です。しかし工事に着手したのは海上自衛隊大湊地区総監部(青森県)の2棟、陸上自衛隊祝園分屯地(京都府)の8棟、大分分屯地(大分県)の2棟の計14棟にとどまっています。
大分では最初の1棟を2025年内に、青森では2棟を2025年度中の完成を目指しています。祝園では8棟分の造成工事を行っており、2028年度末までの完成を目指しています。
防衛省が公表している工程表では、弾薬庫1棟あたり調査・設計に1から2年、工事に約2年かかります。2026年度予算案の概算要求では36棟分の工事費を計上しており、工期通りに進めば2028年度末時点で完成する弾薬庫は全国で40棟程度になるとみられます。
「弾薬庫が近くにできるのは不安です」
「安全性についてもっと説明してほしい」
「工事が進んでいないのはなぜだろう」
「保安距離は確保されているのか心配」
「住民への説明が不十分だと思います」
火薬類取締法による保安距離が課題
弾薬庫建設が容易でない最大の理由は、国内の軍事基地の多くが人口密集地に隣接しており、火薬類取締法に基づく保安距離がとれないことです。火薬の貯蔵量が多ければ多いほど保安距離をとる必要があります。
最大貯蔵量の40トンの場合には、住宅や学校、保育所などから550メートル離さなければなりません。防衛省は2020年、会計検査院から保安距離が不足していると指摘され、貯蔵する火薬量を減らすなど改善措置を余儀なくされています。
一方で防衛省は、保安距離を明らかにすれば弾薬量が分かるとして、個々の弾薬庫の保安距離を明らかにしていません。保管する弾薬の種類や量、弾薬庫の位置や壁の厚さまで明らかにしていないため、安全性への懸念から住民が説明を求める声が各地で上がっています。
国際条約との関係も議論に
住民からは、弾薬庫の安全基準が平時に民間の火薬を保管する火薬類取締法に基づいていることを疑問視する声も上がっています。
日本が2004年に加入したジュネーブ条約の第1追加議定書(1977年採択)第58条は、人口密集地やその近辺に軍事目標の設置を避けるよう求めています。国際赤十字は同条について「こうした配慮は平時からされるべきで、軍用装備や弾薬の倉庫を町の真ん中に建てるべきではない」と解説しています。
政府は、火薬類取締法に基づき保安距離を確保すれば問題ないとする立場です。しかし国際条約の解釈と国内法の運用をめぐっては、引き続き議論が必要とみられます。
長射程ミサイル配備計画の前倒し
政府は2025年8月、敵基地攻撃可能な長射程ミサイルの第1弾の配備計画を発表しました。射程を1000キロ程度に延ばす「12式地対艦誘導弾能力向上型」について、艦船から発射する「艦発型」と戦闘機から発射する「空発型」の運用開始を2028年度から2027年度に前倒ししました。
島しょ防衛用高速滑空弾も2026年度から2025年度に前倒しして運用開始するとしています。ミサイルの量産に伴い、それを保管する弾薬庫の整備が喫緊の課題となっています。
九州・沖縄を中心に、長射程ミサイル配備や弾薬庫新設が進むことに対し、各地で反対する市民団体が発足しています。2025年2月には全国組織「戦争止めよう!沖縄・西日本ネットワーク」が結成され、要請や署名活動を広げています。
弾薬庫建設をめぐっては、安全性の確保、住民への説明、国際条約との整合性など、多くの課題が残されており、今後の動向が注目されます。