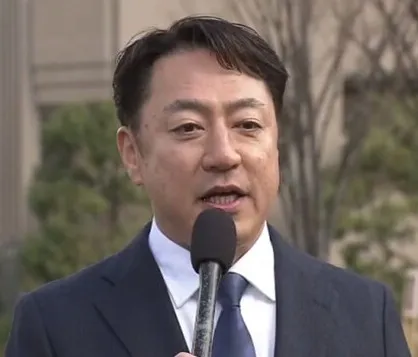2025-07-30 コメント投稿する ▼
国交省が8年ぶりに渇水対策本部設置 鳴子ダムは貯水率0%、新潟・東北で取水制限相次ぐ
国土交通省は7月30日、新潟県や東北地方で深刻化する渇水被害への対応強化のため、中央渇水対策本部を設置した。 国交省によると、28日時点で全国14水系17河川が渇水対策の特別態勢に入っており、特に宮城県の鳴子ダムは貯水率0%と“空のダム”となっている。 新潟県では、すでに上越市が渇水対策統括本部を設置し、市民に節水を呼びかけている。
国交省が8年ぶりに渇水対策本部を設置 新潟・東北でダム枯渇、生活・農業に深刻影響
国土交通省は7月30日、新潟県や東北地方で深刻化する渇水被害への対応強化のため、中央渇水対策本部を設置した。本省に本部を置くのは、2017年以来8年ぶり。記録的な少雨と猛暑の影響で、複数のダムで貯水量が著しく低下しており、一部の河川ではすでに農業用水などの取水制限が実施されている。
被害は広範囲に及び、市民生活や農業・工業用水にも影響が出始めている。政府は今後、関係自治体や関係省庁と連携して、節水呼びかけや支援策を強化する方針だ。
14水系17河川で取水制限 ダムが“空”の状態に
国交省によると、28日時点で全国14水系17河川が渇水対策の特別態勢に入っており、特に宮城県の鳴子ダムは貯水率0%と“空のダム”となっている。新潟県の正善寺ダムも13%と、極端な水不足が続く。
今後さらに少雨が続けば、農業用水の安定供給はもちろん、工業用水や生活用水にも制約が生じかねない状況だ。
「まさかダムが0%になるとは…異常事態すぎる」
「農業だけでなく、生活にも影響出るレベル」
「政府の反応が遅い。もっと早く動くべきだった」
「これ気候変動の影響なんじゃ?」
「災害並みの渇水だと思う。補償や支援を急いで」
SNS上でも、危機感を訴える市民の声や、対策の遅れに対する批判が広がっている。
取水制限の波紋 農業・自治体の対応は限界に
新潟県では、すでに上越市が渇水対策統括本部を設置し、市民に節水を呼びかけている。農業関係者からは「苗が育たない」「予定していた作付けができない」といった深刻な声が上がり、作物の品質や収量への影響は避けられない状況となっている。
宮城県や福島県などでも、田んぼへの給水を巡って地域ごとに制限ルールが設けられ、一部では夜間の断水や給水制限も検討されているという。
8年ぶりの本省設置 “災害級”の渇水に政府も危機感
国交省が本省に渇水対策本部を設けるのは、2017年の西日本の渇水以来。今回は、地域の限定的な被害ではなく、東北・新潟一帯の広範囲にわたってダムが枯渇し、事実上“災害級”の事態として対応に乗り出した。
政府は今後、各水系ごとの渇水リスク評価を進めるとともに、農業被害や取水制限による影響への支援措置を検討するとしている。
また、気候変動による異常気象との関連性についても、気象庁・環境省などと連携して情報分析を進める見通しだ。
気候変動と水資源管理 制度的見直しの議論も
今回の渇水被害を受け、専門家の間では中長期的な水資源政策の再構築を求める声も高まっている。これまでの「治水中心」「渇水は想定外」という方針では、極端な気象リスクへの対応が不十分だという指摘もある。
都市部でも「節水対策」「雨水貯留施設の強化」「ダム再運用」の検討が進められつつあり、今後は水インフラと気候レジリエンスの強化が政策課題として浮上する可能性が高い。