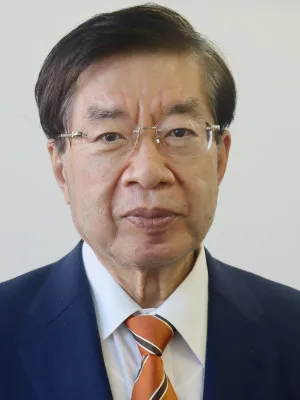2025-11-09 コメント: 2件 ▼
西郷南海子氏「小笠原先住民は欧米系・ポリネシア系」発言で歴史認識に一石・七色の人種論
れいわ新選組の西郷南海子政策委員が、小笠原諸島の先住民について「欧米系やポリネシア系の人々」との発言をXに投稿し、日本の歴史認識をめぐって議論を呼んでいます。 西郷氏は「日本人ファースト」という言説に疑問を投げかけ、東京都の小笠原諸島の真の歴史を明らかにしました。 西郷南海子政策委員は2025年11月、自身のXで「実は東京都の小笠原諸島の先住民は、欧米系やポリネシア系の人々です」と投稿しました。
「先住民は欧米系・ポリネシア系」発言の衝撃
西郷南海子政策委員は2025年11月、自身のXで「実は東京都の小笠原諸島の先住民は、欧米系やポリネシア系の人々です」と投稿しました。この発言は、一般的に認識されている日本の歴史像と大きく異なる内容として注目を集めています。
西郷氏によると、小笠原諸島では1830年にハワイから渡航した人々が初めて移住に成功し、その25人はイギリス、アメリカ、ハワイ、ポリネシアの島々など様々な地域の出身だったといいます。その後、捕鯨が盛んになり世界中から人が集まったため、多民族社会が形成されました。
「小笠原が欧米系・ポリネシア系の先住民って知らなかった。教科書で習った記憶がない」
「日本人ファーストと言うけれど、こういう歴史を踏まえるべきですね」
「多様な民族が先住していたという事実は重要な指摘だと思います」
「これまでの日本史の認識が変わりそうな発言ですね」
「東京都内にこんな複雑な歴史を持つ島があったなんて驚きです」
「七色の人種」という表現の意味
西郷氏の投稿で特に印象的なのは、故・小笠原愛作(アイザック・ゴンザレス)牧師が小笠原を「七色の人種」と表現したという部分です。この表現は、小笠原諸島がいかに多様な民族構成を持っていたかを象徴的に示しています。
小笠原愛作牧師は、ポルトガル系移住者ジョーキン・ゴンザレスをルーツに持つ小笠原家の出身で、戦後に聖ジョージ教会の牧師として活動しました。西郷氏のインタビューに対して、小笠原の多民族的な成り立ちを「七色の人種」という詩的な表現で語ったとされています。
これは単一民族論が根強い日本社会において、極めて対照的な歴史像を提示するものです。小笠原諸島では、異なる文化的背景を持つ人々が共存し、独自のコミュニティを形成してきたことがうかがえます。
歴史的事実としての多民族社会
西郷氏が引用する研究論文によると、小笠原諸島は長い間無人島でしたが、1830年の初回移住以降、世界各地からの移住者によってコミュニティが形成されました。徳川幕府は1861年に調査団を派遣し、1882年にはすべての居住者を帰化させましたが、もともとの住民は多様な出自を持っていました。
明治期の記録では、これらの人々は「帰化人」や「在来島民」と呼ばれていましたが、春日匠氏の研究によると「ふつうは『あとから来た人々』を意味する『帰化人』という言葉と『もとからいた人々という意味の『在来』』という言葉が同じ欧米系・南洋系の人々を指す」という複雑な状況がありました。
太平洋戦争末期には強制疎開が命じられ、6886人が島を去りました。戦後は「欧米系島民」とその家族のみが帰島を許可され、1946年に129人が帰還しました。その後1968年まで米国施政権下での生活が続けられました。
現代的意義と議論の焦点
西郷氏の発言は、現在しばしば語られる「日本人ファースト」的な言説に対する根本的な問題提起となっています。小笠原諸島の歴史は、日本列島が決して単一民族によって構成されてきたわけではないことを具体的に示しています。
ただし、この「先住民」という表現をめぐっては議論もあります。小笠原諸島は長期間無人島だったため、厳密な意味での先住民族は存在しないとする見方もあります。一方で、現在の国際法的な先住民族の定義とは別に、最初に定住した人々の民族的出自という観点から西郷氏は発言していると考えられます。
また、戦前・戦時中に「帰化人」の人々が「鬼畜米英」とみなされて排斥的な視線にさらされた歴史や、戦後の米国統治期を経て日本復帰時に「日本人」としてのアイデンティティを求められた経験なども、現代の多文化共生を考える上で重要な示唆を与えています。
西郷氏の研究発表は、表面的な国民意識ではなく、歴史的事実に基づいた多様性の理解が重要であることを改めて浮き彫りにしました。小笠原諸島の「七色の人種」という歴史は、現代日本社会における真の共生のあり方を考える上で貴重な材料となっています。