2025-07-01 コメント投稿する ▼
電子処方箋、導入目標は2030年へ後ろ倒し 「医療DX」進まぬ現実と制度定着の壁
電子処方箋、全国導入の目標を“事実上延期” 厚労省が方針転換
厚生労働省は7月1日、全国の医療機関での導入を目指していた電子処方箋の整備方針を見直し、電子カルテと一体での導入を推進するとともに、その目標時期を「遅くとも2030年まで」とする方針を示した。導入率の低迷を受けて、これまで掲げていた「2024年3月までの全国導入」という目標は事実上棚上げとなった。
この方針は、同日開かれた医療DXに関する有識者会合で説明されたもの。厚労省によると、電子処方箋の導入率は2024年6月22日時点で33.0%にとどまり、とくに病院や診療所での導入が大きく遅れていることが明らかとなった。
「やっぱり“全国導入”は夢物語だったか…」
「薬局が導入しても、病院や診療所が使ってなきゃ意味ない」
「医療DXって言葉ばっかりで全然進んでないのバレてる」
「現場のシステムはまだ紙ベース。無理に押しつけても混乱するだけ」
「導入率4割切ってるのに“DX”とか言うなよ」
薬局は8割導入も、病院・診療所は1〜2割台 現場に広がる温度差
厚労省が発表した最新の導入率データによれば、薬局の導入率は82.5%と高水準を示している一方、病院は13.4%、医科診療所は19.6%、歯科診療所に至ってはわずか4.7%にとどまっている。
電子処方箋は、患者の服薬情報を医師や薬剤師がリアルタイムで共有し、重複処方や危険な飲み合わせを防ぐことを目的に設計された仕組み。2023年1月から本格運用が始まり、当初は1年余りで全国展開を目指していた。
しかし、現実には「電子カルテが未整備」「既存のレセコン(レセプトコンピューター)と互換性がない」「スタッフのITスキルにばらつきがある」といった課題が山積。中小のクリニックや歯科医院などでは、システム移行への抵抗感が根強く、補助金の不十分さやサポート不足も導入の足かせとなっている。
「うちは電子カルテすら入ってないのに、処方箋だけ電子化とか無理」
「導入に数十万円かかって、結局コストだけかかる」
「自治体によって支援の温度差がありすぎる」
「患者からの“紙ちょうだい”圧もすごい」
「紙の方が安全って考えてる医者もまだまだ多い」
電子カルテとセットで普及促進へ “同時推進”で巻き返しなるか
厚労省は、電子カルテを既に導入している医療機関では電子処方箋の導入率が相対的に高いとの調査結果を踏まえ、今後は「電子カルテと一体的な整備」を推進するとしている。つまり、診療記録と処方箋情報をセットでデジタル化することで、導入ハードルを下げる狙いだ。
また、2023年度補正予算で医療DX推進に関連する助成制度が強化されたが、対象や金額にばらつきがあるという声も少なくない。今後は導入支援金や技術サポートの拡充が焦点となる。
ただし、医療機関によって業務フローや設備環境が大きく異なる現状では、「一律の制度設計」が現場にフィットするかは不透明だ。特に高齢の開業医や個人診療所などでは、人的・技術的な壁も高く、システム導入だけで解決できる問題ではない。
「DX疲れ」と現場の無力感 制度の意義が伝わっていない
今回の目標見直しは、電子処方箋の重要性を否定したわけではない。むしろ、制度の本来の目的――医療の安全性向上と情報共有の効率化――に立ち返る契機ともいえる。
しかしながら、多くの現場医師・薬剤師からは「DX疲れ」とも言える無力感が広がっている。「上からの号令で振り回されるだけ」「患者への説明負担が増える」「結局、紙とデジタルの二重対応になって効率が落ちる」といった声は、医療現場のリアルだ。
「“DX”って聞くとまた面倒くさいことが始まる気しかしない」
「実際には診察時間が伸びる。現場のことをわかってない」
「説明の手間と患者の不安で、現場のストレスはむしろ増えてる」
“2030年”は逃げではなく、再設計の猶予期間となるか
厚労省が設定した「2030年までに全国導入」は、時間を稼ぐ“逃げ”に見える一方で、制度を現実に即して再設計する猶予期間とも捉えられる。技術導入にとどまらず、現場の理解、患者の納得、運用サポートの三位一体がなければ、単なる“仕組みの空転”に終わりかねない。
医療DXという国家戦略が形骸化しないためには、「一方的な普及目標」ではなく、「なぜ必要なのか」という説明責任と、「現場をどう支えるのか」という伴走姿勢が求められる。







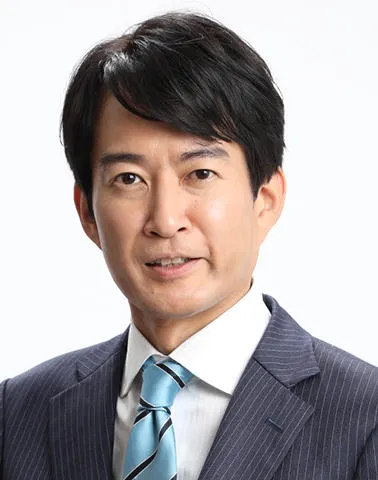




















![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)