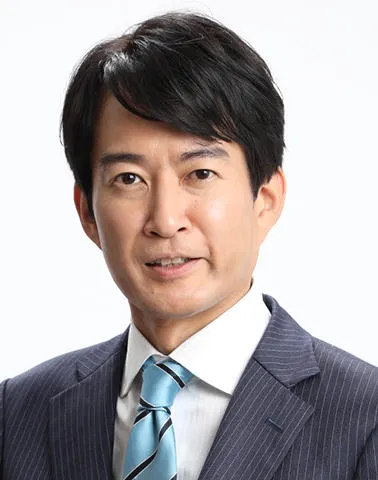2025-06-30 コメント投稿する ▼
期限切れ保険証でも受診容認へ マイナ保険証移行に混乱、厚労省が3月末まで暫定措置
有効期限切れ保険証が“救済措置”に
厚生労働省は、2024年12月に廃止予定の現行健康保険証が有効期限を迎えた後も、2025年3月末までの間、失効保険証による受診を暫定的に認める方針を決定した。マイナンバーカードと一体化された「マイナ保険証」への移行に伴い、全国の医療現場や高齢者を中心に混乱が予想されることを踏まえた判断だ。
この措置は、6月27日付で都道府県や医療関係団体に通知された。本来であれば、12月1日以降は「マイナ保険証」または、未取得者に発行される「資格確認書」のいずれかを提示しない限り、保険診療を受けられない建て付けとなっていた。だが、現場からは「高齢者がルールを把握していない」「受診できない患者が出る」との懸念が広がっていた。
利用率わずか3割未満 進まぬマイナ保険証
厚労省によると、マイナ保険証の利用率は2024年12月の移行開始時点で25%だったが、2025年5月末の時点でも29.3%にとどまる。半数を大きく下回る状況で、制度の定着には程遠い。
「たった3割の利用率で“廃止します”って無理ありすぎる」
「カード紛失してる人がどうなるか、説明すらない」
「病院受付も現場対応に疲弊してる。この制度誰のため?」
「無理やり移行させて、混乱したら“やっぱ柔軟対応します”って…」
「資格確認書とか言われても、普通の人には何のことかわからんよ」
現場では、特に高齢者や障害のある人が対応に苦慮しており、医療機関の窓口も混乱している。マイナカードの取得自体にハードルを感じている人も多く、「制度を分かりやすくせずに“義務”だけ押し付けてくる行政の横暴だ」との批判も少なくない。
「資格確認書」は取得に数日 実務と制度がかみ合わず
マイナ保険証を持たない人が保険診療を受けるには、自治体で「資格確認書」を発行してもらう必要がある。だがこの申請にも時間がかかり、申請日当日に手に入らない自治体も少なくない。
また、現在の制度上、失効した保険証で受診することは原則認められておらず、現場では「患者の命を守るのが先か、制度遵守が先か」という倫理的ジレンマに悩む医師や事務員もいる。厚労省は今回、「医療現場の柔軟対応を認める」として暫定措置に踏み切ったが、この“後出し対応”に政策の不備を感じる国民は多い。
制度先行、現実無視のツケ
今回の暫定対応は、一見すれば柔軟な措置のようにも見える。だが、そもそも利用率3割に満たない状態で、現行保険証を廃止しようとした判断そのものに疑問が残る。現場の声を無視し、制度だけが先行する政府の姿勢に対しては、冷ややかな目が向けられている。
また、マイナンバーカード一体化の是非をめぐっては、プライバシーや情報流出への懸念も根強く、強制的な移行を疑問視する声も後を絶たない。マイナ保険証の「利便性」は掲げられるものの、手続きや説明は複雑で、特にデジタル弱者への配慮が不十分だ。
「義務じゃないって言ってたのに、結局マイナカードなしでは診察も受けられないなんて」
「災害で家ごとカードを失くしたらどうするの?」
「国民皆保険の理念が壊れていく気がする」
日本の医療制度は、誰もが必要な時に必要な医療を受けられるという「皆保険」が柱だ。マイナ保険証への移行が、この原則を損ねるようでは本末転倒だ。
“形式優先”ではなく“命優先”の医療制度へ
今回の決定は、制度設計の甘さと、現実との乖離を象徴している。一方で、医療機関が「制度よりも命」を優先できるようになったことには、一定の評価もある。ただし、それは制度の失敗を現場に押し付けているだけではないか、という批判を免れるものではない。
厚労省は、マイナ保険証の「完全移行」を急ぐ前に、本当に国民のための制度なのかを問い直すべきだ。少なくとも、行政の都合だけで国民を振り回すことは、断じて許されない。