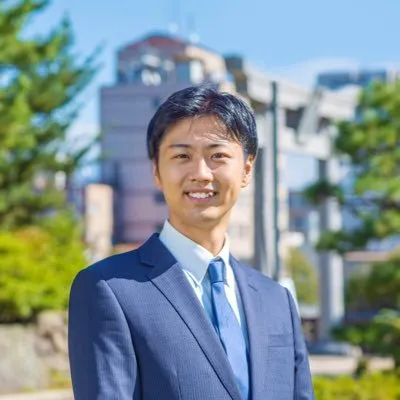2025-09-12 コメント投稿する ▼
岩屋毅外相 日本の大学生55名を中国派遣 日中若者交流で友情醸成と相互理解促進へ
岩屋毅外務大臣は、日本の大学生と大学院生を中国に派遣し、現地の若者との交流を通じて友情を深め、相互理解を促進する取り組みを発表した。 外務省は、この交流が次世代の相互理解を基盤とした日中友好関係の深化に寄与することを期待している。 また、現地の生活や文化を学ぶプログラムも含まれており、教育を軸に幅広い分野での相互理解を深める狙いがある。
岩屋外相、日中友好促進のため大学生を派遣へ
岩屋毅外務大臣は、日本の大学生と大学院生を中国に派遣し、現地の若者との交流を通じて友情を深め、相互理解を促進する取り組みを発表した。派遣期間は9月21日から27日までの7日間で、訪問先は北京市、湖南省、上海市の3地域となる。今回の事業は政府の青少年交流プログラム「JENESYS2025」の一環として実施され、公益財団法人日中友好会館が運営主体を担う。
外務省は、この交流が次世代の相互理解を基盤とした日中友好関係の深化に寄与することを期待している。団体規模は団長と学生50名に加え、日中友好会館事務局員4名を含めた計55名。現地では学校訪問や教育関係者との懇談、企業・施設見学などを通じ、中国社会への包括的な理解を促進する。
教育・文化交流で友情の基盤を
実施団体によると、今回のプログラムの交流テーマは「中国とのふれあい」。北京市や湖南省の小中学校訪問、湖南師範大学附属校での意見交換、中国教育関係者との会合などが予定されている。また、現地の生活や文化を学ぶプログラムも含まれており、教育を軸に幅広い分野での相互理解を深める狙いがある。
ネット上ではさまざまな意見が飛び交っている。
「若者交流で国際理解を深めるのは意義がある」
「こうした派遣事業は一部の参加者だけが恩恵を受けて終わりがち」
「中国に派遣するよりも国内学生の生活支援が必要では」
「友情醸成は良いが、一方的なプロパガンダに利用されないか心配」
「相互理解よりも国益を意識した交流設計が必要だ」
国民からの懸念と外交上の課題
日本政府は「JENESYS」を通じてアジア各国との交流を積極的に推進してきたが、中国に対する取り組みは特に注目を集める。日中関係は経済や安全保障を巡り摩擦が続く中で、若者世代の交流を軸に「草の根の信頼」を築くことを目的としている。しかし一部からは「文化交流の名目で一方的な親中感情の醸成につながるのではないか」という警戒も根強い。
特に今回の派遣では、中国日本友好協会からの招聘を受ける形式となっており、外交的バランスや国益上の透明性が問われる。国民にとっては「どのような成果があるのか」「費用対効果はどうか」という説明責任が政府に求められる。
日中若者交流の意義と今後の展望
岩屋外相の主導する今回の派遣は、教育交流を通じた国際理解促進という点で意義を持つが、その成果が日中関係の改善や国益にどう結びつくかは今後の検証が必要だ。友情や相互理解を強調するだけでなく、日本の立場や価値観を若い世代がしっかりと発信できるかが重要である。単なる一方向の文化交流ではなく、相互の信頼を築く「双方向の対話」として機能するかどうかが、今後の外交戦略に影響を及ぼすだろう。