2025-10-29 コメント投稿する ▼
愛知県が5.5億円事業で定住外国人支援研究会、日本語読み書きの必要性を問い直すテーマに疑問の声
この事業は文部科学省の地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業を活用したもので、2025年度予算として5億5千万円が投入される見込みです。 大村秀章知事氏が率いる愛知県では、外国人住民が33万人を超える中、日本語教育のあり方が問われています。 この事業は文部科学省の2025年度地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業を活用したものです。
「日本語の読み書きが本当に必要かって、そもそも何のための支援なんだ」
「5億円も使うなら、もっと他に優先すべきことがあるんじゃないか」
「外国人が働きやすい環境整備は大切だが、日本のルールは守ってもらわないと」
「言葉が通じない人にどう仕事を教えるか、現場は苦労してる」
「税金の使い道として、国民が納得できる説明が必要だと思う」
外国人住民が県人口の4パーセント超
愛知県内の外国人住民数は2024年12月末時点で33万1733人に達し、県総人口の4.45パーセントを占めています。これは全国平均の2.3パーセントを大きく上回り、東京都に次いで全国2位の規模です。国籍別ではベトナムが6万4377人で最多、ブラジルが6万980人、フィリピンが4万6944人と続きます。
愛知県は自動車産業を中心とした製造業が盛んで、外国人労働者への需要が高い地域です。在留資格別では永住者が最も多く全体の32パーセントを占め、次いで技能実習が16パーセントとなっています。県内では名古屋市、豊田市、豊橋市などで特に外国人住民が多く、地域社会での共生が重要な課題となっています。
読み書き必要性を問い直す研究会
今回の研究集会は国立国語研究所共同研究プロジェクト定住外国人のよみかき研が主催し、公益財団法人愛知県国際交流協会が共催、愛知県が後援する形で開催されます。テーマは「よみかきの多様性を考える、さまざまな手段と支援のかたち」です。
主催者側は「日本語の読み書きとは何か、本当に必要なのかを問い直し、生活に根ざした多様なよみかきの姿を考える」としています。近年の研究では読み書きに不自由があっても人とのつながりや工夫によって生活を支えられることがわかってきたといい、外国人だけでなくろう者・難聴者など障がいを持つ人々の実践も取り上げるとしています。
5億5千万円の予算投入に疑問の声
この事業は文部科学省の2025年度地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業を活用したものです。同省は2025年度にこの推進事業に5億5千万円を投入する予定で、全国53件の取り組みを補助する計画です。
日本語教育課が文部科学省総合教育政策局に設置されて以降、日本語教育関連予算は大幅に増額されています。しかし読み書きの必要性そのものを問い直すという今回の研究会の趣旨に対しては、税金の使い道として適切なのかという疑問の声も上がっています。
法整備なき受け入れ拡大の矛盾
愛知県では公益財団法人愛知県国際交流協会を中心に、外国人児童生徒の日本語学習促進のための環境整備が進められています。県は第4次あいち多文化共生推進プランを策定し、長年にわたり多文化共生のプロジェクトを推進してきました。
しかし外国人労働者の受け入れが拡大する一方で、日本の法律や文化を順守させるための法整備は十分に進んでいません。言葉が通じない、ルールを守らない、トラブルが起きても海外に逃げられるといった問題が現場では指摘されており、受け入れ側の日本人が一方的に負担を強いられる構造になっているとの批判もあります。






























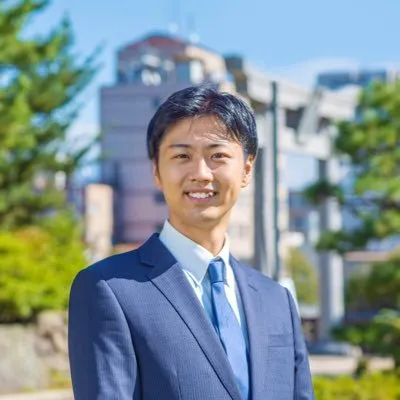
![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)



