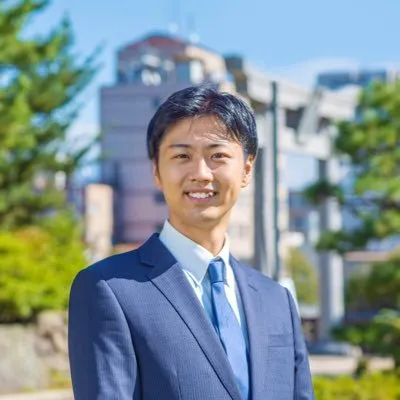2025-11-26 コメント投稿する ▼
外務省事業でインドネシアの主要イスラム団体青年8名が日本の宗教観と平和構築を学習
外務省の対日理解促進交流プログラム「JENESYS」により、インドネシアのイスラム社会団体の学生等8名が2025年11月11日から18日まで日本を訪問し、日本の文化や宗教観について理解を深める活動を行いました。 外務省は対日理解促進交流プログラム「JENESYS」の一環として、インドネシアの代表的イスラム社会団体から青年8名を招へいしました。
インドネシア主要イスラム団体の青年8名が来日
外務省は対日理解促進交流プログラム「JENESYS」の一環として、インドネシアの代表的イスラム社会団体から青年8名を招へいしました。参加者の内訳は、インドネシア最大のイスラム組織ナフダトゥール・ウラマ(NU)所属の青年3名、第2の規模を誇るムハマディヤ所属の青年3名、イスティクラル・モスク所属の青年1名、国立イスラム大学ジャカルタ校所属の青年1名となっています。
ナフダトゥール・ウラマは1926年に設立されたインドネシア最大のイスラム組織で、約3000万人から8000万人の支持者を有し、伝統的なイスラムの価値を守りながら寛容性を重視する立場を取っています。一方、ムハマディヤは1912年に設立された近代主義的なイスラム組織で、2000万人から4000万人のメンバーを擁し、教育と社会福祉に重点を置いています。
イスティクラル・モスクは首都ジャカルタにある東南アジア最大のモスクで、20万人を収容でき、インドネシアの独立を記念して建設された国の象徴的な宗教施設です。
多文化共生と平和構築への意識醸成が目的
今回の事業は、インドネシアの大学生・社会人が日本の伝統文化や歴史、宗教観に関する視察や意見交換を通じて、日本理解と平和構築・多文化共生への意識醸成を促進することを目的としています。
一行は東京と長崎に滞在し、日本の文化、宗教、歴史、平和への取組について理解を深めるため、寺社、高校、大学、原爆資料館、諫早市役所、抹茶工場等を訪問しました。特に注目すべきは、日本におけるイスラム教についての講義を受講したことで、日本社会でのイスラム教の位置づけや多宗教共存の実態について学習しました。
また、2泊3日のホームステイを体験し、日本の家庭生活や地域社会の実情を肌で感じる機会も設けられました。地方自治体が取り組む防災などの課題についての説明も受け、日本の行政システムについても学習しています。
知見の共有と発信への意欲を表明
2025年11月18日に開催された帰国報告会では、参加者たちが各訪問先・行事で撮影した様々な写真を紹介しながら、日本で感じたこと、学んだことを発表しました。参加者たちは、このような知見をそれぞれの団体やコミュニティーで発信していくとの計画を明らかにしました。
インドネシアは世界最大のイスラム人口を擁する国であり、人口の約9割がイスラム教徒です。同国のイスラム社会は穏健で寛容な特色を持っており、今回の交流は日本とインドネシアの相互理解促進に重要な意義を持っています。
JENESYSプログラムは東アジア地域の青少年交流を通じて対日理解を深める外交政策の一環として実施されており、両国の将来を担う若いリーダー育成にも寄与しています。今回の事業により、インドネシアのイスラム社会における日本理解がさらに深まることが期待されています。