2025-08-13 コメント投稿する ▼
富山県、外国ルーツ児童の発達支援セミナー開催 ポルトガル語版WISCで正確な評価へ
富山県は8月22日、外国にルーツをもつ子どもたちの就学や発達支援をテーマにしたセミナーを開催する。 とやま国際センターによれば、外国にルーツを持つ児童生徒は年々増加傾向にある。 1つ目は、NPO法人Gコミュニティ代表理事による「学校の協力と保護者の理解を得て取り組むポルトガル語版WISCによる外国人児童生徒への発達支援」。
富山県、外国ルーツの子どもの就学・発達支援セミナー開催
富山県は8月22日、外国にルーツをもつ子どもたちの就学や発達支援をテーマにしたセミナーを開催する。主催は公益財団法人とやま国際センター、共催はNPO法人アレッセ高岡。対象は外国人児童生徒の支援に携わる人や関心のある人で、定員は40名だ。
背景:日本語力不足で誤認される子どもたち
とやま国際センターによれば、外国にルーツを持つ児童生徒は年々増加傾向にある。しかし、日本語理解が十分でないことを理由に、特別支援学級や特別支援学校に在籍するケースが目立っている。発達の特性を正しく見極めるには、日本語力や文化背景が影響し、判断を誤る危険があるのが現状だ。
こうした中、支援が必要な子どもが適切な支援につながるためには、発達障害と外国ルーツ双方に関する理解を深め、多面的な関わりを持つことが求められている。
「日本語が不十分なだけで発達障害と判断されるのは避けたい」
「文化背景を理解した上で支援を設計する必要がある」
プログラム内容:ポルトガル語版WISCを活用
セミナーは二部構成で行われる。第1部では、事例紹介と講義を実施。
1つ目は、NPO法人Gコミュニティ代表理事による「学校の協力と保護者の理解を得て取り組むポルトガル語版WISCによる外国人児童生徒への発達支援」。ポルトガル語版のWISC(知能検査)を用いることで、日本語力の影響を減らし、正確な発達評価を行う方法を解説する。
2つ目は、文部科学省 元豊橋市教育委員会外国人児童生徒教育相談員による「豊橋市における就学相談の仕組みと支援体制の整備」。外国ルーツ児童生徒の就学相談の実践例や制度づくりのノウハウが共有される。
第2部では、参加者による意見交換・発表を行い、現場での課題や対応策を話し合う予定だ。
意義と今後の課題
このセミナーは、言語や文化の壁が発達評価に影響する現状を改善する一歩と位置付けられる。特にブラジルなどポルトガル語圏出身の子どもたちは、言語の違いによって学習評価や支援が遅れるケースが報告されており、今回のような母語による評価の導入は全国的にも注目される。
ただし、評価手法の普及や現場の理解、専門人材の確保が課題であり、単発のセミナーにとどまらず継続的な研修や支援体制強化が必要だ。
「評価方法の改善が子どもの未来を左右する」
「現場の教員や支援員が継続的に学べる仕組みを作ってほしい」




























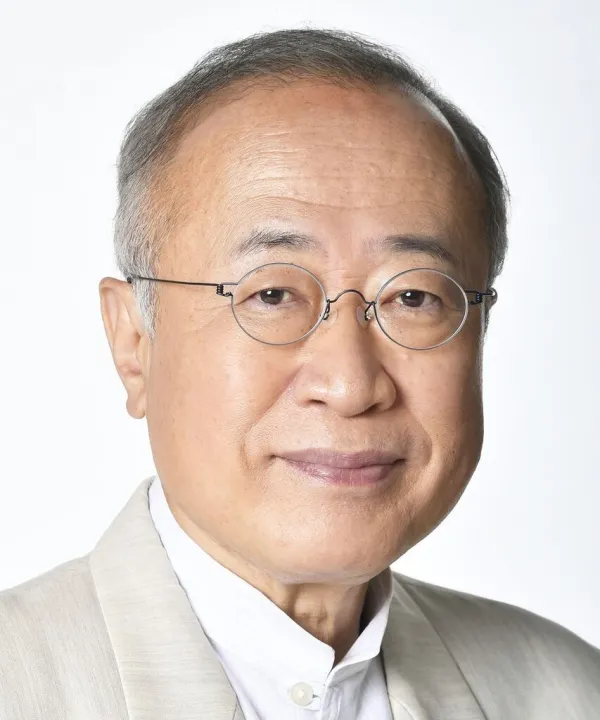


![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)

