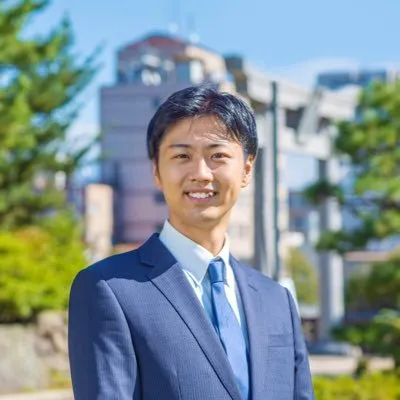2025-11-26 コメント投稿する ▼
政府が少額輸入品課税へ調整 SHEIN・Temu優遇廃止で国内事業者との不公平解消
現在、消費者が海外から1万円以下の商品を購入する際は原則として消費税が免除されていますが、この制度を利用して中国系ECサイトが破格の安値攻勢を仕掛けており、正規の税金を納めている国内事業者が著しく不利な状況に置かれています。 今回の制度見直しが実現すれば、中国系ECサイトで購入する商品には原則として10パーセントの消費税が課されることになり、これまでの価格優位性は大幅に縮小します。
現在、消費者が海外から1万円以下の商品を購入する際は原則として消費税が免除されていますが、この制度を利用して中国系ECサイトが破格の安値攻勢を仕掛けており、正規の税金を納めている国内事業者が著しく不利な状況に置かれています。財務省は海外EC事業者に消費税の納税義務を課し、国内での物品販売などが50億円を超える事業者を対象とする案を検討しています。
「やっと不公平な競争に歯止めがかかるのか。国内事業者にとっては朗報だ」
「SHEINとかTemuばかり使ってたから、値上がりするのは痛いなあ」
「税収確保の観点からも当然の措置。遅すぎるくらいだ」
「中国EC優遇はおかしいと思ってた。日本企業を守るべき」
「個人輸入の恩恵もなくなるのか。時代の流れかな」
急増する少額輸入と税関業務への圧迫
財務省の統計によると、2024年の課税価格1万円以下の「少額貨物」輸入は約1億7千万件に達し、全輸入許可件数の約9割を占める異常事態となっています。この急増の背景には、中国発の格安通販サイトの爆発的な成長があります。とくにSHEINやTemuは免税制度を最大限活用して日本市場での販売を拡大しており、同じ商品でも国内事業者より数十パーセント安く販売できる構造的な優位性を持っています。
この状況は単なる競争の問題にとどまらず、税関業務にも深刻な影響を与えています。少額輸入品の急増により税関の処理能力が圧迫され、偽造品や不正薬物の水際取り締まりといった本来の安全保障機能に悪影響が及んでいるのが実情です。薄利多売のビジネスモデルを採用する中国系ECサイトが大量の小口貨物を送り込むことで、日本の通関システムそのものが機能不全に陥りかねない状況となっています。
国内の小売業やメーカーからは「同じ商品なのに税制上の優遇で価格差が生まれるのは明らかに不公平」という声が高まっており、正当な競争環境の回復を求める声は業界全体に広がっています。また最近は商業輸入を個人輸入と偽って通関するケースや、複数回に分けて発送して課税を逃れる行為も増加しており、制度の抜本的な見直しが避けられない状況となっています。
世界的な免税制度見直しの潮流
この問題は日本だけでなく、アメリカや欧州連合(EU)などでも深刻化しており、各国が相次いで対応に乗り出しています。アメリカでは2025年5月2日からトランプ政権が中国・香港からの荷物について「デミニミス・ルール」の適用を廃止し、800ドル以下の少額貨物にも関税を課す措置を開始しました。
この結果は劇的で、Temuのアメリカにおける月間ユーザー数は58パーセントも減少し、中国系ECサイトのビジネスモデルが根本から揺らいでいます。EUでも2021年7月から輸入額に関係なく付加価値税(VAT)を課す「IOSS制度」を導入しており、海外EC事業者への課税強化は世界的な潮流となっています。
メキシコ政府も2025年1月1日より、中国からの製品に対して19パーセントの関税を課す新制度を施行するなど、各国が自国産業保護の観点から規制を強化しています。日本がこの流れに遅れることは、国際競争力の観点からも問題があり、早急な対応が求められています。
国内経済への影響と今後の展望
今回の制度見直しが実現すれば、中国系ECサイトで購入する商品には原則として10パーセントの消費税が課されることになり、これまでの価格優位性は大幅に縮小します。国内事業者にとっては公正な競争環境の回復につながる一方、消費者にとっては実質的な値上げとなるため、購買行動に変化が生まれる可能性があります。
ただし、この変化は必ずしも消費者にとってマイナスばかりではありません。正当な税金を納めている国内事業者が競争力を回復することで、品質やアフターサービスの充実した商品がより評価されるようになり、長期的には消費者利益の向上にもつながると期待されています。
政府は海外EC事業者に対して適切な納税システムの構築を求めるとともに、税務当局による監督体制の強化も検討しています。これにより透明性の高い電子商取引環境の構築を目指しており、消費者保護の観点からも重要な意義を持っています。
今回の制度見直しは、デジタル時代における税制の在り方を問う重要な転換点となっており、財政収入の確保と公正な競争環境の両立という難しい課題に対する政府の明確な意志を示すものです。2026年度からの実施を目指して年末の税制改正大綱に盛り込まれる見通しであり、関係業界では対応準備が急ピッチで進められています。
この投稿の高市早苗の活動は、79点・活動偏差値57と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。