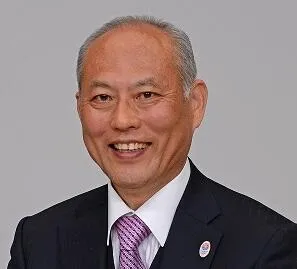2025-11-17 コメント: 5件 ▼
高市早苗首相の台湾有事発言で中国が「沖縄は日本ではない」と無理筋主張、日中関係が急速悪化
中国の「沖縄は日本ではない」発言と日中関係悪化。 中国国営メディアは「沖縄は日本ではない」とする極端な主張まで展開し、文明国家のメディアとは思えない無理筋な言動で日本を威嚇している。 こうした「沖縄は日本ではない」という主張は、国際法上も歴史的事実からも完全に誤りである。
高市早苗首相氏の台湾有事に関する国会答弁をめぐり、中国政府が激しい反発を続けている。2025年11月17日、中国外務省の毛寧報道官は22日から23日に南アフリカで開催される主要20カ国・地域首脳会議(G20サミット)期間中、李強首相と高市首相の会談は「予定がない」と明言した。中国国営メディアは「沖縄は日本ではない」とする極端な主張まで展開し、文明国家のメディアとは思えない無理筋な言動で日本を威嚇している。
高市首相氏が2025年11月7日の衆議院予算委員会で、台湾有事が集団的自衛権行使の根拠となる「存立危機事態」になり得ると答弁したことが発端となった。首相氏は中国軍による台湾への武力侵攻について「戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得るケース」と述べた。これに対し中国側は猛烈な勢いで反発し、答弁の撤回を要求している。
中国国営メディアの異常な沖縄主張
中国の反発は政治的抗議にとどまらず、国営メディアまで動員した情報戦の様相を呈している。チャイナ・デイリーは11月15日、「琉球(沖縄の旧称)は日本ではない」とする沖縄の学者のインタビューを掲載した。同紙は第二次世界大戦中の沖縄戦を引き合いに出し、「日本を守るために沖縄を犠牲にしようとした」と歴史を歪曲した主張を展開。さらに「高市首相氏の過激な立場に対し、沖縄住民の大半が懸念している」と事実無根の内容を報じた。
こうした「沖縄は日本ではない」という主張は、国際法上も歴史的事実からも完全に誤りである。沖縄は1972年の沖縄返還により正式に日本に復帰し、現在は日本の47都道府県の一つとして確固たる地位を占めている。中国のこのような主張は文明国家のメディアが報道すべき内容ではなく、明らかに政治的意図を持った宣伝活動と言わざるを得ない。
「中国の沖縄に対する主張は歴史的根拠が全くない。完全に的外れだ」
「沖縄は間違いなく日本の領土。中国の言いがかりは許せない」
「中国は尖閣諸島に続いて沖縄まで狙っているのか。危険すぎる」
「沖縄県民として中国の勝手な主張には強く反対する」
「日本政府は中国の暴論に毅然とした姿勢で対応してほしい」
中国政府の報復的措置が拡大
中国政府の反発は外交面にとどまらず、経済・文化交流分野にも拡大している。2025年11月14日夜、中国外務省は中国国民に対して日本への渡航を控えるよう注意喚起を発表した。さらに11月16日には中国教育省も日本への留学について「慎重な検討」を求める通知を出した。これらの措置により、日本の観光業や教育機関への影響が懸念されている。
愛知県半田市では11月18日に予定されていた中国江蘇省徐州市政府代表団の表敬訪問が急遽中止された。また、2005年から毎年開催されていた日中有識者による「東京―北京フォーラム」も中国側の通告により延期に追い込まれた。民間レベルの交流まで政治問題の影響を受ける事態となっている。
日本政府の対応と今後の展望
木原稔官房長官は中国側の一連の措置について「首脳間で確認した戦略的互恵関係の推進という方向性と一致しない」と強く批判した。外務省の金井正彰アジア大洋州局長は11月17日に北京を訪問し、中国外務省の劉勁松アジア局長との協議に臨んだ。日本政府は対話を通じた関係改善を模索している。
しかし中国側の姿勢は硬化の一途をたどっている。中国外務省の孫衛東次官は11月13日、金杉憲治駐中国大使を呼び出し、高市首相氏の発言撤回を要求。応じない場合は「一切の責任は日本側が負わなければならない」と威嚇的な発言を行った。中国の薛剣駐大阪総領事に至っては、SNS上で高市首相氏に対する暴言を投稿し、後に削除する騒動も起きている。
今回の一連の事態は、中国が台湾問題を自国の核心的利益と位置づけ、少しでも中国の立場に反する発言に対しては激しい反発を示す姿勢を鮮明にしたものだ。高市首相氏の発言は日本の防衛政策の一環として当然の内容であったにもかかわらず、中国は過剰反応を示している。特に「沖縄は日本ではない」という荒唐無稽な主張は、中国の覇権主義的野心を如実に示すものであり、日本としては断固として受け入れることはできない。
日中関係の安定は東アジア地域全体の平和と繁栄にとって重要である。しかし、それは中国が国際法と歴史的事実を尊重し、責任ある大国としての行動を取ることが前提となる。日本政府には引き続き毅然とした外交姿勢を貫き、同時に建設的な対話の扉を開いておくことが求められている。
この投稿の高市早苗の活動は、100点・活動偏差値61と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。