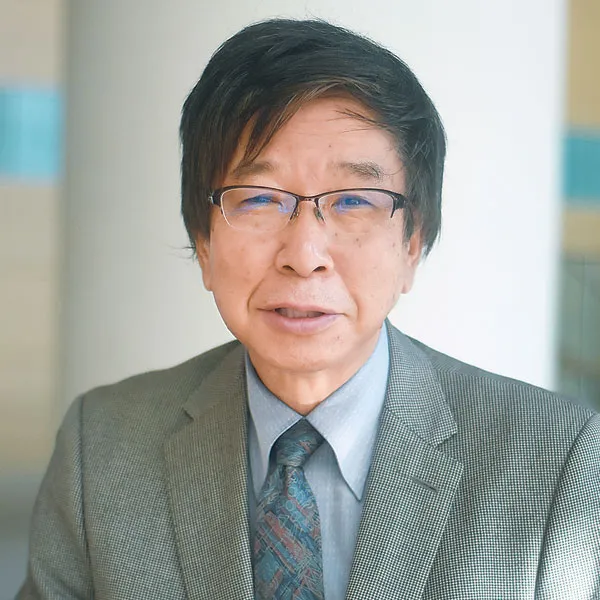2025-06-28 コメント投稿する ▼
杉ひさたけ氏が訴える「中小企業支援」は本物か──給付金依存からの脱却を問う
具体的には、物価高を上回る賃上げの実現を掲げ、「年収の壁」の引き上げなどの実績をアピールした。 年収の壁対策とは、パート労働者が一定の年収を超えると社会保険の負担が発生することから、就業調整を強いられる構造の改善を狙ったものだが、それ自体が抜本的な解決とは言い難い。
「中小企業活性化」へ全力?実効性に乏しい政策の現実
参院選を前に、大阪選挙区から立候補予定の杉ひさたけ氏(公明党)が28日に大阪市で行われた政経講演会に登壇し、「中小企業の活性化に全力を挙げる」と強調した。具体的には、物価高を上回る賃上げの実現を掲げ、「年収の壁」の引き上げなどの実績をアピールした。
しかし、この主張には疑問の声も少なくない。年収の壁対策とは、パート労働者が一定の年収を超えると社会保険の負担が発生することから、就業調整を強いられる構造の改善を狙ったものだが、それ自体が抜本的な解決とは言い難い。そもそも根本的な制度の見直し、特に税制改革に触れないままの「対症療法」である。
さらに「物価高を上回る賃上げ」という目標を掲げる一方で、実際に企業が人件費を上げる余力を持てるような減税措置や規制緩和への具体策は乏しい。給付金や補助金で一時的な“対策感”を演出するだけでは、持続的な成長にはつながらない。
「活性化って言っても、減税も規制緩和もなしじゃ意味ない」
「また給付金頼み?それで中小企業が元気になるのか」
「物価高なのに消費税はそのままって…庶民の生活わかってない」
「賃上げ支援って言っても、企業の体力がないと無理でしょ」
「聞こえのいいことばかりで実行力が見えない」
“年収の壁”改革の限界──現場の声との乖離
杉氏は「年収の壁」引き上げを成果として強調するが、これは短期的な措置にすぎない。本来、こうした制度は社会保険料負担のあり方や雇用制度全体の見直しとセットで進めなければ、真の働き方改革にはつながらない。現場からは「結局、企業側の判断でシフトを削られる」「扶養控除の枠が変わっても根本は変わらない」という声も多い。
さらに、パートや非正規労働者に頼る中小企業にとって、政府の一方的な制度変更は混乱を招くだけの側面もある。「労働者が長く働けるようになる」はずの施策が、結果的に労使間の不信や調整負担を増やすリスクもあるのだ。
つまり、制度の「見直し」が政治的な実績として扱われる一方で、肝心の「現場の実情」には十分に寄り添っていないという批判も根強い。
本当に必要なのは「減税」という構造改革
選挙前になると、どうしても耳障りの良い言葉が並ぶ。「賃上げ」「物価対策」「中小企業支援」──これらは有権者の不安を和らげる言葉としては有効だが、肝心なのは“どのように実現するのか”という具体性と実効性である。
本当に中小企業を活性化させたいのであれば、法人税の軽減、消費税の減税、インボイス制度の廃止など、コストを直接削減できる策こそが必要だ。補助金や給付金では一時しのぎにしかならず、「もらえるかどうか」の不安が経営の不安定要因となる。
杉氏が語る「中小企業活性化」は、現状ではこの根本的な政策論には踏み込めていないように見える。
「まず消費税を下げてほしい。それが一番の支援だよ」
「中小企業支援って言うならインボイス撤廃しなよ」
「賃上げ?減税しなきゃ企業に余力なんてない」
「財源ってどうするの?補助金バラマキじゃ続かない」
「また公明党が“やってる感”だけ出して終わりそう」
耳障りの良い言葉より、骨太な改革を
杉ひさたけ氏の演説は、「庶民の味方」としての姿勢を前面に出したものだった。しかし、その内容は、いわゆる“選挙向けの優等生的アピール”に終始している感が否めない。確かに給付金や年収の壁の見直しなど、過去の「成果」を並べることは容易だ。だが、それが持続可能な社会をつくる政策なのか、今一度考える必要がある。
耳障りの良いスローガンではなく、真に中小企業や庶民の生活を支えるには、思い切った減税と構造改革が不可欠だ。公明党の一角を担う杉氏がそのリーダーシップを発揮できるのか──有権者はそこを見ている。