2025-06-27 コメント投稿する ▼
公明党・新妻ひでき氏が掲げる「温かい政治」は幻想か──減税なき支援政策の限界
しかし、こうした美辞麗句とは裏腹に、「温かい政治」が具体的に何を意味し、どのように実現されるのかという肝心な点はあいまいなままだ。 給付金頼みの政策が本当に国民生活の底上げにつながっているのか、疑問の声も上がっている。 新妻氏の講演では、公明党が実現したとされる各種補助政策に繰り返し触れられた。 新妻氏の訴える「温かい政治」とは何なのか。
比例候補・新妻ひでき氏が語る未来
公明党の新妻ひでき氏(比例代表・参院選予定候補)が、静岡市で開催された時局講演会に登壇し、「すべての人を照らす温かい政治の実現へ戦い抜く」と決意を語った。同行した山口那津男常任顧問は、物価高への対策として公明党の役割を強調。「103万円の壁」の引き上げや、ガソリン・電気・ガス代への補助は公明党が主導して実現したとアピールした。
また、新妻氏の実績として「東日本大震災で被災した福島県に、ロボットやAIなど先端産業を集積させた」と紹介。地方創生に貢献したという評価を得ようとしている。
しかし、こうした美辞麗句とは裏腹に、「温かい政治」が具体的に何を意味し、どのように実現されるのかという肝心な点はあいまいなままだ。給付金頼みの政策が本当に国民生活の底上げにつながっているのか、疑問の声も上がっている。
「“温かい政治”って…結局は曖昧な言葉だよね」
「補助金より減税してくれた方がありがたいのに」
「103万の壁とか言ってる場合?手取りを増やす減税が先でしょ」
「先端産業って言うけど、福島の暮らしは良くなったの?」
「ロボット産業よりまず、生活を支える仕組み作ってよ」
公明党の「補助金政治」は誰のため?
新妻氏の講演では、公明党が実現したとされる各種補助政策に繰り返し触れられた。電気・ガス代、ガソリン代、そしてパートタイマーなどへの「年収の壁」対策など、家計支援策が中心だ。しかし、そのほとんどが補助金による一時的な支援であり、制度的な構造改革や恒久的な税制見直しには踏み込んでいない。
実際、多くの国民は「生活を根本から支える政策」、すなわち所得税・消費税の減税やインボイス制度の撤廃を望んでいる。にもかかわらず、公明党はあくまで「給付」と「支援」でしのごうとする姿勢を崩していない。
給付金政策は即効性こそあるものの、持続可能性が乏しく、結局は増税や借金という形で国民の負担に跳ね返ってくる。一時の補助金より、可処分所得が増える減税の方がよほど長期的な効果が期待できるにも関わらず、その声は政策の中にほとんど反映されていない。
「先端産業の集積」は誰を救うのか
新妻氏は、福島へのロボット・AI産業の集積を「被災地支援の柱」として紹介しているが、これも疑問視される点が多い。そもそも最先端技術産業は高い専門性を必要とし、被災地域の高齢化が進む中で地元住民がその恩恵に直接あずかれるとは限らない。
技術誘致によって地域経済が活性化することを否定はしないが、それが本当に「誰一人取り残さない政治」につながるのかといえば、答えは簡単ではない。むしろ、真に必要とされているのは、住民が日々の暮らしで安心できる社会保障制度や減税による支出の軽減ではないか。
「先端技術を集めても地元が使えなければ意味ないよね」
「福島の人たちがどれだけ恩恵受けたのか、ちゃんと説明して」
「生活支援って言うなら、減税をまずやってからにして」
「ロボットより病院と学校じゃないの?」
「地方創生って言うけど、東京と何が違うのか全然伝わらない」
「温かい政治」に必要なのは減税と制度改革
新妻氏の訴える「温かい政治」とは何なのか。それは誰にとっての「温かさ」なのか。曖昧な言葉に期待を持たせるだけでなく、具体的な中身が問われる段階にきている。
公明党が本当に庶民のための政治を標榜するのであれば、インボイス制度の廃止、消費税の引き下げ、そして中小企業に対する法人税軽減措置など、明確な減税政策に踏み出すべきだ。短期的な補助金ではなく、生活の根幹を支える税制改革こそが「温かい政治」の第一歩である。
今のままでは、給付金バラマキを繰り返すだけの選挙向け政策にしか見えない。耳障りの良いスローガンではなく、実効性のある改革を打ち出せるか。それが今、新妻ひでき氏に問われている。



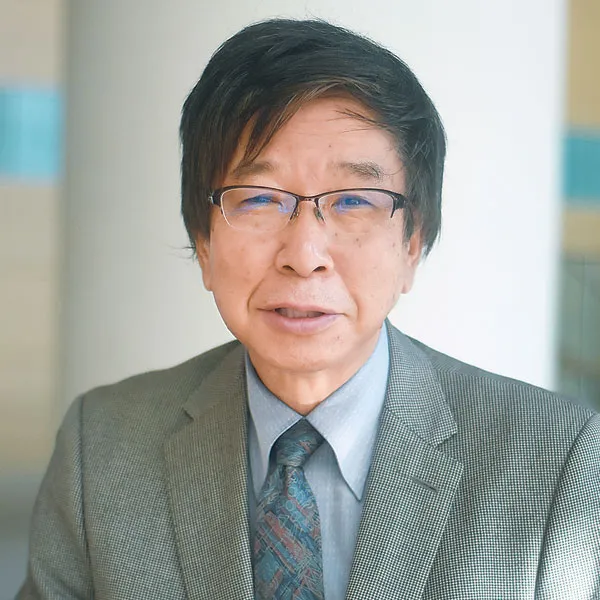



























![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)


