2025-11-04 コメント: 1件 ▼
和歌山県立高校募集定員が過去最少6200人に減少 少子化で157学級に削減2026年度
和歌山県立高校の募集定員が過去最少を更新 少子化で全日制157学級6200人に減少。 和歌山県では少子化の進行が深刻な課題となっています。 中学生も2年連続で最少を更新し、前年度より434人少ない2万3002人となっています。 今回の募集定員削減では、耐久高校の普通科と神島高校の経営科学科がそれぞれ1学級減となりました。
和歌山県教育委員会は11月4日、2026年度(令和8年度)県立高校の募集定員を発表しました。全日制課程は28校4分校の計157学級6200人で、前年度より2学級110人減少し、現行入試制度開始以来の過去最少となりました。少子化の進行により、県内の高校再編が加速している状況が浮き彫りになりました。
少子化の波が高校教育に深刻な影響
和歌山県では少子化の進行が深刻な課題となっています。県内の小学生数は38年連続で最少を更新しており、2023年度は前年度より891人少ない4万2164人でした。中学生も2年連続で最少を更新し、前年度より434人少ない2万3002人となっています。
このような中学生数の継続的な減少が、高校の募集定員削減に直結しています。県教委は「中学生の人数や受験者の状況、学科のバランスを考慮した」と説明していますが、実質的には生徒数減少への対応が主な要因となっています。
和歌山県の人口は1985年の約108万7千人をピークに減少を続けており、2025年には約87万人と予測されています。特に15歳から64歳までの生産年齢人口の減少が顕著で、これに伴って中学卒業者数も今後さらに減少することが見込まれています。
「このまま生徒数が減り続けると、うちの高校も統廃合の対象になるのでは」
「定員削減で倍率が上がるかもしれない。志望校選びがより慎重になる」
「地方の高校がどんどん減ると、通学の選択肢が狭まって困る」
「県内で高校教育を受ける機会が減るのは将来が心配」
「統廃合で伝統ある学校がなくなるのは寂しい」
具体的な削減内容と学校への影響
今回の募集定員削減では、耐久高校の普通科と神島高校の経営科学科がそれぞれ1学級減となりました。また、紀北農芸高校などは定員を40人から35人に削減するなど、きめ細かな調整が行われています。
一方で、併設中学校からの進学者のみで募集を行う学級も拡大しています。橋本高校の探究科と日高高校の総合科学科の各1学級、向陽高校の環境科学科と桐蔭高校の普通科、田辺高校の自然科学科の各2学級については、外部からの募集を停止し、併設中学校からの進学者計320人のみで構成されます。
これは中高一貫教育の拡充によって、限られた教育資源を効率的に活用する狙いがあります。県教委は「質の高い教育を継続的に提供するため、学校規模の適正化を図っている」としています。
定時制・通信制は増加傾向
全日制の定員削減とは対照的に、定時制課程は7校計16学級570人で前年度から2学級75人増加しました。きのくに青雲高校の普通科(昼間)と新宮高校新翔校舎の普通科(昼間)でそれぞれ1学級が増設されています。
また、通信制課程では新宮高校に新たに設置され、県内の通信制高校は4校となりました。多様な学習ニーズへの対応や、不登校生徒の受け皿としての役割が期待されています。
これらの動きは、従来の全日制一辺倒の高校教育から、生徒の多様な学習スタイルに対応した教育制度への転換を示しています。
他府県でも進む高校再編の動き
和歌山県と同様の課題は全国的な傾向で、各都道府県で高校再編が進んでいます。兵庫県では2025年度に14校を6校に統合する大規模な再編を実施予定です。神奈川県でも2030年から2031年にかけて8校を4校に統合する計画が発表されています。
これらの再編は単なる学校数の削減ではなく、教育内容の充実や施設の効率的活用を目指した改革として位置づけられています。統合により生まれる新校では、総合学科や特色ある専門学科の設置などが検討されています。
全国的に見ても、高校生数は2011年度から13年連続で減少しており、この傾向は今後も続くと予想されます。そのため、各都道府県では教育の質を維持しながら適正規模を保つための再編計画が不可欠となっています。
和歌山県の今回の発表は、地方における教育環境の変化を象徴する事例として注目されます。今後も少子化の進行に伴い、さらなる学校再編が避けられない状況となっており、地域の教育機会確保と質の維持が重要な課題となっています。




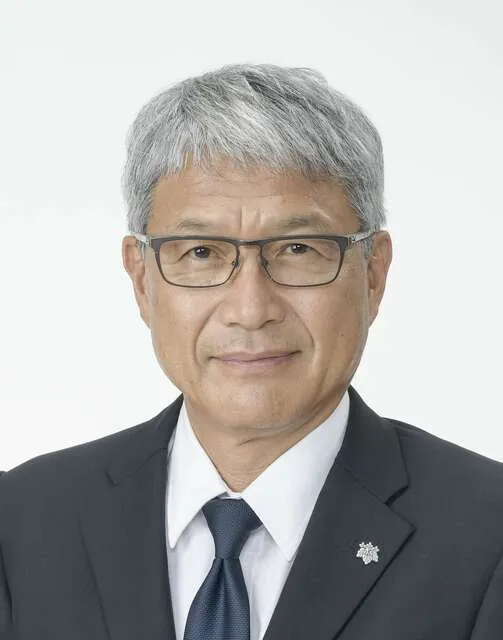




















![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)


