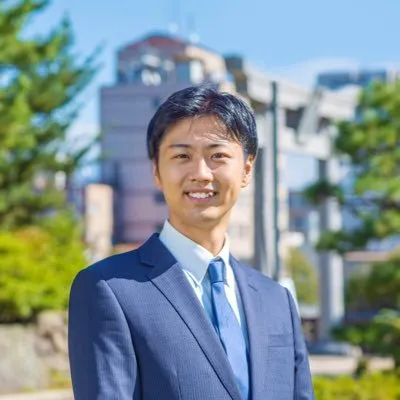2025-08-29 コメント投稿する ▼
緊急銃猟でハンター責任は「問われず」 環境省見解と北海道の対応
北海道で深刻化するヒグマ出没問題をめぐり、29日、鈴木直道知事は会見で「緊急銃猟」での発砲によって万が一人的被害が生じた場合でも、捕獲者であるハンターの責任は通常問われないとする環境省の回答を明らかにした。 出没件数が増加し、市街地での人身被害の危険が高まるなか、現場で発砲に当たるハンターの法的責任があいまいなままであれば、自治体の対応は立ちゆかなくなる。
緊急銃猟の責任問題に環境省が見解 ハンターの不安解消なるか
北海道で深刻化するヒグマ出没問題をめぐり、29日、鈴木直道知事は会見で「緊急銃猟」での発砲によって万が一人的被害が生じた場合でも、捕獲者であるハンターの責任は通常問われないとする環境省の回答を明らかにした。これは26日に環境省が示したもので、「市町村長の安全確保のもとで実施される場合」という条件付きで、刑事・行政責任の追及は想定されないという。
出没件数が増加し、市街地での人身被害の危険が高まるなか、現場で発砲に当たるハンターの法的責任があいまいなままであれば、自治体の対応は立ちゆかなくなる。北海道猟友会はこれまで「責任が不明確なままでは要請に応じられない」との姿勢を示しており、国の見解は一定の安心材料となる。
「責任がないと明言されて初めて安心して出動できる」
「事故が起きてもハンターが罪に問われないなら参加しやすい」
「自治体や国の補償体制も合わせて明確にすべき」
「銃猟のリスクを理解せず現場に頼るだけでは限界」
「人命優先だが、国民に説明責任はある」
ハンターの不安と自治体の現場対応
北海道猟友会の内部では「自分の判断で撃った結果、責任を問われるのでは」との懸念が長く続いていた。市街地での発砲は誤射や流れ弾のリスクが伴うため、ハンター個人に責任が及ぶ可能性を恐れる声は強い。今回の環境省の回答はそうした不安を解消する狙いがあるが、現場の信頼を得るには補償制度や手順のさらなる明確化が欠かせない。
一方で、自治体も住民の安全を守る責任を負っている。建物や車両などへの損害が生じた場合には市町村が補償するとされ、鈴木知事は「市町村の財政負担を道が支援する」と明言した。だが、補償スキームが自治体ごとに異なると現場に混乱を招く可能性があり、全国統一の仕組みづくりが課題となる。
野生動物対策と地域社会
ヒグマによる被害は北海道の農業被害や観光にも影響を及ぼしつつある。山間部だけでなく市街地に出没するケースが増加し、住民の不安は拡大している。緊急銃猟はあくまで最終手段であり、出没抑制や生息地管理など中長期的な対策も並行して求められる。
また、銃猟の担い手不足も顕在化している。ハンターの高齢化が進み、出動可能な人員は限られる。責任問題が不明確なままでは若手の参入はさらに難しくなり、地域社会のリスク管理が立ち行かなくなる懸念がある。
緊急銃猟の法的位置づけと国民への説明責任
今回の環境省の見解は、緊急時における法的責任を整理した重要な一歩である。だが「責任を問われない」という方針は国民的合意を伴わなければ、かえって不信や誤解を生みかねない。住民の安全を守るための制度設計と同時に、リスクや補償のあり方を国民にわかりやすく説明することが不可欠だ。
石破政権の下で進む野生動物対策は、国民の安全と地域社会の持続可能性を両立できるのか。緊急銃猟の制度化は、日本の「人と自然の共生」の在り方を問う試金石となっている。