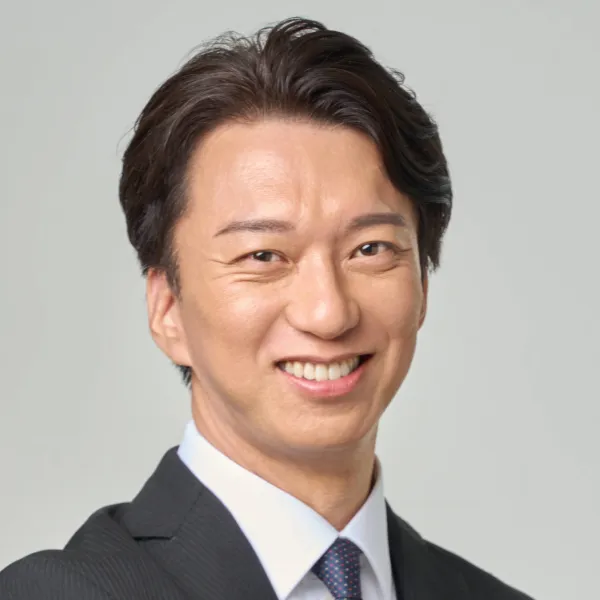2025-11-20 コメント: 1件 ▼
国民民主党・山田吉彦氏、尖閣諸島の固有種保護で政府に上陸調査要請
特に魚釣島では、センカクモグラやセンカクサワガニ、センカクツツジといった貴重な固有種が生息しているものの、現在その生存が深刻な脅威にさらされています。 質疑で政府側が衛星画像による調査を実施していると答弁したのに対し、山田氏は「衛星ではモグラやサワガニを発見することはまず難しい」と反論し、上陸による現地調査の必要性を強く訴えました。
尖閣諸島の深刻な環境危機と固有種の絶滅リスク
東海大学海洋学部客員教授でもある山田氏は、沖縄県石垣市に属する尖閣諸島の環境悪化について警鐘を鳴らしました。特に魚釣島では、センカクモグラやセンカクサワガニ、センカクツツジといった貴重な固有種が生息しているものの、現在その生存が深刻な脅威にさらされています。
これらの固有種は、長い地理的隔離の中で独自の進化を遂げた学術的に極めて価値の高い生物です。センカクモグラは1979年に1頭のみ捕獲された後、詳細な生態調査が行われておらず、環境省のレッドリストでは絶滅危惧IA類に指定されています。
「尖閣のヤギ問題は深刻だと思う」
「固有種が絶滅したら取り返しがつかない」
「政府は何をやってるんだ」
「衛星だけじゃ実態がわからないでしょ」
「現地調査なしに環境保護は無理だよ」
1978年に持ち込まれたヤギが生態系を破壊
環境悪化の主要因として山田氏が指摘したのは、1978年に民間団体が人為的に持ち込んだヤギの繁殖問題です。当初は雌雄各1頭だったヤギが爆発的に増加し、現在では500頭から1000頭にまで達していると推定されています。
野生化したヤギによる植生への食害は深刻で、衛星画像の分析では魚釣島の総面積3.8平方キロメートルのうち約13.59パーセントが裸地化していることが確認されています。山肌の露出や崖崩れも随所で発生しており、土壌流出による近海の汚染も懸念されています。
ヤギの食害により植物が減少すれば、土壌中の有機物も減少し、センカクモグラの餌となるミミズなどの土壌生物も激減します。このような生態系の連鎖的な破綻により、固有種の絶滅リスクが高まっているのが現状です。
政府の衛星調査では限界があると指摘
質疑で政府側が衛星画像による調査を実施していると答弁したのに対し、山田氏は「衛星ではモグラやサワガニを発見することはまず難しい」と反論し、上陸による現地調査の必要性を強く訴えました。
衛星画像では植生の変化や地形の変化は把握できても、地下に生息するセンカクモグラや岩陰に隠れるセンカクサワガニなどの小型動物の生息状況は確認できません。また、土壌の質的変化や微細な環境変化も、現地での詳細な調査なしには把握が困難です。
2022年から2024年にかけて石垣市が実施した海洋調査では、洋上からの観察や赤外線センサー搭載ドローンによる調査が行われましたが、野生化したヤギの正確な個体数や固有種の生息状況の詳細な把握には至っていません。
学術界からも長年の上陸調査要請
尖閣諸島の環境問題については、学術界からも長年にわたって上陸調査の実施が求められています。2003年には日本生態学会、日本哺乳類学会、沖縄生物学会が連名で環境省や外務省に対し、魚釣島のヤギ駆除と学術上陸調査の許可を要請しました。
石垣市議会も2008年に全会一致で「尖閣諸島(魚釣島)ヤギ捕獲を求める要請決議」を可決し、国に対して現地調査と自然保護対策を求めています。しかし、領有権をめぐる中国との外交的対立もあり、これまで政府による上陸調査の許可は下りていません。
山田氏の今回の質疑は、国会議員として初めて科学的根拠に基づいて尖閣諸島の環境保護を正面から取り上げたものであり、今後の政府対応が注目されています。
この投稿の山田吉彦の活動は、72点・活動偏差値56と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。