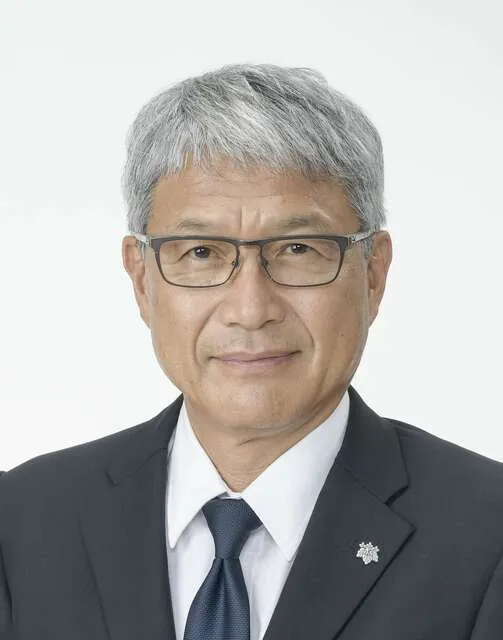2025-10-22 コメント投稿する ▼
クマ被害者108人、死者過去最多9人 木原官房長官が警戒呼びかけ 緊急銃猟制度の運用推進
クマによる被害者が2025年9月末時点で108人、死者が過去最多の9人となっていることを、木原稔官房長官氏が10月22日の会見で明らかにし、警戒を呼びかけました。 また、2025年9月から始まった緊急銃猟制度について、木原長官氏は「地方自治体への技術的・財政的支援を通じ、円滑な運用を全国に広げていく」と述べました。
木原長官氏によると、今年度のクマによる人身被害者数は9月末時点で108人で、2023年度の219人に迫るペースです。死者数は過去最多の9人となり、統計開始以来最悪の事態となっています。北海道と岩手県でそれぞれ2人、宮城県、秋田県、長野県でそれぞれ1人などが犠牲になりました。
緊急銃猟制度の円滑な運用を推進
木原長官氏は「地域でのクマの出没に関する地方自治体からの情報に注意するなど、引き続き十分な警戒をお願いする」と国民に呼びかけました。特に冬眠前の秋にはクマが活発化するため、山間部への立ち入りには十分な注意が必要です。
「クマ被害が過去最多なんて怖すぎる。山に近い地域の人は本当に気をつけて」
「9人も亡くなってるのに対策が追いついてない。国はもっと本気で取り組むべき」
「緊急銃猟制度ができても、ハンター不足で機能するのか心配だ」
「クマの個体数管理を強化するって言うけど、具体的にどうするのか見えない」
「餌不足でクマが人里に下りてくるなら、根本的な対策が必要じゃないか」
また、2025年9月から始まった緊急銃猟制度について、木原長官氏は「地方自治体への技術的・財政的支援を通じ、円滑な運用を全国に広げていく」と述べました。この制度は改正鳥獣保護管理法に基づき、市町村長の判断で市街地でも銃を使った駆除を可能にするものです。
緊急銃猟制度は、ヒグマやツキノワグマが住居や広場などに侵入またはその恐れがある場合、危害防止が緊急に必要で、銃猟以外で的確かつ迅速な捕獲が困難、かつ住民らに弾丸が当たる恐れがないと市町村長が判断した場合に実施できます。
科学的データに基づく個体数管理
木原長官氏は「科学的データに基づいた上で、クマの捕獲を含めた個体数管理を一層強化するなど、取り組みを総合的に実施する」と強調し、「地方の暮らしと安全を守っていく」と述べました。
2024年4月からクマは特定鳥獣管理計画の対象種に追加され、全国34都道府県で計画的管理が推進されています。環境省の2022年改訂ガイドラインでは、クマ生息域を防除区域や排除区域など4ゾーンに区分し、居住域周辺では必要に応じて捕獲を行う方針が示されています。
クマ出没件数も深刻で、2025年4月から7月のクマ出没情報は全国合計1万704件に上り、前年同期を上回りました。同期間までの許可捕獲数も2471頭と報告されており、クマ被害抑制のため各地で多数の個体が駆除されています。
近年のクマ被害増加の背景には、餌となるブナの実やドングリの凶作があります。東北地方などでは2025年もブナの実の大凶作が見込まれており、クマの出没がさらに増える可能性が指摘されています。
また、過疎化による耕作放棄地の増加や、ハンターの高齢化と担い手不足も深刻な問題です。狩猟免許を持つハンターの平均年齢は60歳を超えており、緊急銃猟制度が機能するための人材確保が課題となっています。
環境省は自治体向けに研修や事例の共有を行い、財政支援などを通じて円滑な運用に努めるとしています。東京海上日動火災保険は自治体向けに緊急銃猟時補償費用保険を開発し、発砲に伴う第三者の財物損害などへの対応を支援しています。
住民の安全確保と森林環境保全の両立、捕獲したクマの有効利用など、様々な課題が絡み合った複雑な問題です。科学的モニタリングに基づく適応的管理が求められています。