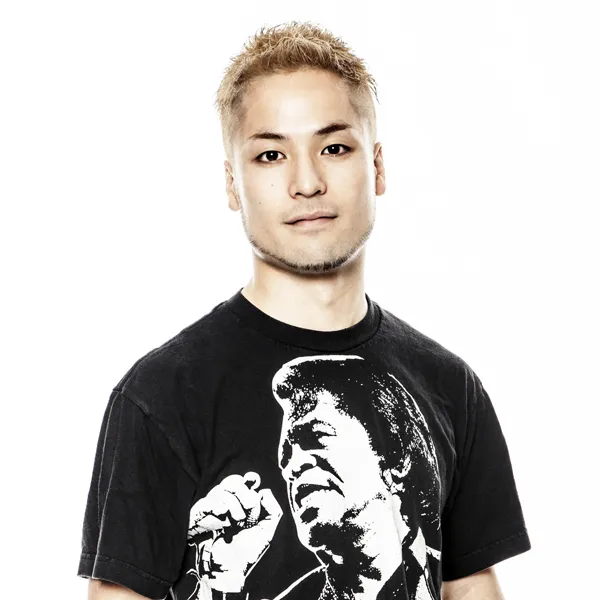2025-07-15 コメント投稿する ▼
長野県が外国人受け入れ加速へ「多文化共生推進本部」設置 知事主導で本格始動、懸念の声も
外国人材の受け入れを「人手不足対策」として進める政府方針に呼応するかたちだが、住民の間では「制度の整備なくして共生は成り立たない」との慎重論も出ている。 長野県としては「多文化共生」は移民政策とは異なると説明しているが、住民感情としては“実質的な移民受け入れ”との認識が根強い。
外国人県民1.5倍に増加 長野県が“共生”を本格推進
長野県は、在留外国人が過去10年で約1.5倍の約4.7万人に増加していることを受け、「多文化共生推進本部」を新たに設置し、県として外国人政策の本格展開に乗り出した。7月17日には第1回となる会議を開催予定で、阿部守一知事が自ら本部長に就任し、県の各部局を横断して施策を連携・統括する。
この本部は、外国人の生活・教育・労働などにおける課題を部門ごとに拾い上げ、県として「共生社会の推進」を目指すための組織。外国人材の受け入れを「人手不足対策」として進める政府方針に呼応するかたちだが、住民の間では「制度の整備なくして共生は成り立たない」との慎重論も出ている。
「“共生”って言うなら、日本人の不安にもちゃんと向き合って」
「外国人が悪いわけじゃない。でも制度が追いついてない」
「教育現場がもうパンクしてる。現場の声も聞いて」
「ただの人手不足の穴埋めにならないようにしてほしい」
「県民の理解と納得を得られる進め方じゃないと反発生むよ」
「共生」理念と現場のギャップ──求められるのは制度の実効性
会議では、「県内の外国人数の状況」「共生施策の現状と課題」「各分野に関する現状と取り組み」が主な議題となる見通しだ。だが、住民サービスの現場では、すでに「日本語支援」「通訳不足」「行政対応の限界」「治安や文化摩擦」といった問題が噴出している。
例えば教育現場では、日本語を理解できない外国籍の子どもが年々増え、教員の負担が急増している。医療や福祉分野でも、制度理解の不足や手続きの煩雑さからトラブルが発生しやすくなっており、「受け入れありき」の政策に対する疑念も広がっている。
「移民政策ではない」では通じない時代へ
長野県としては「多文化共生」は移民政策とは異なると説明しているが、住民感情としては“実質的な移民受け入れ”との認識が根強い。労働力不足を背景に外国人受け入れが拡大する中で、国も地方も「制度整備」と「住民との対話」が決定的に不足しているとの指摘が増えている。
知事が本部長を務めることで、トップダウンによる迅速な対応は期待されるものの、地域住民との温度差や摩擦を解消するには、表面的な“共生スローガン”では不十分だ。
「誰のための政策か」──県民合意こそが鍵
外国人を支援する体制の整備が進む一方で、「その費用や負担は誰が担うのか」「本当に県民の生活にプラスになるのか」という問いが置き去りになっている。
人手不足の解消、地域の多様性推進、国際的な評価向上──それらは確かに重要だが、それを支える“受け入れる側の理解と納得”がなければ、共生は成立しない。むしろ、不信と分断を生むリスクが高まる。
今、必要なのは、「なぜ外国人受け入れを進めるのか」「県民にとってどういう利益があるのか」を丁寧に説明し、共に築く仕組みをつくること。理念先行の政策では、いずれ制度疲労と反発に直面する。