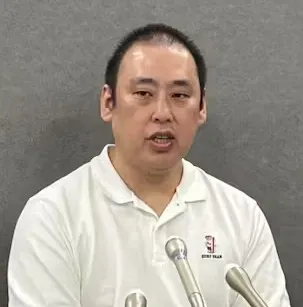2025-08-25 コメント投稿する ▼
渋谷区がふるさと納税返礼品に「ゲーム内通貨」導入 金券競争再燃の懸念も
渋谷区がゲーム内通貨をふるさと納税返礼品に 「金券競争」再燃の懸念も
東京都渋谷区は25日、IT大手MIXIと連携し、同社が運営する人気ゲーム「モンスターストライク(モンスト)」や「共闘ことばRPGコトダマン」で利用できるゲーム内通貨をふるさと納税の返礼品として提供開始した。寄付額1万円、3万円、5万円のコースに応じて、寄付額の3割に相当するゲーム内通貨がシリアルコードで付与される仕組みだ。
渋谷区は「ゲーム関連企業が集積する渋谷の特色を活かした新しい形の返礼品」と説明しているが、金銭との類似性が高いゲーム内通貨が返礼品として認められれば、過去に問題となった「金券競争」が再燃しかねないとして波紋を呼んでいる。
ふるさと納税と金券規制の経緯
ふるさと納税は本来、地域の特産品や地場産業を支援する制度として始まった。しかし一時期、アマゾンギフト券など換金性の高い金券を返礼品にする自治体が相次ぎ、過当競争が問題化。総務省は金券の取り扱いを禁止し、返礼率も3割に制限した。
その後も各自治体は独自色を出そうと競い合い、NFT(非代替性トークン)や旅行券、地域通貨などが返礼品として扱われるケースも見られた。特にNFTやデジタル資産を巡るブームでは投機的利用が問題視され、規制強化の動きが強まった経緯がある。
渋谷区・MIXIの狙いと課題
渋谷区にとって、今回の施策は「エンターテインメントの街」としての発信力を強める狙いがある。MIXI側も「総務省による審査認定を経て正式に決定した取り組み」として透明性を強調している。
しかし、ゲーム内通貨は事実上「電子マネー」や「金券」に近い性質を持つ。返礼品として認められれば、全国の自治体が再び寄付を集めるために「デジタル通貨競争」に走る可能性が高く、制度の趣旨を逸脱する恐れがある。ネット上でも反応は分かれている。
「渋谷らしい返礼品で面白い」
「ゲーム通貨は実質ギフト券と同じでは」
「また金券競争に逆戻りするのでは」
「地域の魅力発信どころか制度の抜け穴だ」
「ふるさと納税の本来の趣旨を見失っている」
規制強化の動きと制度の持続性
総務省は10月からふるさと納税に関する規制をさらに強化する方針で、ポイント付与の禁止や「地場産品基準」の厳格化を打ち出している。デジタル空間で消費されるゲーム内通貨が返礼品に加われば、過去の「金券バブル」と同様に寄付競争が再燃する可能性は否定できない。
ふるさと納税は本来、地域経済や地場産業の活性化を目的とする制度だ。渋谷区の取り組みは都市の特色を打ち出す一方で、「地域の産品」という枠組みをどう解釈するかという根本的な議論を突きつけている。今後、国がどのような線引きを行うかが焦点となりそうだ。
ふるさと納税返礼品に広がる「金銭類似品」問題
ゲーム内通貨を返礼品とする今回の事例は、ふるさと納税制度が抱える構造的な矛盾を象徴している。制度の本来目的と寄付競争のバランスが崩れれば、ふるさと納税そのものへの国民の信頼を損なう危険性もある。
渋谷区の試みが「新しい地域発信」として定着するのか、それとも「金券競争の再来」として規制対象となるのか。今後の展開は制度の未来に直結する注目点となる。