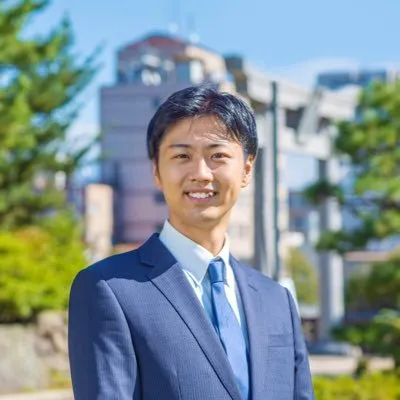2025-05-23 コメント投稿する ▼
AIで子どもの心は救えるか?こども家庭庁のいじめ・不登校対策に現場から疑問の声
こども家庭庁が公表した中間報告によれば、いじめや不登校に悩む子どもたちが気軽に相談できるよう、AIやSNSを活用した新たな相談窓口の拡充を目指す方針だという。 こども家庭庁は「時間や場所を選ばず悩みを話せる環境を整える」と強調しているが、それは裏を返せば、子どもが人と面と向かって話す機会を失いかねないという懸念にもつながる。
「AIで子どもの悩みを救えるのか?」こども家庭庁の方針に疑問の声
こども家庭庁が公表した中間報告によれば、いじめや不登校に悩む子どもたちが気軽に相談できるよう、AIやSNSを活用した新たな相談窓口の拡充を目指す方針だという。しかしこの動きに対し、現場や市民からは「実態を見ていない」「結局は責任の分散」といった批判が相次いでいる。
今回の報告は、小中学生へのヒアリングを基に作成されたという。報告書では「深夜は電話対応しかなく、部屋がない子には使いづらい」との声や、「AIは否定せずに聞いてくれるので話しやすい」といった感想が紹介されている。しかし、これは一部の事例に過ぎず、実際には対人関係に悩む子どもにとってAIやチャットでの相談が本当に有効なのかという根本的な疑問が残る。
SNS相談とAI対応、頼りすぎが生む“孤独”の加速
こども家庭庁は「時間や場所を選ばず悩みを話せる環境を整える」と強調しているが、それは裏を返せば、子どもが人と面と向かって話す機会を失いかねないという懸念にもつながる。AIがどれだけ応答できても、それは“会話”ではない。子どもが感じる疎外感や孤独感に、果たしてAIがどこまで応えられるのか。
実際、現場では支援体制そのものが人手不足の状態が続いている。教員やスクールカウンセラーは対応に追われ、相談員の研修や配置も追いついていない。そこに新たな仕組みを“デジタルで”導入するという方針は、問題の本質をかえって見えにくくしているという指摘もある。
ネットユーザーの反応にも厳しい意見
SNS上でもこの取り組みに対しては懐疑的な意見が多く見られる。
「相談って“話を聞いてもらった”という実感が必要。AIはその代わりになるの?」
「また責任の所在が曖昧になる仕組みを作るんだね。問題はそこじゃない。」
「困ってるのは“人手”であって、“技術”じゃないよ。」
「代理店が儲かるだけ。ズブズブなんじゃ?」
「結局、“対応しました”ってアリバイ作りじゃないの?」
「この間AI途中でポシャって税金ドブに捨ててましたよね?」
これらの意見に共通するのは、テクノロジーに頼るよりも、まずは人と人とのつながりを重視するべきだという現場目線の訴えだ。
本当に必要なのは“顔の見える支援”
AIやSNSの導入はあくまで補助的な手段であり、メインの支援体制は“人”が担うべきである。相談しやすい環境を作ることは重要だが、それは無機質なチャットボットではなく、信頼できる大人としっかり向き合える場であるべきだ。
また、制度の整備と並行して、学校や地域の相談窓口の人的リソースを拡充し、定期的なフォローアップが可能な仕組みも必要不可欠である。こども家庭庁が掲げる方針は、善意を前提とした理想論にすぎず、今ある問題を解決できる即効性のある対策とは言い難い。