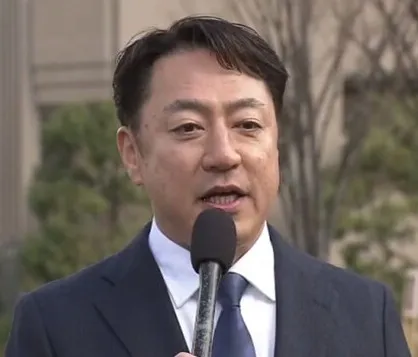2025-08-26 コメント投稿する ▼
米軍無人機MQ9が嘉手納基地で無期限展開へ 沖縄の反発と中国抑止の狭間
南西諸島地域での監視態勢強化は日本政府にとっても安全保障上の課題とされ、情報収集や警戒監視能力の向上を目的にMQ9の常駐が打ち出された。 近年は米国が中国やロシアを念頭にインド太平洋地域で展開を強化しており、沖縄はその拠点のひとつとして位置づけられている。 一方で、沖縄県にとっては基地負担の固定化に直結する。
米軍無人機MQ9、沖縄で無期限展開へ
米海兵隊が嘉手納基地(沖縄県嘉手納町など)に一時展開していた無人偵察機MQ9について、当初予定されていた「1年間の期間限定」から「期限を設けない無期限展開」へ切り替える方針を固めた。防衛省沖縄防衛局は27日、沖縄県に正式に伝達する予定だ。沖縄ではすでに無人機の恒常的な展開が進んでおり、地元住民や県側の反発が避けられない情勢となっている。
米側が展開を決めた背景には、中国が東シナ海や太平洋で海洋進出を強める動きがある。南西諸島地域での監視態勢強化は日本政府にとっても安全保障上の課題とされ、情報収集や警戒監視能力の向上を目的にMQ9の常駐が打ち出された。最大で6機が展開する見込みだ。
MQ9の性能と軍事的意味
MQ9は全幅約20メートル、全長約11メートルの大型無人機で、航続距離は約8500キロに及ぶ。長時間の飛行が可能で、海洋監視や偵察に優れ、遠隔操作で高精度の映像や情報を収集できる点が強みだ。近年は米国が中国やロシアを念頭にインド太平洋地域で展開を強化しており、沖縄はその拠点のひとつとして位置づけられている。
防衛省の資料によれば、MQ9の常駐により日本の自衛隊との情報共有も一層強化される見通しだ。南西地域は台湾有事や尖閣諸島を巡る緊張が高まる中で「最前線」となっており、米軍の監視力増強は抑止力の観点から歓迎する声もある。
沖縄の反発と住民感情
一方で、沖縄県にとっては基地負担の固定化に直結する。嘉手納基地は国内最大規模の米空軍基地であり、これまでにも騒音や環境負荷、事件・事故への懸念が絶えない。今回の「無期限展開」は事実上の常駐化を意味し、県民からは反発の声が上がるとみられる。
SNS上でもさまざまな意見が出ている。
「結局、期限付きなんて口約束で、常駐化が狙いだったのでは」
「中国への抑止は理解できるが、沖縄ばかりに負担を押し付けるのは不公平」
「騒音や事故リスクが増える中で、地元への説明は十分なのか」
「安全保障は必要でも、沖縄の人権や生活が犠牲になっている」
「国防のためと言いながら、実際は米軍の戦略に組み込まれているだけ」
日本の安全保障と地域の葛藤
政府は中国の海洋進出や台湾情勢の不安定化を踏まえ、南西地域の防衛力強化を急いでいる。石破茂政権下でも「日米同盟を軸にした抑止力の確保」が明確に打ち出されており、今回の米軍無人機常駐はその一環と位置づけられる。ただし、日本全体での負担の公平性や、沖縄に集中する基地依存の構造は依然として解消されていない。
今後、沖縄県と防衛省の協議は難航が予想される。県民感情に配慮しないまま進めれば、さらなる不信感を招き、日米同盟への支持基盤を揺るがしかねない。日本の安全保障と沖縄の地域社会との調和をどう図るかが、今後の最大の課題となる。
沖縄嘉手納基地での無人機常駐化が示す日米安保の現実
今回の決定は、単なる装備展開の枠を超え、日米安保の現実を象徴している。米軍は中国を念頭に抑止力を高め、日本政府はそれを追認する一方で、沖縄県民の負担は増す。透明性ある説明と責任ある議論が求められているが、その道筋は見えていない。沖縄の無人機常駐化は、今後の日本の防衛政策と地域社会の在り方を問う大きな分岐点になるだろう。