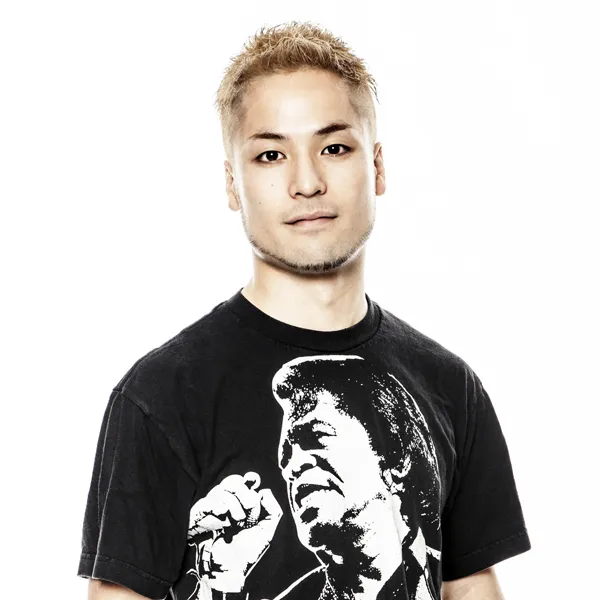2025-10-03 コメント投稿する ▼
太陽光発電と希少種保全 政府が「種の保存法」検討会を設置へ
浅尾慶一郎環境相は2025年10月3日の閣議後記者会見で、太陽光発電施設の建設による生態系や景観への影響に対応するため、種の保存法の在り方を議論する検討会を新たに設置すると発表した。 希少種保全や流通規制の課題が指摘されており、今回はさらに再生可能エネルギー開発との衝突が焦点に加わる。
太陽光発電施設と希少種保全 政府が検討会を設置
種の保存法見直しに向けた動き
浅尾慶一郎環境相は2025年10月3日の閣議後記者会見で、太陽光発電施設の建設による生態系や景観への影響に対応するため、種の保存法の在り方を議論する検討会を新たに設置すると発表した。第1回は10月中旬に開催予定で、2026年5月ごろに報告書案を示す見通しである。
種の保存法は絶滅の恐れのある野生生物を保護する法律で、2017年の改正法に基づき評価会議が行われてきた。希少種保全や流通規制の課題が指摘されており、今回はさらに再生可能エネルギー開発との衝突が焦点に加わる。
「環境に優しいはずの再エネが逆に自然を壊している」
「釧路湿原や里山を壊してまでパネルを並べる意味があるのか」
「希少動植物の保護は地域の誇りでもある」
「再エネ推進と自然保護を両立させる仕組みが必要だ」
「選挙が近づくと自民党の議員や閣僚が急に働き出す」
SNS上では、開発と自然保護の矛盾に加え、政治家の姿勢を揶揄する声も広がっている。
太陽光発電と生態系の衝突
大規模太陽光発電所(メガソーラー)は山林や湿地を造成することが多く、伐採や地形改変によって生態系が損なわれる懸念が大きい。北海道の釧路湿原周辺では希少種の生息環境への影響が指摘され、九州や中部の里山では景観破壊や土砂災害リスクが問題視されている。
浅尾環境相は「全国で太陽光発電施設の建設による希少種への影響が課題となっている。野生動植物の生息環境を適切に保全できるよう取り組む」と強調した。
調整の難しさと政策課題
再生可能エネルギーは温室効果ガス削減の柱とされるが、開発偏重では地域社会の理解を得られない。これまでの政策は発電量や投資効率を優先しがちで、住民合意や環境保全が軽視されてきた。今回の検討会は、開発と保護をどう調整するかが試金石となる。
企業の利益優先で乱開発が進めば「国民ではなく企業のための政治」との批判が強まる。国民に根拠を示し、説明責任を果たすことが不可欠だ。
今後の展望
検討会では専門家や自治体関係者を交え、希少種や景観への影響を事前評価し、回避・軽減を制度化する方策を議論する。自然を守りつつエネルギー政策を進めるためには、選挙向けのパフォーマンスではなく、持続的かつ透明性ある制度設計が求められる。