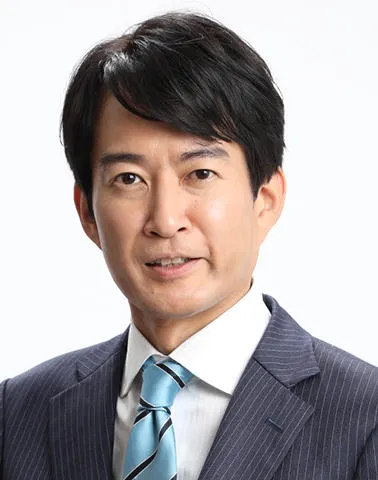2025-09-30 コメント投稿する ▼
後期高齢者の医療費「配慮措置」終了で窓口負担増、310万人影響
75歳以上の後期高齢者で医療費窓口負担が2割となる人を対象に設けられていた「配慮措置」が、9月30日で終了しました。 ただし急激な負担増を避けるため、外来負担増は月3000円までとする特例が運用されてきました。 しかし10月以降は2割にあたる1万円の自己負担が必要になり、2000円の増加となります。 ただし高額療養費制度があるため、月の窓口負担は最大でも1万8000円に抑えられます。
後期高齢者医療費「配慮措置」終了で負担増
75歳以上の後期高齢者で医療費窓口負担が2割となる人を対象に設けられていた「配慮措置」が、9月30日で終了しました。これにより、10月1日からは外来受診の窓口負担が増えるケースが出てきます。
この制度は3年前の改正で導入されたもので、単身世帯で年収200万円以上、複数世帯で年収320万円以上の後期高齢者は、従来1割だった窓口負担が2割に引き上げられました。ただし急激な負担増を避けるため、外来負担増は月3000円までとする特例が運用されてきました。
具体的な負担の変化
例えば、医療費が月5万円の場合を考えます。これまでは1割の5000円に3000円を加えた8000円が上限でした。しかし10月以降は2割にあたる1万円の自己負担が必要になり、2000円の増加となります。
厚生労働省は影響を受ける人を全国で約310万人と試算しており、1人あたり年間で平均9000円程度の負担増になると見込んでいます。ただし高額療養費制度があるため、月の窓口負担は最大でも1万8000円に抑えられます。
制度全体への効果
一方で、この変更により現役世代の保険料負担は年間でおよそ240億円軽減されるとされています。制度を維持するためには高齢者側の一定の負担増を不可避とする考え方が背景にあります。
厚生労働省は「制度の持続可能性を確保するため、今後も世代間で能力に応じて支え合う仕組みを議論していく」とコメントしました。政府が掲げる「全世代型社会保障」の一環と位置づけられています。
議論の焦点と今後
今回の措置終了は、国民にとっては「負担増」と「制度維持」の両面を含む判断です。高齢者にとっては日々の外来医療での負担感が増す一方、現役世代にとっては保険料負担が軽くなる形となります。
医療財政の持続可能性をどう確保するか、また高齢者と現役世代の負担をどこまで調整するかが今後の焦点となります。議論次第ではさらなる制度改正につながる可能性もあります。