2025-09-05 コメント投稿する ▼
介護処遇改善加算の取得率95.3% サービス間格差と賃金底上げの課題
大規模で人員が比較的安定している施設型サービスでは上位加算が取りやすい一方、小規模事業所では体制整備に必要な人員確保が難しく、結果として下位区分の取得にとどまっている。 介護サービスの持続性を確保するためには、制度の細かな設計だけでなく、全体としての賃金底上げが求められている。 処遇改善加算の取得率が9割を超えていることは、制度が介護現場に浸透している証左である。
処遇改善加算の取得状況と全体像
厚生労働省は5日に開催した社会保障審議会・介護給付費分科会で、介護報酬の「処遇改善加算」の最新データを報告した。今年4月時点の取得率は全体で95.3%と、ほぼ全ての介護事業所が加算を取得している状況が示された。
区分別では、最上位の「加算Ⅰ」が44.6%、「加算Ⅱ」が36.6%で、両者を合わせると全体の81.2%を占める。前年6月から新設された一本化制度の下で、旧来の加算Ⅴは4月で廃止されており、要件の弾力化も適用されている。こうした制度改正が、上位区分への移行を後押ししているとみられる。
「加算を取らなければ人材確保ができない状況になっている」
「現場にお金が回る仕組みをさらに強化すべき」
「格差が広がると、特定のサービスに人材が集中してしまう」
「介護職員の賃金水準が全産業と比べて低すぎる」
「一律の改善でなく、現場の実情に合わせた柔軟な制度が必要だ」
サービス別にみる格差
データをサービス別に分析すると、加算Ⅰの取得率に大きな差がある。特別養護老人ホームでは79.1%と約8割が取得しているが、訪問介護(39.5%)、通所介護(39.2%)、グループホーム(33.0%)では4割を下回る。特に地域密着型通所介護では23.9%と低水準にとどまっている。
この背景には、職員配置基準や事業所規模の違いがある。大規模で人員が比較的安定している施設型サービスでは上位加算が取りやすい一方、小規模事業所では体制整備に必要な人員確保が難しく、結果として下位区分の取得にとどまっている。制度設計の公平性が改めて問われる状況といえる。
介護職員の賃金と全産業平均との差
厚労省の提示した統計によれば、介護職員の平均月収は30.3万円。全産業平均の38.6万円と比べると8.3万円の差がある。この賃金格差は長年の課題であり、離職率の高さや人材不足の主要因ともされてきた。処遇改善加算の拡充によって改善の兆しはあるが、依然として他産業との格差は埋まっていない。
審議会でも委員から「さらなる処遇改善が必要」との声が相次いだ。介護サービスの持続性を確保するためには、制度の細かな設計だけでなく、全体としての賃金底上げが求められている。
今後の課題と展望
処遇改善加算の取得率が9割を超えていることは、制度が介護現場に浸透している証左である。しかし、サービスごとの格差や賃金水準の低さは依然として深刻な課題だ。特に在宅系サービスで取得が進まない現状は、地域包括ケアの実現に逆行する懸念がある。
また、加算取得による賃金改善が必ずしも全額職員に還元されていないとの指摘も存在する。制度の実効性を高めるには、透明性を確保し、改善効果を国民に明確に示す必要がある。
高齢化が進む中、介護職員の安定確保は社会保障制度全体の持続性を左右する。処遇改善加算がその切り札となるためには、事業所間格差の是正と、他産業並みの賃金水準を目指した抜本的対策が不可欠だ。
介護処遇改善加算の格差是正と賃金底上げの必要性
今回のデータは、介護現場の努力と制度の定着を示すと同時に、解決すべき課題を浮き彫りにしている。加算取得が進む一方で、在宅サービスや小規模事業所の取り残しをどう支えるか。介護職員の生活を安定させるために、さらなる賃金改善が求められている。制度が真に現場と利用者のために機能するかどうかが、これからの大きな分岐点となる。
















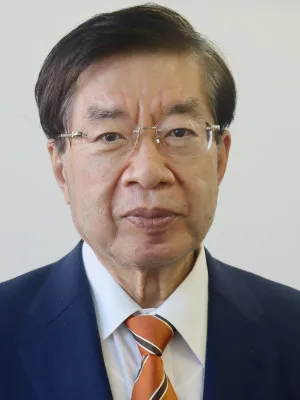















![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)
