2025-09-03 コメント投稿する ▼
新型コロナ後遺症支援の利用は1割のみ 厚労省調査で判明、制度周知不足と利用難が課題
新型コロナ後遺症支援の利用はわずか1割、厚労省が詳細調査を公表
厚生労働省は3日、新型コロナウイルス感染後に長く続く後遺症について、支援制度を利用した人が1割にとどまるとの調査結果を発表した。感染から1年以上経過しても疲労感や倦怠感などの症状が残る人を対象に行われた追跡調査で、制度の周知不足や利用しにくさが改めて浮き彫りとなった。
調査は同省研究班が2024年11月から2025年1月にかけて実施。それ以前に調査へ協力した札幌市と大阪府八尾市の住民にアンケートを送付し、計約1万3千人から回答を得た。その結果、1年以上後遺症が続いていた人のうち、何らかの支援を受けたと回答した割合は両市で約1割にすぎなかった。
最も多く利用されたのは傷病手当
利用した支援の内容は「傷病手当」が最多で、ほかに「労災保険」「高額療養費制度」「精神障害者保健福祉手帳」などがあった。だが、多くの人は制度の存在を知らなかったり、申請が複雑で利用を諦めたりした可能性があるとみられる。
ネット上でもこの結果を受け、多くの反応が見られた。
「制度があるのに使われていないのは周知不足だ」
「1割しか支援を受けていないなんて驚き」
「疲労や倦怠感は目に見えにくく理解されにくい」
「申請手続きが面倒で諦めた人も多いのでは」
「行政はもっと情報発信を強化してほしい」
後遺症の持続率と症状の傾向
感染から時間が経過するにつれて、後遺症を訴える人の割合は減少した。感染から2年後も症状が続いていると答えた人の割合は、成人では八尾市で3.5%、札幌市で7.2%。子供は八尾市0.3%、札幌市0.8%にとどまった。
成人では疲労感や倦怠感、睡眠障害、呼吸困難が多く報告され、子供では頭痛や集中力の低下が目立った。学業や仕事への影響が長期化する例もあり、個人や家族の生活に深刻な負担を与えている。
海外の取り組みとの比較と日本の課題
海外では、長期にわたる後遺症への対応が進んでいる。英国では「ロングCOVIDクリニック」が各地に設置され、症状に応じて多職種の医療者が連携して支援にあたる。米国でもリハビリや心理的サポートを含む包括的なプログラムが整備されつつある。
一方、日本では既存の制度を組み合わせて対応しているが、利用率の低さからも分かる通り十分に機能しているとは言い難い。支援の存在を周知し、申請を簡素化するなど制度を実際に「使えるもの」にする必要がある。
新型コロナ後遺症と支援策の今後
調査結果は、後遺症の症状自体は時間とともに減少するものの、一部の人にとっては生活を長期にわたり制限する深刻な課題であることを示している。にもかかわらず、制度利用は限定的であり、支援が必要な人に十分届いていない。
今後は、後遺症の実態をさらに把握し、医療・生活支援を組み合わせた長期的かつ包括的な対策を講じることが重要だ。後遺症患者が孤立せず、社会参加を続けられる環境を整えることが、行政と地域社会に求められている。
新型コロナ後遺症支援の利用率1割、厚労省調査が示す課題
厚労省の調査で、新型コロナ後遺症で支援を利用した人は1割にとどまることが判明。症状は成人・子供ともに生活に影響を与え、制度の周知不足と申請の複雑さが課題となっている。























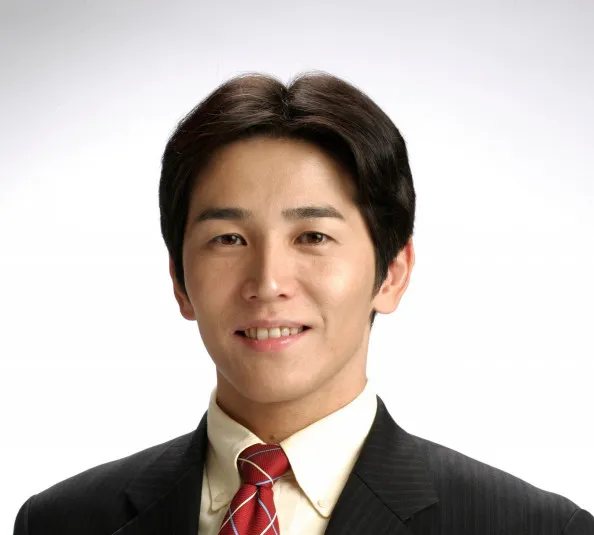










![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)