2025-08-29 コメント投稿する ▼
長生炭鉱の人骨「戦没者遺骨収集の対象外」 福岡厚労相、法的枠組みの限界示す
山口県宇部市の長生炭鉱坑道で見つかった人骨について、福岡厚生労働大臣は29日の閣議後会見で「関係省庁と連携して適切に対応していきたい」と述べる一方、戦没者遺骨収集推進法に基づく遺骨収集の対象には該当しないとの認識を示した。 市民団体は近年「歴史的責任を明らかにすべきだ」として潜水調査を継続しており、今回の人骨発見は大きな節目となった。
福岡厚労相「長生炭鉱の人骨は遺骨収集対象外」
山口県宇部市の長生炭鉱坑道で見つかった人骨について、福岡厚生労働大臣は29日の閣議後会見で「関係省庁と連携して適切に対応していきたい」と述べる一方、戦没者遺骨収集推進法に基づく遺骨収集の対象には該当しないとの認識を示した。
長生炭鉱では戦時中、1942年に水没事故が発生し、183人が犠牲となった。市民団体が昨年から潜水調査を実施しており、今月ダイバーが坑道で骨のようなものを発見。警察が鑑定した結果、人骨と確認された。
福岡厚労相は「炭鉱の安全性や潜水調査の実施可能性の観点から、専門的知見を収集している」と述べ、今後も関係省庁と連携する方針を示した。
「183人もの命が奪われたのに対象外とは納得できない」
「遺骨収集は国の責務ではないのか」
「労働者だから外すというのは線引きが冷たすぎる」
「戦争の犠牲者であることに変わりはない」
「国益や歴史教育の観点からも対応が必要だ」
「戦没者」の定義と対象外の理由
戦没者遺骨収集推進法は「今次大戦により沖縄、硫黄島などで死亡した戦没者の遺骨収容」と定義している。長生炭鉱事故で亡くなったのは徴用された労働者らであり、戦闘行為に直接関わったものではないため、同法の適用外とされる。
しかし、事故の背景には戦時体制下の過酷な労働環境があり、「戦争による犠牲」という側面は否定できない。厚労相の説明は法令上は正しいが、社会的・歴史的に妥当かどうかは議論を呼んでいる。
歴史的背景と市民運動
長生炭鉱は旧日本海軍の要請で増産を強いられ、朝鮮半島出身者を含む多くの労働者が過酷な条件で働かされた。1942年の水没事故では183人が死亡し、坑内に多くの遺骨が残されたままとなってきた。
市民団体は近年「歴史的責任を明らかにすべきだ」として潜水調査を継続しており、今回の人骨発見は大きな節目となった。しかし、国の法制度上は遺骨収集の枠組みに入らないため、国費による本格調査や身元特定が困難となっている。
国の責任と今後の課題
今回の厚労相発言は、国の法制度と歴史的責任の狭間にある問題を浮き彫りにした。戦時中の労働者犠牲者が法的には「戦没者」に含まれない一方、犠牲の実態を放置すれば国の姿勢が問われる。
国民が求めているのは、給付金のような一時的対応ではなく、歴史的責任を踏まえた明確な方針だ。遺骨収集や歴史継承は「国益」にも直結する課題であり、政府は透明性ある説明を行い、必要なら制度改正も検討すべきだろう。



























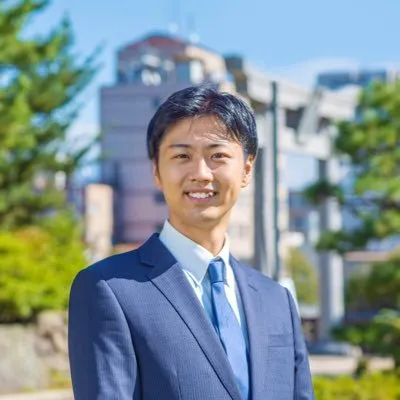

![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)


