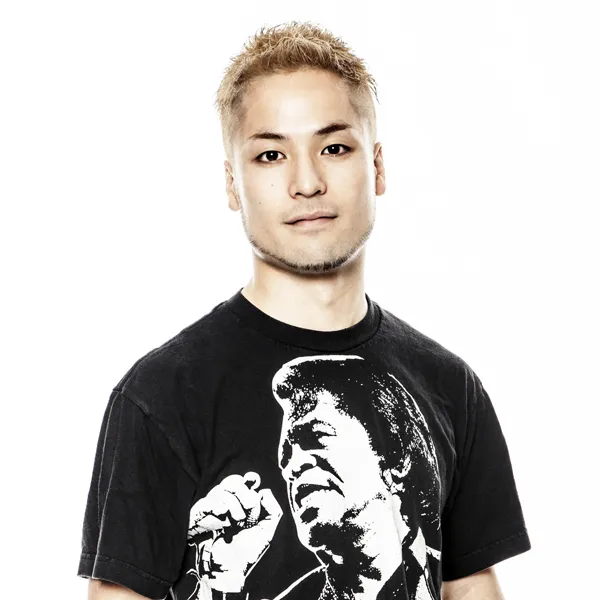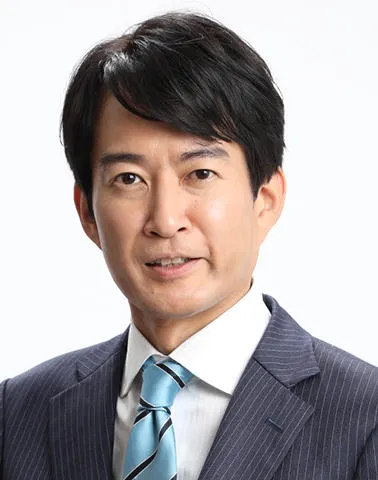2025-07-18 コメント投稿する ▼
政党交付金78億円を9党に配分 自民党が34億円、立憲20億円 共産党は辞退
交付金は年4回に分けて支払われる制度となっており、各党の国会議員数と過去の国政選挙(直近の衆院選と過去2回の参院選)の得票数に基づいて金額が決まる。 比較的新しい政党であるれいわ新選組には約2.3億円、参政党には約1.3億円、日本保守党には約4300万円が交付された。 一方、制度そのものに反対している共産党は、今回も交付金の受け取りを辞退している。
政党交付金、第2回分として78億円超を9党に交付 自民34億円、立憲20億円 参院選後に再算定へ
総務省が政党交付金を分配 9党に78億円超、自民が最多34億円
総務省は7月18日、2025年分として2回目となる政党交付金を9つの政党に総額78億8413万円交付した。交付金は年4回に分けて支払われる制度となっており、各党の国会議員数と過去の国政選挙(直近の衆院選と過去2回の参院選)の得票数に基づいて金額が決まる。7月20日に投開票を迎える参議院選挙の結果を受けて、今後の配分額は再算定される予定だ。
最も多くの交付を受けたのは、自民党で34億円余り。以下、立憲民主党が20億円強、日本維新の会が8億円余、公明党が約6.6億円、国民民主党が約4.9億円と続いた。比較的新しい政党であるれいわ新選組には約2.3億円、参政党には約1.3億円、日本保守党には約4300万円が交付された。社民党にも7000万円超が支払われた。一方、制度そのものに反対している共産党は、今回も交付金の受け取りを辞退している。
交付金の根拠は議席数と得票 選挙結果が直結する仕組み
政党交付金制度は、企業・団体献金に依存しない政治資金の透明性確保を目的に、1995年に導入された。国会議員5人以上の政党、あるいは直近の国政選挙で一定の得票数を得た政治団体が対象となる。
交付額は毎年1月1日時点の国会議員数、直近の衆院選と参院選2回分の得票数に基づいて総額が計算されるため、選挙結果が反映されるのは翌年以降となる。ただし、選挙実施の年には暫定的に計算された金額が交付されたのち、選挙後の確定データを基に再算定される仕組みだ。
今回の交付額も、20日の参院選の結果を踏まえて再調整される予定であり、新人政党や勢力を伸ばした政党には増額の可能性がある一方、議席を減らせば減額も免れない。
税金からの支出に批判も 制度の是非が改めて問われる
政党交付金は国民の税金から支出されているため、制度そのものへの是非を問う声も根強い。とりわけ、「既成政党の延命策ではないか」「交付金の使い道が不透明」といった疑問は繰り返し提起されており、共産党が制度への反対姿勢を貫いているのも、そうした批判を背景にしたものだ。
SNSでも、交付額が明らかになるたびに納税者の立場から疑問の声が相次ぐ。
「選挙前に税金で78億円って、どう使われてるのか全く見えない」
「政治とカネの問題で騒がれてるのに、平然と交付してるのどうかしてる」
「共産党の“受け取らない”姿勢はブレないよな」
「政党助成金って、要するに国民のカネで政治活動してるってことだよね」
「新党もベンチャーも、まず交付金頼みじゃ健全じゃない」
一方で、企業献金や組織依存から脱却し、政治資金の透明性を確保する手段として制度を評価する声も一定数存在する。問題は、その使途や透明性にあり、政党による適切な説明責任と報告が今後一層求められる。
参院選の結果が交付金を左右 「1票」が政党資金に直結
今回の交付額は選挙前の暫定的なものであり、7月20日の参院選結果によって各党の今後の資金体制も大きく変わる可能性がある。比例代表票や選挙区での得票が、翌年以降の交付金に反映されるからだ。
つまり、有権者の「1票」が政党の資金にも直結していることになる。新たに議席を得た政党は活動基盤を強化する原資を得ることができ、一方で議席を失えば資金面でも後退を余儀なくされる。
政治とカネをめぐる問題が後を絶たない中、政党交付金制度の意義、運用方法、そして透明性に対する注目は、今後ますます高まるだろう。
政党交付金・2025年第2回配分額(単位:円)
自民党:34億988万円
立憲民主党:20億4279万円
日本維新の会:8億230万円
公明党:6億6184万円
国民民主党:4億9481万円
れいわ新選組:2億2919万円
参政党:1億2917万円
社民党:7096万円
日本保守党:4316万円
共産党:受け取り辞退(交付なし)