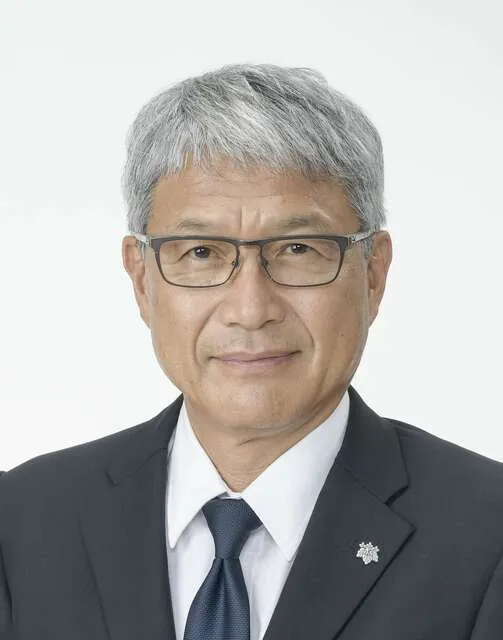2025-08-28 コメント投稿する ▼
神戸市が住宅供給5000戸拡大へ 戸建て中心で人口流出防止を狙う
市内では民間による年間約2500戸の住宅供給があるとされるが、市が宅地を積極的に創出することで供給量を底上げし、人口流出を抑制する狙いがある。 市は年平均500戸分の宅地を確保する見込みで、低利用・未利用の市有地活用、公共施設跡地の利用、民間の遊休不動産の活用などを組み合わせ、合計で5000戸分の宅地供給を進める。
神戸市、2030年までに住宅供給5000戸を上乗せへ
神戸市の久元喜造市長は27日の定例会見で、2030年までに5000戸以上の住宅供給を市として上乗せする方針を明らかにした。市内では民間による年間約2500戸の住宅供給があるとされるが、市が宅地を積極的に創出することで供給量を底上げし、人口流出を抑制する狙いがある。
市は年平均500戸分の宅地を確保する見込みで、低利用・未利用の市有地活用、公共施設跡地の利用、民間の遊休不動産の活用などを組み合わせ、合計で5000戸分の宅地供給を進める。特に戸建て住宅に重点を置き、供給されるうちの半分程度を個人の嗜好に合わせた木造戸建てとする方針だ。
低利用地と公共施設跡地を宅地化
具体的な供給計画では、まず今後5年間で郊外を中心とした低利用・未利用の私有地を売却し、約1000戸分の宅地を提供する。さらに市営住宅の再編や公共施設跡地の活用によって約3000戸分を確保。加えて、民間企業の遊休不動産や里山・農村地域の未利用地を規制緩和などで宅地化し、約1000戸分の宅地を生み出すと見込んでいる。
これらの施策を通じ、市は民間住宅供給に加え、新たに多様な住まい方を提案する。平屋建て、菜園付き、店舗付きといった住宅様式を打ち出し、都市部では難しい暮らしのスタイルを神戸で実現させたい考えだ。
戸建て中心の戦略で人口流出を防ぐ
神戸市はこれまで、三宮周辺など中心部ではタワーマンションを含む大規模住宅開発を規制し、駅前広場整備や郊外居住の促進を進めてきた。今回の施策はその流れを後押しするもので、既存の住宅地や郊外地域に新しい住民を呼び込む狙いがある。
久元市長は「人口減少時代でも新築住宅の需要はある。周辺都市に比べ住宅供給が必ずしも十分でなかった」と指摘し、「多様で良質な住宅の提供が人口減少を緩やかにする」と述べた。市は「都市のスポンジ化」を防ぐため、郊外の住環境整備を柱に据える。
神戸市の住宅供給拡大戦略と今後の焦点
今回の政策は、人口減少と都市縮小への対応策として注目される。市が主体的に宅地を供給することで、民間事業者に住宅開発を促し、供給不足を補う形だ。ただし、市有地の売却や規制緩和には地元合意や景観保全との調整も必要であり、円滑に進められるかが課題となる。
供給される5000戸の半数を戸建てとする方針は、ファミリー層の定住を促す可能性がある一方で、若年層や単身者向けの需要に応えられるかは議論を呼びそうだ。神戸市が「多様で良質な住宅」を掲げる中で、具体的にどのような住環境を提示できるかが、都市の魅力と人口維持の鍵を握る。