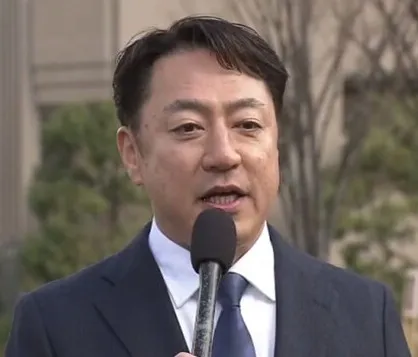2025-07-28 コメント投稿する ▼
長射程ミサイルを熊本に初配備へ 日本が反撃能力を正式保有、専守防衛との整合性に懸念も
防衛省は、国産の長射程ミサイル「12式地対艦誘導弾能力向上型(地発型)」の初期配備先として、陸上自衛隊の健軍駐屯地(熊本市)を選定する方向で最終調整を進めている。 今回の配備は、日本がかねてより議論してきた「反撃能力」の保有に直結する。
長射程ミサイル、熊本に初配備へ 日本が本格的な反撃能力を保有へ
防衛省は、国産の長射程ミサイル「12式地対艦誘導弾能力向上型(地発型)」の初期配備先として、陸上自衛隊の健軍駐屯地(熊本市)を選定する方向で最終調整を進めている。配備時期は2025年度末を予定しており、日本はこのタイミングで事実上「反撃能力(敵基地攻撃能力)」を保有することになる。
この動きは、急速に軍事的プレゼンスを強める中国を南西諸島方面で牽制する狙いがある一方で、憲法上の「専守防衛」の原則との整合性を問う声や、配備先が標的になるリスクに対する懸念も根強く、国内外で議論が高まりそうだ。
健軍駐屯地に初配備 大分・沖縄にも拡大へ
今回配備されるのは、12式ミサイルの改良型のうち、地上発射型の「地発型」。飛距離は約1000キロとされ、九州からでも朝鮮半島や中国沿岸部の一部が射程圏内に入る。運用は、健軍駐屯地を拠点とする第5地対艦ミサイル連隊が担当する。
2026年以降は、大分県の湯布院駐屯地にも同型ミサイルを配備する予定であり、将来的には沖縄県の勝連分屯地への展開も視野に入れている。これにより、南西方面全体でのミサイル防衛網の構築が段階的に進められる見通しだ。
政府関係者は「島嶼防衛の抑止力強化が目的であり、他国を威嚇するものではない」と説明するが、地政学的に対立関係にある国々はこの動きを敏感に受け止める可能性がある。
反撃能力保有は「専守防衛」の転換か
今回の配備は、日本がかねてより議論してきた「反撃能力」の保有に直結する。岸田前政権が打ち出した国家安全保障戦略では、敵基地攻撃能力を含む「反撃能力」の保有が明記されていたが、石破政権下でもこれが着実に実行に移されている格好だ。
一方で、「専守防衛」を掲げてきた日本の防衛方針に対する根本的な転換とも受け止められており、憲法9条の趣旨とどう折り合いをつけるのか、明確な説明が求められている。
市民の間にもさまざまな反応が広がっている。
「攻撃されてからじゃ遅い。必要な装備だと思う」
「結局これって、アメリカの要請じゃないの?」
「自衛のためって言うけど、他国からはどう見えるのか」
「九州が狙われるリスクが高まった気がする」
「戦争の準備より、外交力の強化をしてほしい」
地域の不安と安全保障の狭間で
熊本市をはじめとする九州の住民にとって、長射程ミサイルの配備は「防衛力強化」という安心材料である一方で、ミサイル基地が真っ先に標的となる危険性への不安もぬぐえない。特に健軍駐屯地周辺は住宅地も多く、配備後の安全管理や避難体制についての説明を求める声も高まっている。
政府としては、地域住民との対話を重視しながら、配備による国益や抑止力強化の意義を丁寧に説明していく必要がある。ミサイルの性能や作戦運用の詳細については「機密性の高い情報」として非公表部分も多いため、透明性の確保も問われる。
また、万一の事態に備えた避難計画や、自治体との連携体制の構築も、実際の配備に向けた重要な課題となってくるだろう。
今後の焦点は「使用判断の枠組み」へ
反撃能力の保有とミサイル配備の次に問われるのは、実際にそれを「いつ・誰が・どのように」使うかの判断基準だ。首相の専権事項として一元的に扱うのか、国会承認を要するのか、あるいは米軍との共同判断が前提なのか。使用基準を曖昧にしたままでは、国民の理解も得られにくい。
今回の配備決定は、日本の安全保障政策の大きな転換点となる可能性がある。中国や北朝鮮との緊張が高まる中、日米同盟を軸にした抑止力構築は不可避との見方もあるが、国民の生命と暮らしを守るためには、軍事力の整備だけでなく、それを支える丁寧な民主的プロセスが不可欠だ。