2025-10-13 コメント投稿する ▼
川口クルド人騒動と強制送還の功罪 住民「おとなしくなった」が示す限界
埼玉県川口市では、トルコ国籍のクルド人らが地域で集住する中、近年、コンビニ前での騒音・飲酒・立ちションなどの「迷惑行為」が住民との摩擦を引き起こしているという。 対する国の動きとして、不法滞在者を強制送還する「不法滞在者ゼロプラン」が加速している。
川口市で表面化するクルド人トラブルと強制送還の逆説
埼玉県川口市では、トルコ国籍のクルド人らが地域で集住する中、近年、コンビニ前での騒音・飲酒・立ちションなどの「迷惑行為」が住民との摩擦を引き起こしているという。こうした実態が明るみに出る一方で、政府が推進する「不法滞在者ゼロプラン」によって数十人規模の強制送還が行われ、地域の雰囲気に変化が出始めている。
本稿では、川口市におけるクルド人コミュニティと住民対立の現状を丁寧に追い、政策の効果と限界を浮き彫りにする。
日常を脅かす“目に見えるトラブル”
川口市北部のあるコンビニ隣接の飲食店。20代の従業員は、この春、店内で騒ぐクルド人男性に“やんわり注意”したところ、体当たりされたという。店主は「駐車場に解体トラックを止め、荷台に椅子を置いて飲んだり騒いだりしている」と語る。近隣住民から通報が相次ぎ、警察が一晩に6回駆け付けたケースもあったという。
さらに、十数人でバイクを爆音走行させながら徘徊したり、店内で刃物を購入する者、金属バットを持ち歩く者もいたとの証言も残る。注意を受けると「帰レジャナイ」などカタコトの日本語で抵抗して去っていくという。ある住民は、「注意したら目の前にタバコを投げつけ、『何カ悪イコトシタノカ』と怒鳴られた」と語る。ある家族は「もう限界」として引っ越した。
こうした“目に見えるトラブル”が、住民の不安を加速させている。このような言動が広がれば、住民感情は“異文化・外国人拒絶”へと動いてしまう。
強制送還と地域の“沈静化”の空気
対する国の動きとして、不法滞在者を強制送還する「不法滞在者ゼロプラン」が加速している。法務省・入管当局は、6〜8月期で119人を護送官付きで送還したと明かし、そのうちトルコ国籍者は最多の34人。うち22人は難民申請を3回以上繰り返した者であった。
この中で、川口市で解体工事会社を実質経営し、在留クルド人社会では“リーダー格”とされていた男性(通称 M 氏)が7月、強制送還されたことは象徴的な出来事と捉えられている。彼は2004年来日、難民申請を繰り返したが認められず、不法在留となっていた。支配的な立場でコミュニティに影響を与えていた彼の送還後、「少し静かになった」「おとなしくなった」と住民が感じるケースもあるという。
実際、住民の間に「もう応じられない」というあきらめの空気も広がる中、帰国を自発的に希望する動きも増えつつあると入管側も報告している。
ただし、送還されても再入国を試みる例も確認されており、それが一層の物議をかもしている。
数字で見るクルド人コミュニティと構造変化
川口市内に住民登録されているトルコ国籍者(多くはクルド人と推定される)は、6月末時点で2146人。半年前から60人減少した。うち「特定活動」資格で滞在する者は760人(半年で144人減)、強制送還手続き中の者は707人(41人減)で、全体の約68%が難民申請者と算定されている。
一方で、川口市の減少傾向とは逆に、隣接するさいたま市南区などでクルド人の集合住宅入居が増えているとの指摘もある。また、特定活動や「家族滞在」「日本人の配偶者等」といった正規資格取得者が増えつつあるという点は、“移民化”の動きと指摘されている。
これらの変化を背景に、住民・行政・国家政策の三者が緊張しながら、共生と排除のはざまで揺れている。
制度の限界、政策のジレンマ
川口市での問題は、単なる地域トラブルではなく、国の難民政策・入管制度の硬直性を浮き彫りにしている。日本は難民認定率が極めて低く、申請を繰り返す制度の悪用を許さない仕組みを強めてきた。改正入管法では、難民申請が認められない者に対し、3回目以降は強制送還を認める規定も設けられた(例外あり)との制度改定も進められている。
ただし、こうした政策は、地域社会や人道的観点とのバランスを欠く可能性もある。たとえば、日本で生まれ育った子どもたちは日本語しか話せず、トルコに帰れば生活の基盤がない場合もある。また、クルド人に対する民族的抑圧の議論もあり、強制送還後の安全性への懸念を指摘する声もある。
さらに、こうした地域対立が過度に“クルド人全体”へと一般化され、ヘイト言説を助長する恐れもある。過去には川口市議会が「一部外国人による犯罪の取り締まり強化」を求める意見書を可決し、それを機に偏見や誤情報が拡散した歴史もある。
地域住民の声を無視できないことは明らかだ。しかし、反発ばかりを政策根拠にすれば、法の支配と公正原則を損なう。国家は決して「住民の嫌悪感」をそのまま政策に昇華させてはならない。
排除でなく制度改革こそが本質
川口市の事例は、「移民」「共生」「排除」の葛藤が凝縮された場だ。迷惑行為を許すわけにはいないが、ただ送還を強めればすべてが解決するわけでもない。
国家は、厳格な入管運用と同時に、制度的な道筋を示すべきだ。たとえば、仮放免者や難民申請中の外国人に対して、就労や社会参加の合理的な枠を与える「監理措置」の柔軟化、適正な手続きの透明化、日本で育った子どもや家族を切り捨てない道を検討すべきだ。
また、住民側にも過剰な不安やステレオタイプにとらわれず、事実に即した議論を成熟させる責任がある。外部からの過剰報道・SNSの誇張も、地域を分裂させる火種になりかねない。ヘイトを乗り越え、法と人間性を伴う共生を模索することが最も困難だが、最も正しい道だ。





























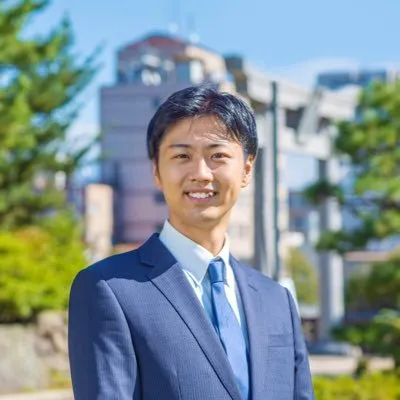


![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)

