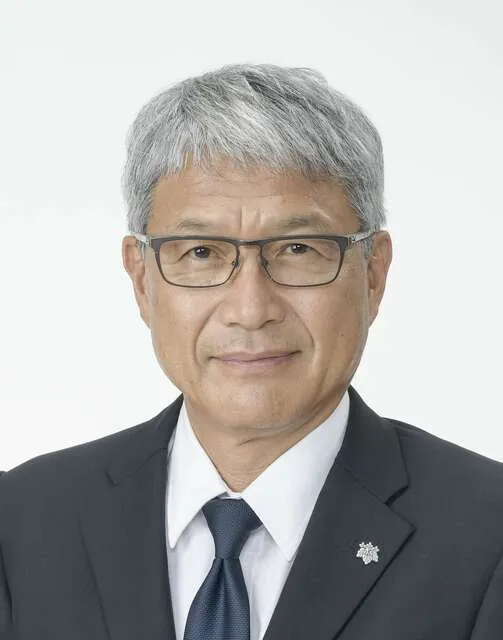2025-09-25 コメント: 1件 ▼
石垣市議会「君が代」調査可決 国歌教育を拒む議員の無責任
日本の国歌を義務教育課程で歌えるようにすることは、国民として当然の教育課題である。 そもそも学習指導要領で国歌指導が明記されている以上、学校教育において子どもが歌えるようになるのは当然の到達目標である。 義務教育の中で歌えるようになることは、音楽教育の一部であると同時に、国民としての基礎的教養の一つである。
石垣市議会で「君が代」調査可決
沖縄県石垣市議会は2025年9月24日、定例会最終本会議で「児童生徒が国歌『君が代』を歌えるかどうか」に関するアンケート調査実施を求める意見書を賛成多数で可決した。結果は賛成14、反対7。アンケートは「国歌を知っているか」「歌えるか」「授業で習ったか」「式典で歌っているか」の4項目で構成され、市長と教育長に提出される。
賛成した議員は「学習指導要領に基づき、児童生徒がきちんと歌えるようにすることは必要」と主張した。これは単なる政治的意思表示ではなく、教育現場の実態を把握するための基本的調査である。日本の国歌を義務教育課程で歌えるようにすることは、国民として当然の教育課題である。
「強制」批判への反論
一部の議員は「子どもへの強制になる」として反対した。しかしこの主張は論点をすり替えている。調査は「歌えるかどうか」を確認するものであり、児童に強制的に歌わせる行為とは別である。そもそも学習指導要領で国歌指導が明記されている以上、学校教育において子どもが歌えるようになるのは当然の到達目標である。調査を拒むことは、現場の指導状況を検証しないまま放置することにつながり、教育の責任を果たさない態度といえる。
市民の声として「子どもたちが国歌を十分に歌えていないのではないか」という懸念が出ている以上、現状把握を行うのは行政と教育委員会の当然の責務である。反対した議員は「政治の介入」を理由にするが、学習指導要領の履行確認は政治介入ではなく教育行政の正当な監督機能である。
国歌教育の意義
国歌は国民統合の象徴であり、式典や国際行事で必ず用いられる。国歌を歌えないという状況は、国際社会の一員として不自然であり、国家意識の希薄化を招く。義務教育の中で歌えるようになることは、音楽教育の一部であると同時に、国民としての基礎的教養の一つである。
国旗や国歌を学ぶことは、国際理解教育とも矛盾しない。むしろ自国の象徴を正しく理解し、尊重できてこそ、他国文化との対話や相互尊重が成立する。今回の調査は、そうした基礎教育の達成度を把握するだけのものであり、「強制」との批判は的外れである。
市民の受け止め
市民の反応も分かれているが、教育責任を果たす観点から調査実施を支持する声は少なくない。
「国歌を学ぶのは当然。調査を拒む理由が分からない」
「子どもに無理強いではなく、教育の到達度を知ることが大事だ」
「反対議員は義務教育の責任を軽んじている」
「式典で国歌を歌えないのは国民として不自然だ」
「調査は教育改善の手がかりになるはずだ」
教育の責任と今後の課題
今回の議決は、国歌教育の到達度を明らかにする第一歩である。反対した議員の「強制になる」との主張は、教育現場への正しい監督機能を否定し、国歌を軽視する姿勢を示すものだ。義務教育は学ぶべきことを体系的に身につけさせる制度であり、その一部に国歌指導が含まれている以上、現場が適切に実施しているかを調べるのは当然である。
今後は調査結果を踏まえ、授業での指導方法や式典での運用を改善していくことが重要になる。国歌を子どもたちが歌えるようにすることは、日本人としての共通基盤を築く教育の根幹であり、政治的対立の道具にしてはならない。
この投稿の中山義隆の活動は、86点・活動偏差値59と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。