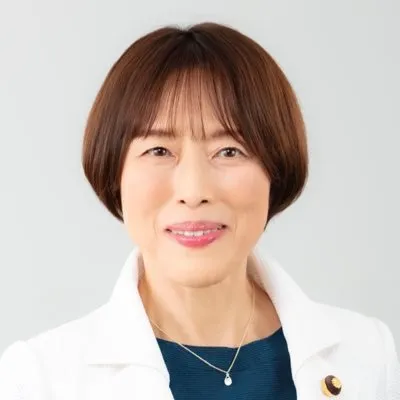2025-12-22 コメント投稿する ▼
本村伸子が訴えた高知の周産期医療危機、分娩施設減と医師不足が深刻化
県内では産婦人科医の不足が続き、分娩を扱う施設がない医療圏もあるため、受診や出産のために長距離移動が必要になる妊婦がいます。 国と県の資料では、高知県の分娩施設は約15年で21施設から9施設へ減り、分娩の受け皿が約6割減ったと整理されています。
高知の周産期医療、分娩の受け皿が縮小
2025年12月22日、日本共産党(共産党)の本村伸子衆議院議員と中根耕作衆議院四国比例予定候補が高知県を訪れ、県や医療機関から周産期医療の実態を聞き取りました。
周産期は妊娠22週以降から出産後7日未満までを指し、母体と赤ちゃんの状態が急変しやすい時期です。出産できる場所までの距離と搬送体制は安全に直結し、待ったなしの判断が求められます。
県内では産婦人科医の不足が続き、分娩を扱う施設がない医療圏もあるため、受診や出産のために長距離移動が必要になる妊婦がいます。移動中に分娩が始まり搬送が間に合わない例も出ていると関係者が説明し、高幡医療圏で分娩施設がないことが現実のリスクとして語られました。
国と県の資料では、高知県の分娩施設は約15年で21施設から9施設へ減り、分娩の受け皿が約6割減ったと整理されています。施設が減れば夜間や休日の受け入れに余力がなくなり、妊婦側の選択肢も狭まります。
「夜に陣痛が来たら、どこに行けばいいのか不安です」
「予約が埋まっていて受け入れ先が見つからないのが怖い」
「里帰りしたいのに、地元で産めないと言われました」
「助産師さんに頼りたいけど、緊急時の搬送が心配です」
「産科が減ると若い人が住めなくなると思います」
県の医師確保策は前進、それでも崩れる現場
一行は県庁で医療政策部門から説明を受け、県側は奨学金制度などで医学生を支援し、分娩に関わる産婦人科医師が前年の36人から44人に増えたと報告しました。
ただ、数が増えても勤務の偏りや当直の負担が解決しない限り、現場の体感は変わりにくいのが実情です。県側は少子化で分娩数が減り収益が立ちにくいことや医師の高齢化が重なり、体制が安定しにくいと課題を挙げました。
出生数自体も減っており、県内の統計では2014年の出生数が5015人だったのに対し、2024年は3233人まで減っています。需要が細る一方で、救急や帝王切開など「絶対に止められない機能」は残るため、規模縮小がそのまま安全性の低下につながりやすい構造です。
国の検討資料では、分娩施設や産科医が存在しない周産期医療圏が生まれないよう体制を組み直す方針が示されています。高知県の協議の場でも、周産期母子医療センターの機能を複数病院で維持しつつ、限られた人員で安全性を保つ具体策が議論されています。
中核病院に低リスク分娩が集中し受け入れ調整
続いて一行は県内の中核病院の高知医療センターを訪ね、同センター側は分娩施設の減少でローリスク分娩の受け入れが急増し、スタッフ負担が増していると説明しました。
ハイリスク妊娠の管理や新生児集中治療室(重い病気の赤ちゃんを治療する病棟)などの機能は高度で、担当できる医師や助産師が限られます。ローリスクの分娩が増えても現場の仕事が軽くなるわけではなく、夜間対応や緊急手術に備える体制が常に必要です。
同センターは2025年10月に、出産予定の妊婦の受け入れを2026年3月まで制限すると公表しています。受け入れ制限は「断るための制度」ではなく、崩壊を避けて救える命を守るための調整であり、現場が限界に近いサインでもあります。
同センター側は国への要望として、産婦人科医の確保に加え、診療科の偏在を是正する仕組みを求めました。必要な診療科に人が集まりにくい状況を放置すれば、患者は残っても担い手がいなくなるという矛盾が広がります。
助産院の役割と国の責任、守るべき安全網
最後に一行は香南市の助産院を訪問し、助産師による継続的な妊婦健診や出産支援の意義を確認しました。助産院は妊婦に寄り添える一方、異常が起きた場合は病院への搬送が前提になるため、受け入れ先の病院が逼迫していれば助産院だけでは完結しません。
県内では、病院の医師が妊婦健診の一部を地域側と分担し、出産は中核病院で受ける仕組みづくりも検討されています。院内助産やセミオープンといった運用は、医師の不足を埋める近道ではなく、限られた医療資源を安全に回すための手段です。
それでも最後に必要になるのは、夜間も含めて分娩と救急を支える医師と助産師の数です。本村伸子氏は、聞き取った要望を国政に届け、国の医療政策の下で生じる困難の打開につなげたいと述べました。