2025-11-27 コメント投稿する ▼
国保料上限5年連続上げで110万円に、実質増税路線が加速、中間層への影響拡大も懸念
厚生労働省は2025年11月27日、自営業者らが加入する国民健康保険の年間保険料上限額を2026年度から1万円引き上げ、110万円とする方針を社会保障審議会で了承されました。 しかし、政府は「高齢化による医療費増大」を理由に、毎年のように保険料上限を引き上げており、実質的には税と変わらない強制徴収が拡大し続けています。
実質的な増税が止まらない「隠れ増税」の実態
厚生労働省は2025年11月27日、自営業者らが加入する国民健康保険の年間保険料上限額を2026年度から1万円引き上げ、110万円とする方針を社会保障審議会で了承されました。この上限額引き上げは5年連続となり、実質的な増税として国民生活を圧迫し続けています。2008年から現在まで、上限額は約31万円も上昇しており、政府による「隠れ増税」の実態が浮き彫りになっています。
国民健康保険は自営業者やフリーランス、年金受給者など約2660万人が加入する重要な社会保障制度です。しかし、政府は「高齢化による医療費増大」を理由に、毎年のように保険料上限を引き上げており、実質的には税と変わらない強制徴収が拡大し続けています。
5年連続値上げの実態と影響範囲
2022年度から2026年度までの上限額推移を見ると、連続的な負担増の深刻さが明確になります。2022年度は3万円、2023年度は2万円、2024年度は2万円、2025年度は3万円、そして2026年度は1万円と、5年間で計11万円もの大幅増額が実施されています。
現在の上限額109万円から110万円への引き上げにより、年収1170万円以上の世帯が新たな負担増の対象となります。対象世帯は全加入者の約1.5%とされていますが、これは政府が意図的に「少数の高所得者のみ」という印象を与えるための数字操作に過ぎません。
「毎年毎年値上げばかりで、もはや税金と同じじゃないか」
「高所得者と言っても、税金も高いのにさらに保険料まで上がるなんて」
「今は影響ないけど、この調子だと中間層にもいずれ影響が出てくる」
「政府は増税と言わないで実質増税を続けている、姑息なやり方だ」
「保険料という名前だけど、実際には強制的な税金でしょこれ」
中間所得層にも迫る負担拡大の危機
政府は「高所得者のみが対象」と強調していますが、実際には中間所得層への影響も無視できません。各自治体レベルでも保険料率の引き上げが続いており、2022年度には全国1648自治体中457自治体が値上げを実施しています。
東京都新宿区の例では、年収900万円以上の世帯で3万円の負担増が生じており、決して超高所得者だけの問題ではないことが分かります。また、過去10年間で上限額は77万円から110万円へと30万円以上も上昇しており、月平均で約2万5000円の負担増となっています。
厚生労働省は「中間所得層への配慮」を理由に挙げていますが、実際には保険料率そのものの引き上げも各自治体で進んでおり、結果的に全所得層で負担が増加している状況です。
「医療費増大」を口実とした財政政策の限界
政府が毎年の値上げ根拠として挙げる「高齢化による医療費増大」ですが、これは構造的な問題であり、保険料引き上げだけでは根本的解決になりません。2022年時点で65歳以上の高齢者が人口の29.1%を占め、75歳以上の人口は16.3%に達しており、今後もさらに増加が予想されます。
しかし、問題は医療費増大そのものではなく、政府が抜本的な制度改革を避けて小手先の値上げを繰り返している点にあります。国民健康保険の構造的問題として、加入者の平均年齢が高く所得水準が低いという特性があるにも関わらず、負担だけが一方的に増加し続けています。
さらに深刻なのは、国民健康保険料には減免制度があるものの、申請手続きが複雑で十分に活用されていない現実です。結果として、真に支払い能力のある層への適正負担ではなく、制度を理解し活用できる層とそうでない層での不公平な負担配分が拡大しています。
政府はこの「隠れ増税」路線を改め、医療制度全体の抜本的見直しと、国民負担の公平性確保に真剣に取り組むべき時期に来ています。毎年の値上げありきの政策では、国民の生活基盤そのものが揺らぎかねません。
この投稿の上野賢一郎の活動は、0点・活動偏差値42と評価されています。下記GOOD・BADボタンからあなたも評価してください。



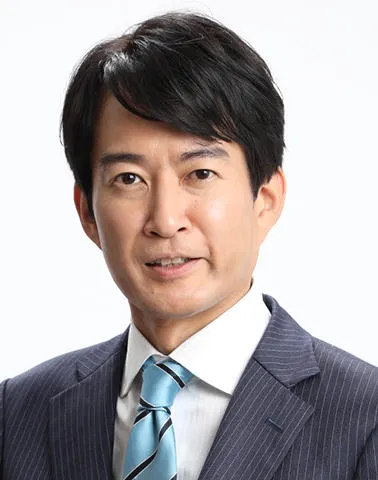
























![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)

