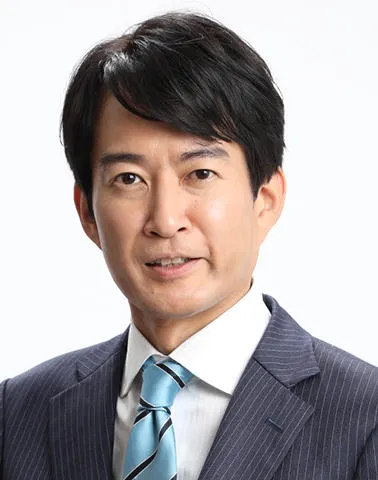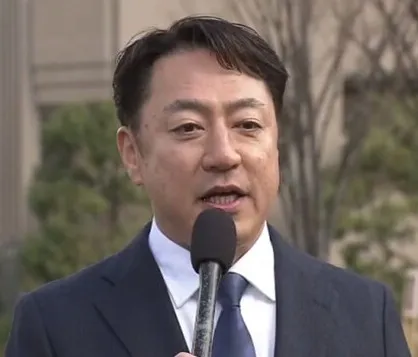2025-11-25 コメント投稿する ▼
生活保護費 全額補償を求める 抗議と司法判断の波紋
11月25日、中央社会保障推進協議会(中央社保協)は、厚生労働省(厚労省)前で抗議行動を行い、2025年6月に最高裁判所が過去に実施された生活保護費の引き下げを「違法」と判断したことを受けて、すべての生活保護受給者に対して「基準額の全額を補償せよ」と迫りました。
行動のきっかけと要求内容
11月25日、中央社会保障推進協議会(中央社保協)は、厚生労働省(厚労省)前で抗議行動を行い、2025年6月に最高裁判所が過去に実施された生活保護費の引き下げを「違法」と判断したことを受けて、すべての生活保護受給者に対して「基準額の全額を補償せよ」と迫りました。
参加者は「生活保護基準額の全額を補償せよ!」「政府は原告と生活保護利用者を差別するな!」とのコールを行い、実際の減額によって生活に打撃を受けた受給者の声を政府に突きつけました。原告である武田新吾さんは「原告には補償案が出されているが、他の利用者にはわずか10万円では到底足りない。私たちはもっと大きな被害を受けている」と訴え、全利用者への真の救済を求めました。
また、中央社保協の 林信悟 事務局長は「全員に全額補償を求める」と断言し、他の福祉団体の代表も「一部補償だけでは差別と分断を生む」「国は全国どこでも公平な福祉を提供すべきだ」と強く批判しました。
最高裁判決の意味と厚労省の対応案
そもそも問題となったのは、2013〜2015年に施された生活保護の「生活扶助」の大幅な引き下げでした。国は物価の下落などを理由に削減を行い、当時で約670億円規模のコスト削減を図っていました。
しかし今年6月27日、最高裁はこの引き下げについて「違法」と判断。補助基準の根拠となる統計処理や手続きが客観性や妥当性を欠いており、憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を脅かすものと認定しました。これは引き下げを撤回し、国による支払いの義務を認めたことを意味します。
これを受け、厚労省の専門委員会は補償案を検討。その中では「全額補償」「一部補償」の両案を報告書の選択肢に挙げました。だが最終的に厚労省は、いわゆる「一部補償」で対応する方向を打ち出したとされます。具体的には、原告ら一部には補償を上乗せするが、一般の受給者には限定的な補償とする案です。これに対して支援団体や原告側からは「違法判決への応答として不十分」「事実上の差別だ」と強い反発が出ています。
受給者・市民の視点:裁判勝訴でも不安続く
この問題に対して、ネット上や市民の間では「裁判で勝っても補償が不十分なら意味がない」との声が少なくありません。
「裁判で違法と言われたのに、なぜ全額戻さないの?」
「一部だけじゃ、やっぱり生活できない」
「こんなやり方じゃ、不安だけが残る」
「本当に国は弱い立場を守る気あるのか」
「補償ありきじゃなく、人として尊重してほしい」
こうした声には、「裁判が認めるべき最低ラインなら、国は守る義務がある」「受給者の命と暮らしがかかっている」という切実さがにじみ出ています。たとえ判決で勝っても、補償が不十分なら「勝利」は形だけだ、との不満も根強いようです。
なぜ全額補償が必要か:社会保障の理念と実態
支援団体や社会福祉学の専門家は、補償を一部にとどめることを「制度としての矛盾」と批判します。生活保護は国の責任で生活の最低基準を保証する制度であり、最高裁が不当と断じた引き下げ分を放置すれば、法律違反の状態が延々と続くことになるからです。
また、補償が限られた人にしか行われないなら、受給者間に不公平が生まれ、生活保護そのものへの社会的偏見や分断を助長しかねません。多数の人が補償を待ち望んでおり、裁判勝訴から事実上の救済までに時間がかかれば、生活苦に苦しむ人々が救われないままとなります。
今後の焦点と政府の責任
現在、厚労省がどのような補償スキームを最終的に採るかが最大の焦点となっています。全額補償か、それとも一部のみか――この選択が、制度の公平性と国民の信頼を大きく左右します。支援者や原告側は、「補償とともに国としての謝罪」「再発防止策」も併せて求めています。
一方で、国の財政や他制度との兼ね合いを理由に限定的な対応を主張する声もあるでしょう。しかし、そもそも違法とされ、元の水準に戻す必要がある以上、「経費節約」の論理を先行させるのは制度の理念に反します。
今後、政府は裁判の結果を受け止め、実効性ある救済措置と、生活保護制度の信頼回復に真摯に取り組む必要があります。社会保障の根幹にかかわる今回の問題を、単なるコストの問題で片付けることは許されません。