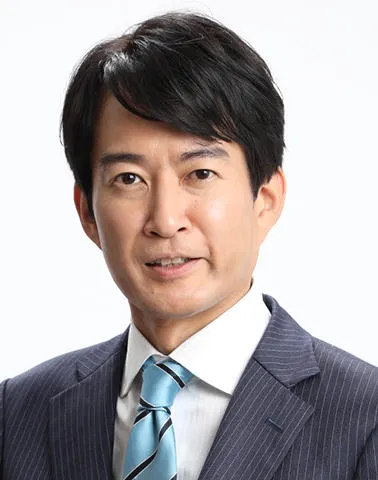2025-11-06 コメント投稿する ▼
生活保護減額補償で政府判断分かれる 最高裁違法認定受け厚労省は一部支給方針
厚生労働省は2025年11月6日、生活保護費の2013年から2015年にかけての引き下げを違法とした最高裁判決への対応について、当時の減額分の追加支給を全額ではなく一部にとどめる方向で調整に入ったことが明らかになりました。
厚生労働省は2025年11月6日、生活保護費の2013年から2015年にかけての引き下げを違法とした最高裁判決への対応について、当時の減額分の追加支給を全額ではなく一部にとどめる方向で調整に入ったことが明らかになりました。同省は当時の一般低所得世帯の消費実態を踏まえると、全額支給は難しいと判断したとしています。
原告側は全額補償を求めており、反発が出るのは必至です。当時の受給者は約200万人に上り、減額は累計で数千億円規模になると見られています。
最高裁判決が認めた違法性
2025年6月27日の最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、2013年から15年にかけて国が生活保護費のうち食費や光熱費など日常生活を維持するための「生活扶助費」を最大10%引き下げたことについて、基準額引き下げの大きな根拠となった「デフレ調整」に裁量権の範囲の逸脱や乱用があり、生活保護法に違反すると認定しました。
国は13年から15年にかけて生活保護費を約670億円削減し、うち約580億円は厚労省が独自に算出した08年から11年の物価下落率(4.78%)を踏まえた「デフレ調整」によるものでした。判決では、基準額を改定する際に物価下落率を指標の一つとするのは許容されるものの消費実態を把握するには限界があると指摘し、これまで別の方式を用いて基準額を改定していたにもかかわらず、専門部会による審議を経なかったことを問題視しました。
しかし、最高裁判決は基準引き下げの根拠のうち物価下落を反映するデフレ調整を違法とする一方、受給者間の公平を図った、ゆがみ調整は違法ではないとしました。厚労省は今回の一部補償方針の根拠として、この点を重視していると見られます。
支援団体と当事者からは強い懸念の声
「保護費が引き下げられ物価高も加わり、何のぜいたくもしていないのに苦しい。食べる量を減らす以外なく、冷房も暖房も使えない」
「基準減額と物価高騰で生活が苦しい。服、下着は買えていない状況が続いている」
「今年の夏は猛暑と物価高で、とんでもなく地獄を見ている。電気代が怖くてエアコンが使えない」
「私たちの生存権が侵害された状態を解消するため、速やかに差額を払ってほしい」
「最高裁判決を骨抜きにしようとしているのではないかと懐疑的に見ている」
原告の新垣敏夫さん(71歳・大阪)は「私たちの生存権が侵害された状態を解消するため、速やかに差額を払ってほしい」と述べ、専門委員会については「あらを探して最高裁判決を骨抜きにしようとしているのでは」と懐疑的な見方を示しています。
日本弁護士連合会が2024年12月3日を中心に実施した「全国一斉生活保護ホットライン」では、「保護費が低すぎて生活できない」などの相談が、生活保護利用中の者からの相談190件中49件(約26%)を占めました。物価高騰の中で、生活保護受給者の生活困窮が深刻化している実態が浮き彫りになっています。
厚労省の対応と今後の課題
厚労省は2025年8月以降、行政法などの識者による専門委員会で対応を協議してきており、近く取りまとめ議論に入る予定です。これまでの専門委では追加支給の是非や、支給する場合の水準などについて議論が行われています。
厚労省は既に死亡している人は追加支給の対象外とする案なども提示していました。原告弁護団によると、裁判が10年以上の長期間に渡ったため、原告の2割を超える232名がすでに亡くなり、勝訴判決を聞くことはできませんでした。
政府、与党内では「当時の受給者全員に追加支給せざるを得ない」との認識が広がっている一方で、立法措置が必要との指摘があり、国会への法案提出も視野に入れています。
物価高騰の中で続く基準額据え置き
現在の物価高騰は生活保護受給者の生活をさらに厳しくしています。消費者物価指数は2020年以降連続して上昇し続け、2020年を100とした2024年10月分の消費者物価指数は109.5(前年同月比2.3%上昇)で、中でも光熱・水道は111.1(同3.2%上昇)、食料は120.4(同3.5%上昇)となっています。
厚労省は2025年度の生活保護費について月500円程度の引き上げを調整していますが、物価高騰に追いついていないのが実情です。支援団体は抜本的な基準額の引き上げを求めていますが、財務省は11月に支給額の引き下げを求めており、政府内でも意見が分かれています。
生活保護の基準は5年おきに見直しが行われており、2013年に続き、2018年にも引下げが強行されました。2023年見直しでは急激な物価高騰を踏まえ、特例的な加算を行い引下げを回避しましたが、2025年度以降の基準については改めて検討するとの方針が示されています。
最高裁が国の政策決定を裁量権の逸脱として違法と認めることは珍しく、画期的な判決と評価される一方で、厚労省の今回の方針は判決の趣旨に反するとの批判も予想されます。受給者の生存権保障と国の財政負担のバランスをどう取るかが、今後の大きな焦点となります。