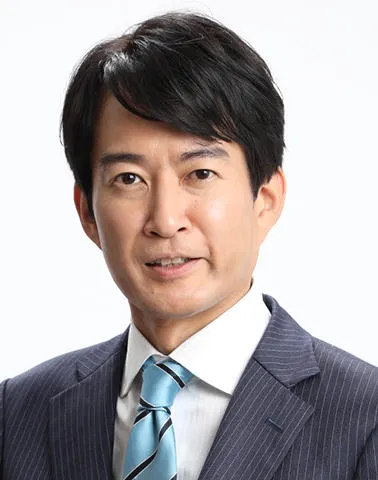2025-10-29 コメント投稿する ▼
国保料値上げが全国33%超 都道府県化の弊害と住民負担の現実
2025年度、全国の自治体で国民健康保険料(税)の値上げが広がっています。 調査によると、577自治体(全国の33.2%)が保険料を引き上げており、2018年度の都道府県化以降では2024年度の676自治体に次ぐ多さとなりました。 保険料の値上げは、こうした層にとって生活の圧迫要因となっています。
3割超の自治体が保険料を引き上げ
2025年度、全国の自治体で国民健康保険料(税)の値上げが広がっています。調査によると、577自治体(全国の33.2%)が保険料を引き上げており、2018年度の都道府県化以降では2024年度の676自治体に次ぐ多さとなりました。
調査は各自治体の公式資料をもとに保険料率を収集し、モデル世帯を設定して試算したものです。モデル世帯(給与年収400万円、専業主婦の妻、小学生2人の4人家族)では、平均保険料が2018年度の39.72万円から2025年度には40.49万円に上昇しています。単身世帯(年収240万円)でも、566自治体(32.6%)が値上げを実施しました。
都道府県化がもたらした負担の連鎖
都道府県別にみると、広島県は全市町で一斉に値上げを行った唯一の地域です。値上げ率が特に高いのは、愛知県(77.8%)、滋賀県(73.7%)、和歌山県(73.3%)、石川県(68.4%)、埼玉県(68.3%)などです。
こうした背景には、2018年度から始まった「国保の都道府県化」があります。それまで市町村単位で運営していた国保が都道府県に集約されたことで、各自治体が独自に行ってきた保険料軽減措置(一般会計からの繰入)が抑制され、結果的に住民負担が増しました。都道府県化は一見、制度の統一化や効率化を目的とした改革でしたが、実際には低所得層や非正規雇用者への重い負担として跳ね返っています。
制度の歪みと住民の声
国民健康保険の加入者は、約4割が年金生活者などの無職層、約3割が非正規雇用者で、その他もフリーランスや請負業など低所得者が多くを占めています。保険料の値上げは、こうした層にとって生活の圧迫要因となっています。
「年金だけで暮らしているのに、保険料がまた上がるなんてやりきれない」
「非正規で働いても手取りが少ないのに、国保料が重くのしかかる」
「子どもの教育費も削って払っている。制度が逆行していると感じる」
「自治体が助けてくれると思っていたのに、都道府県化で冷たくなった」
「暮らしを支えるための保険が、暮らしを圧迫しているのは本末転倒だ」
これらの声は、制度が本来の目的を果たせていない現状を映しています。
国保制度を巡る政治の責任
政府は「保険料の統一化」を掲げ、標準保険料率の導入や「保険者努力支援制度」によって医療費削減を促しています。しかし、これは自治体の裁量を制限し、地域の実情に応じた支援策を取りにくくする要因にもなっています。
憲法が定める「地方自治の本旨」および「条例制定権」は、自治体が住民の実態に応じて独自の政策を講じるために保障されたものです。したがって、自治体が自らの判断で公費を繰り入れることは法的にも可能です。それを制限する仕組みは、地方自治の理念を損ねかねません。
減税と制度見直しの必要性
現状の国保制度は、生活に余裕のない人々にとって過度な負担となっており、減税優先の立場から抜本的な見直しが急務です。医療制度の安定運営と住民負担の軽減は両立可能であり、財政の問題を理由に負担を押し付けるのは筋が通りません。
さらに、自治体が再び自由に公費を繰り入れられるよう制度を修正し、地域実情に応じた柔軟な軽減策を整備することが求められます。政治は財政均衡ではなく、国民の生活を守る責任を果たすべきです。
日本共産党は、住民生活を守るために1兆円規模の公費投入を提案していますが、政権側は財政規律を優先し、減税や負担軽減よりも「制度の均一化」を重視しています。これは国民生活の安定とは逆方向の政策です。
制度改革は必要ですが、方向を誤れば制度そのものが崩壊します。保険料引き上げではなく、減税と支援拡充による構造的立て直しこそが必要です。