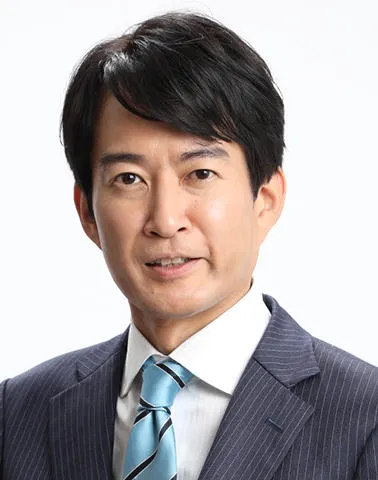2025-10-31 コメント投稿する ▼
生活保護加算も違法減額 のべ443万人に影響、再引き下げへの懸念
国の大幅な生活保護基準引き下げに伴い、加算支給も同様に削減されていた実態が明らかになりました。 この引き下げは、2013~2015年に実施された保護基準の「デフレ調整」を巡るもので、最高裁判所がこの調整を違法と判断しています。 しかし、厚労省は仮に追加支給をする場合でも、保護基準そのものを改めて引き下げる案を示しており、加算分についても再引き下げを行う恐れがあります。
引き下げ「加算」まで波及
国の大幅な生活保護基準引き下げに伴い、加算支給も同様に削減されていた実態が明らかになりました。特に、母子加算や障害者加算、冬季加算などが対象となり、該当者はのべ約443万人にも上ることが厚生労働省の資料で判明しました。
この引き下げは、2013~2015年に実施された保護基準の「デフレ調整」を巡るもので、最高裁判所がこの調整を違法と判断しています。
判決の内容と加算支給への影響
2013~2015年、保護費の基準が物価変動率のみを根拠に減額される「デフレ調整」が行われました。これについて、最高裁は2025年6月27日、こうした方法を「専門的知見が認められず、厚生労働大臣の裁量権の逸脱・乱用」と判断しました。
厚労省資料によると、デフレ調整の適用を受けて現在まで見直しが行われていない加算では、期末一時扶助が約187万人、障害者加算が約37万人、合計のべ約239万人が対象でした。
また、過去にデフレ調整が適用された加算として、冬季加算・居宅分が約186万人、母子加算が約7万人、合計のべ約204万人が該当します。つまり、加算支給分まで引き下げられていた可能性が極めて大きいということです。
追加支給と“再引き下げ”のリスク
今後、判決を受けて、基準引き下げによる減額分の差額支給が検討されています。原告や支援団体からは「差額を速やかに支給してほしい」という声も上がっています。
しかし、厚労省は仮に追加支給をする場合でも、保護基準そのものを改めて引き下げる案を示しており、加算分についても再引き下げを行う恐れがあります。
それは、違法とされた「デフレ調整」と同様の考え方を使って、再び被保護者の支援水準を下げる可能性を含んでおり、支援を必要とする人々にとっては重大な懸念です。
制度の根幹と政治的背景
本件の背景には、制度運用の過程で政治的な意図があったとの指摘があります。特に、保護基準引き下げをめぐっては、所得の低い層への支援を削る政策決定が財政削減の一環として推進された経緯がありました。
ここで問われるのは、生活保護制度が憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に沿って運用されているかという点です。最高裁も「判断過程および手続に過誤、欠落がある」と明言しています。
加算支給を削ることは単なる金額の問題ではなく、生活保護制度の「補完的支援」の部分を失わせる行為でもあります。母子世帯や障害のある世帯では、この加算が生活の支えそのものでした。
国民・受給者の声
「ずっとギリギリでやってきたのに、さらに削られていたと聞いて怒りを感じた」
「母子加算が減らされていたなんて知らなかった。子どもを育てるのがさらに難しくなった」
「追加支給と言われても、再び引き下げる案が出てるって話を聞いて絶望的」
「制度は助けになると信じてた。でもこんなやり方なら期待できない」
「最低限の生活を保障する仕組みが、政治的な理由で変わってしまっているのではないか」
これらの声が示すのは、制度変更が人々の生活を「見えない形」で蝕んでいたという現実です。
政策的な課題と今後の対応
まず、制度設計と運用における裁量の透明性と専門的検討の必要性が強く求められています。最高裁が示した通り、基準引き下げの判断には、十分な専門委員会審議や説明責任が欠けていました。
次に、生活保護制度は、受給者にとって予測可能で安定したものであるべきです。加算支給が減らされ、さらに再引き下げの可能性があることは、制度への信頼を根本から揺るがします。
また、政治的な観点から見ても、生活保護制度を「財政削減の道具」とすることは、公平性と国民への信頼を失う結果を招きます。制度は国民の生活を守るためのものであり、政治の思惑で左右されるべきではありません。
今後必要なのは、追加支給の実施だけではなく、再引き下げを前提としない安定した保護水準の確立です。国は誤った政策を繰り返さず、生活の安全網としての役割を取り戻す責任があります。