2025-10-30 コメント投稿する ▼
医療・福祉業の精神障害労災が2倍増加 2024年白書で過去最高水準
厚生労働省が2025年10月に発表した「過労死等防止対策白書」によると、2024年の自殺以外の精神障害事案に関する労災保険給付請求件数を業種別に分析した結果、医療・福祉業は969件に上り、2020年の478件と比べて2倍以上に増加しました。 ただし医療・福祉業の969件という数字は、これらの業種と比べて明らかに突出しており、医療・福祉職の危機的状況を示しています。
医療・福祉職における精神的負荷が急速に高まっています。厚生労働省が2025年10月に発表した「過労死等防止対策白書」によると、2024年の自殺以外の精神障害事案に関する労災保険給付請求件数を業種別に分析した結果、医療・福祉業は969件に上り、2020年の478件と比べて2倍以上に増加しました。わずか4年間で請求件数がほぼ倍増したという異常事態です。
この急増の背景には、医療機関や福祉施設の深刻な人手不足と、患者や利用者への対応の重圧が重なった状況があります。医療職(医師・看護師)に限定すると、3年ごとの平均事案数は2011年から2016年の14件から、2017年から2019年には24.7件へと増加し、2020年から2022年には46.7件となり、わずか6年間で3倍以上に跳ね上がっています。
医師の働き方改革が追いつかない現実
医師や看護師の働き方改革が2024年4月に本格施行されたにもかかわらず、同年の請求件数は過去最高水準に達しました。時間外労働の上限規制が導入されても、制度面の改善だけでは現場の過重労働と精神的負荷を根本的に解決できていない実態が浮き彫りになっています。
医師の働き方改革では、時間外労働を原則として年960時間以下に制限する基準が設けられています。しかし多くの医療機関では地域医療を支える特例により年1860時間まで時間外労働が認められており、実質的には規制緩和の側面も残っています。一般企業の上限である年720時間と比較すると、医療業界での対策は不十分な状況が続いています。
「医師の働き方改革が始まったのに、精神疾患での労災請求がむしろ増えている。改革の掛け声だけで現場が変わっていない証拠だ」
「看護師不足が深刻で、一人当たりの負担がさらに増えている。改革で医師の時間が減った分が看護師に転嫁されている」
「患者さんの死に直面する環境で、十分な休息も取れず働き続ければ、誰だって精神を病む」
「福祉施設でも同じ。介護職員は月給20万円程度で、認知症の利用者さんからの暴力や暴言に耐えている」
「処遇改善加算が増額されても、給与が実際に上がらない施設も多い。働く理由が見つからない」
医療現場での悲劇的な出来事が引き金に
白書で注目すべきは、精神障害が発生する具体的な出来事の分析です。医療業界で顕著な原因として、「悲劇的な事故や災害の体験・目撃」と「同僚からの暴行やいじめ・嫌がらせ」がいずれも全産業平均の2倍以上の件数となっています。医療従事者は日常的に患者の苦痛や死に直面する環境にあり、これがPTSDやバーンアウト(燃え尽き症候群)のリスクを高めています。
医療の現場は命に関わる瞬間が繰り返される緊張の連続です。救命に失敗した経験、悲鳴を上げる患者、家族の絶望的な表情。こうした場面は医療従事者の心に深い傷を残します。さらに人手不足から十分な休息も得られず、心理的ケアも受けられない医療従事者は、やがて心身の不調に陥るのです。
一方、福祉業界でも状況は深刻です。介護労働安定センターの調査では、2024年7月の段階で介護事業所の約6割が介護職員不足を感じており、「大いに不足」という回答は直近10年で初めて3割を超えました。認知症利用者からの暴力や暴言、長時間の力仕事、低い賃金という三重苦のなかで、多くの介護職員が心理的限界に達しているのです。
他業種との比較で見えてくる課題
白書によると、精神障害事案の労災請求件数の業種別動向では、医療・福祉以外にも製造業(537件)と卸売業・小売業(512件)で増加が目立っています。ただし医療・福祉業の969件という数字は、これらの業種と比べて明らかに突出しており、医療・福祉職の危機的状況を示しています。
国が掲げた医療従事者の処遇改善策も進みが遅いままです。介護職員の処遇改善加算は2024年2月から5月にかけて月額平均6000円(2%程度)の引き上げが実施されましたが、給与全体の水準が依然として低く、魅力的な職場環境とは言えません。さらに介護現場で働く職員にとって、2024年度に2.5%、2025年度に2.0%のベースアップが予定されていますが、これが実際の給与に反映されるかは不透明です。
今求められる抜本的な対策
医療・福祉業での精神障害労災が倍増したという事実は、日本の医療・福祉体制の持続可能性に対する警告信号です。時間外労働の上限規制や処遇改善加算という上からの制度改正だけでは、現場の疲弊を止めることはできません。
必要なのは、医療機関や福祉施設への人的資源の抜本的な投下です。医師・看護師・介護職員の大幅な増員によって、一人当たりの業務負担を減らすことが急務となっています。同時に、精神保健相談体制の充実やメンタルヘルスケアの義務化、職場でのパワーハラスメント対策の強化も必要です。
白書が明示する医療・福祉職の苦境は、国民全体の医療・介護サービスの質の低下にも直結する課題です。従事者の心身の健康と尊厳を守らなければ、誰もが安心して医療・福祉サービスを受ける社会は実現できません。














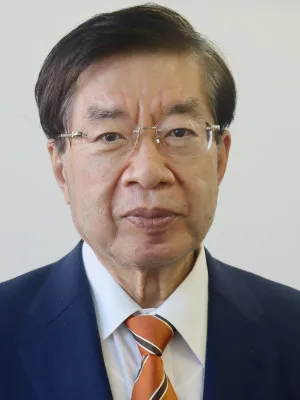












![EBPM[エビデンス(証拠・根拠)に基づく政策立案]とは何か 令和の新たな政策形成](https://m.media-amazon.com/images/I/41y20VDvhnL._SY445_SX342_.jpg)


